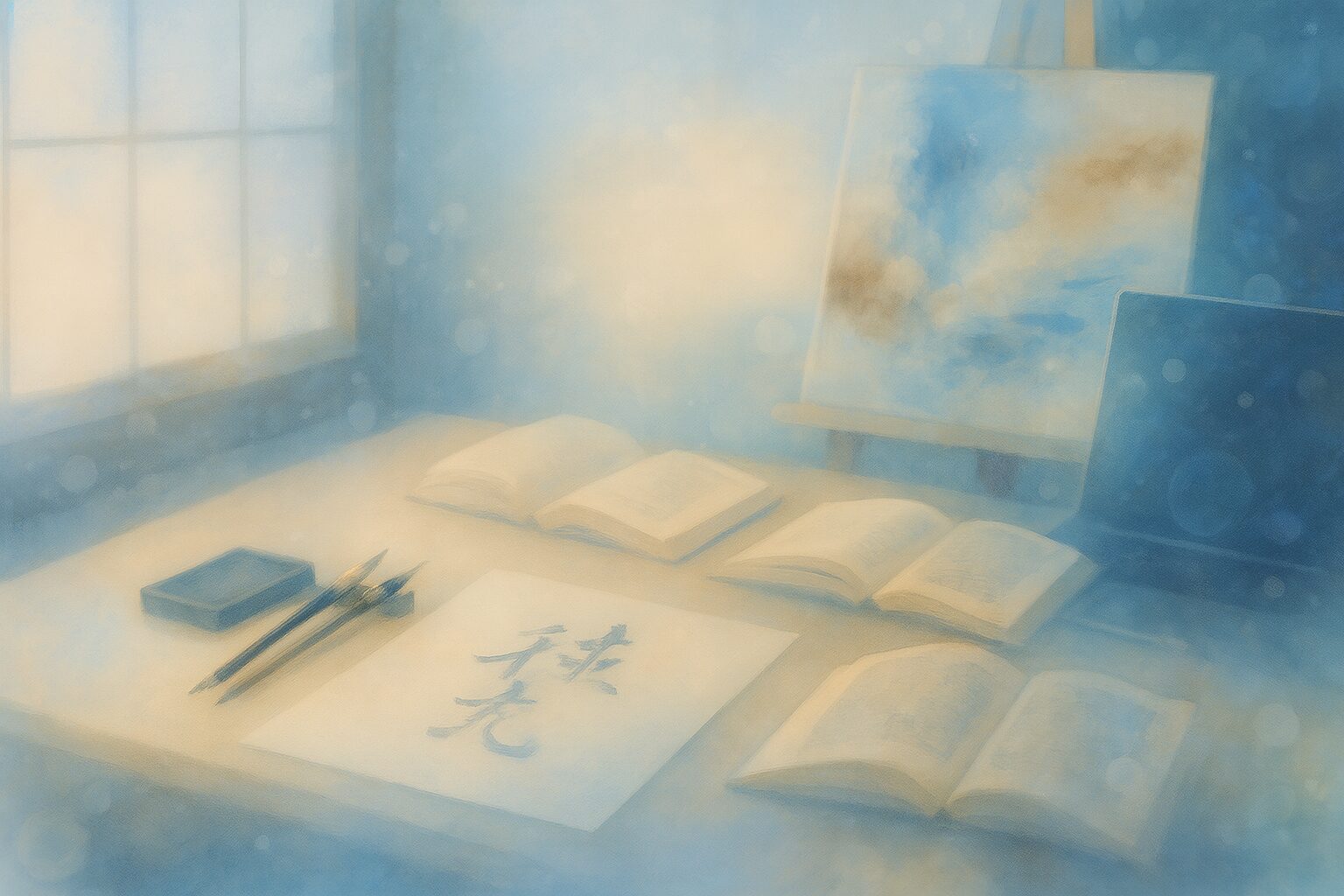序章:余白との出会い
余白という言葉を耳にすると、私は幼い日の光景を思い出す。
母は書道の師範で、墨の香りと和紙の白が日常にあった。
伯父は抽象画家で、アトリエには大胆な色彩とともに、静かな余白が漂っていた。
二人の背中を見ながら育った私は、余白を「何もないところ」ではなく、「何かが始まるところ」として感じるようになった。
一日目:書の余白 ― 静けさの呼吸
母の書における余白は、呼吸のようなものだった。
筆を紙に走らせたあと、母はすぐには筆を置かない。
紙全体を眺め、文字と白との釣り合いを確かめる。
余白はただ残された空白ではなく、文字を引き立て、全体を整える静けさだった。
余白は不足ではなく、調和を生み出すものだ――その感覚が私の中に根づいていった。
二日目:絵画の余白 ― 想像の広がり
伯父の抽象画には、必ず描かれない部分があった。
「ここには何が見える?」
伯父にそう問われると、私は黙り込みながらも、心の奥にいくつもの形や物語を思い描いていた。
描かれていない部分にこそ、視線は引き寄せられる。
そこには一つの正解はなく、見る人の数だけ解釈がある。
母の余白が静謐であったなら、伯父の余白は揺らぎだった。
三日目:哲学の余白 ― デリダとの邂逅
のちに出会ったジャック・デリダの思想は、これらの体験を別の言葉で説明してくれた。
彼は「意味は決して一度で定まらず、常にずれ続ける」と語り、これを「差延(サエン)」と呼んだ。
また「言葉には必ず痕跡があり、不在の影を背負う」とも言う。
母の余白も、伯父の余白も、この哲学と響き合っていた。
余白とは、決定を拒み、可能性を開き続ける場なのだと気づかされた。
四日目:現在の余白 ― 生成AIとの共創
いま私は、生成AIと共に文章を紡いでいる。
AIは瞬時に答えを返してくれるが、その答えには必ず「間」が残っている。
そこに私は自分の感性を差し込み、言葉を揺らがせる。
母の書の白、伯父のキャンバスの余白。
その延長線上に、AIとの共創に息づく「感性の余白」があるのだと思う。
余白は過去の美学にとどまらず、いまもなお新しい形をとりながら息づいている。
終章:そっと佇む余白
余白は、不足ではなく、開かれている。
静けさであり、揺らぎであり、未来を示唆するゆとりでもある。
私はこれからも、余白を感性のまま残していきたい。
その余白は、そっと佇みながら、次の問いを待っている。
そして旅は、まだ続いていく。