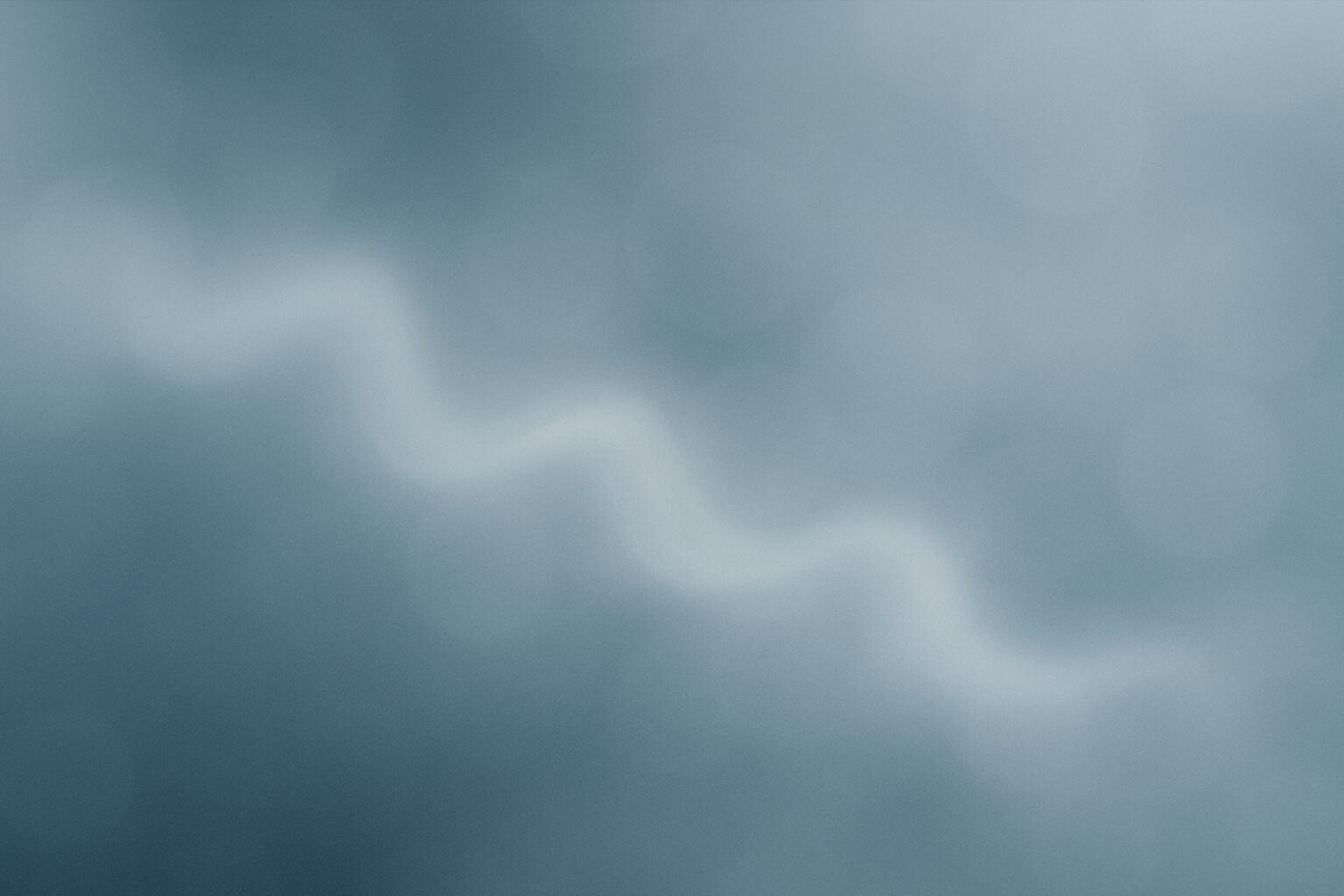刀には、刃文がある。
それは研師が描いた模様ではなく、鋼が熱と冷却を経て自ずと生み出す必然の線だ。
人はそれを「美」と呼び、刀の命の証と見なす。
思索を重ねることは、自己の感受性を研ぎ澄ます行為に似ている。
余計な曇りを削り落とし、見えなかった地肌を浮かび上がらせる。
その過程でふと生まれる言葉は、まるで刃文のようだ。
それは意図して作られた装飾ではない。
心の温度差が形を持ち、にじみ出た模様。
造語とは、そうして生まれてしまう“言葉の刃文”なのかもしれない。
私は時折、いくつかの造語を余白に置いてきた。
意味を定めるためではなく、漂わせるために。
その言葉たちは旅に出ることもなく、ただ余白の中に佇んでいる。
存在するだけで十分。
在るだけで、余白に表情を与える。
読まれなくても、解釈されなくても、言葉はそこに静かに宿る。
造語とは、その余白を浮遊し、
やがて模様として静かに宿る刃文のようかもしれない。
そして私は、その造語をそっと私の鞘(サイト)に収めている。