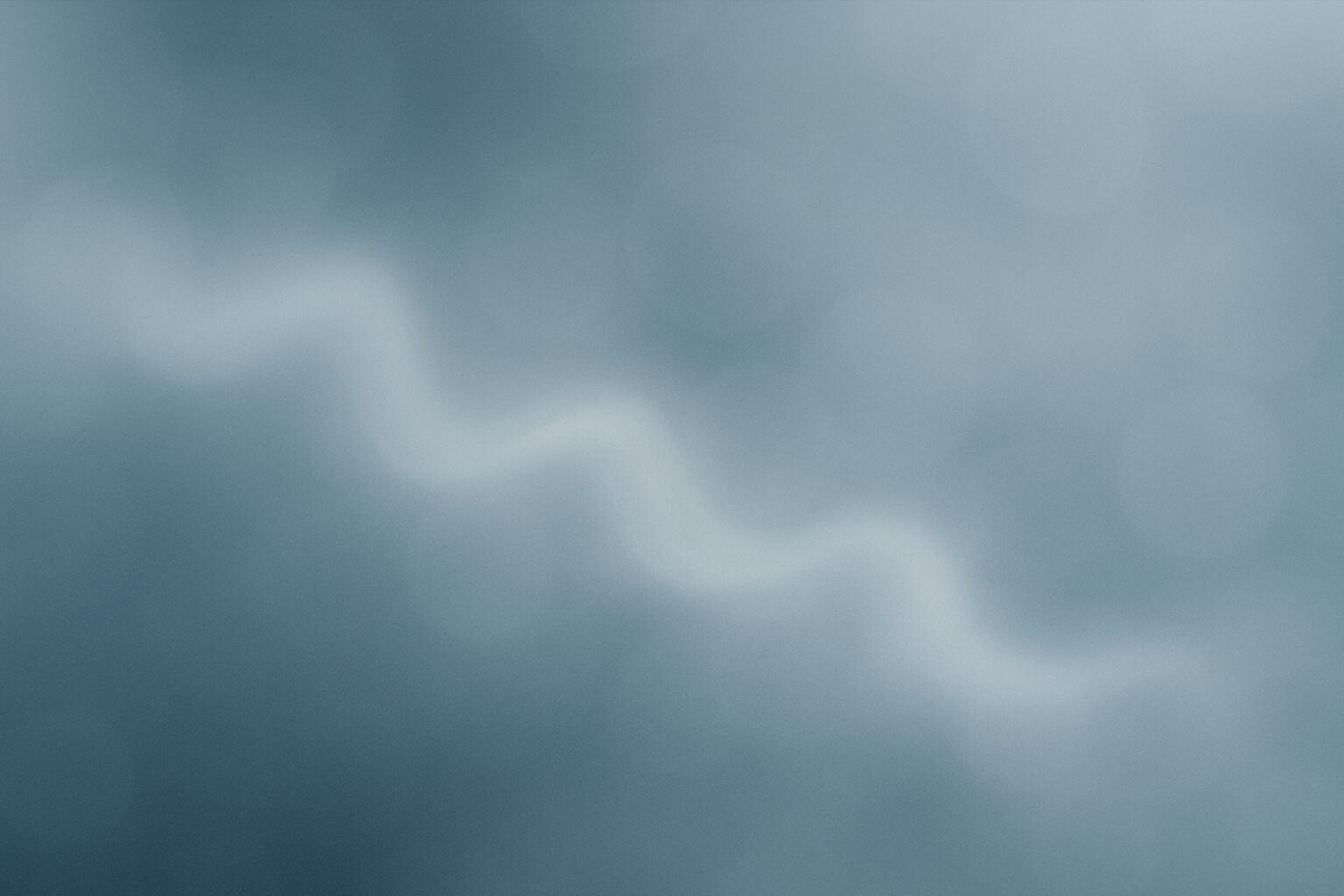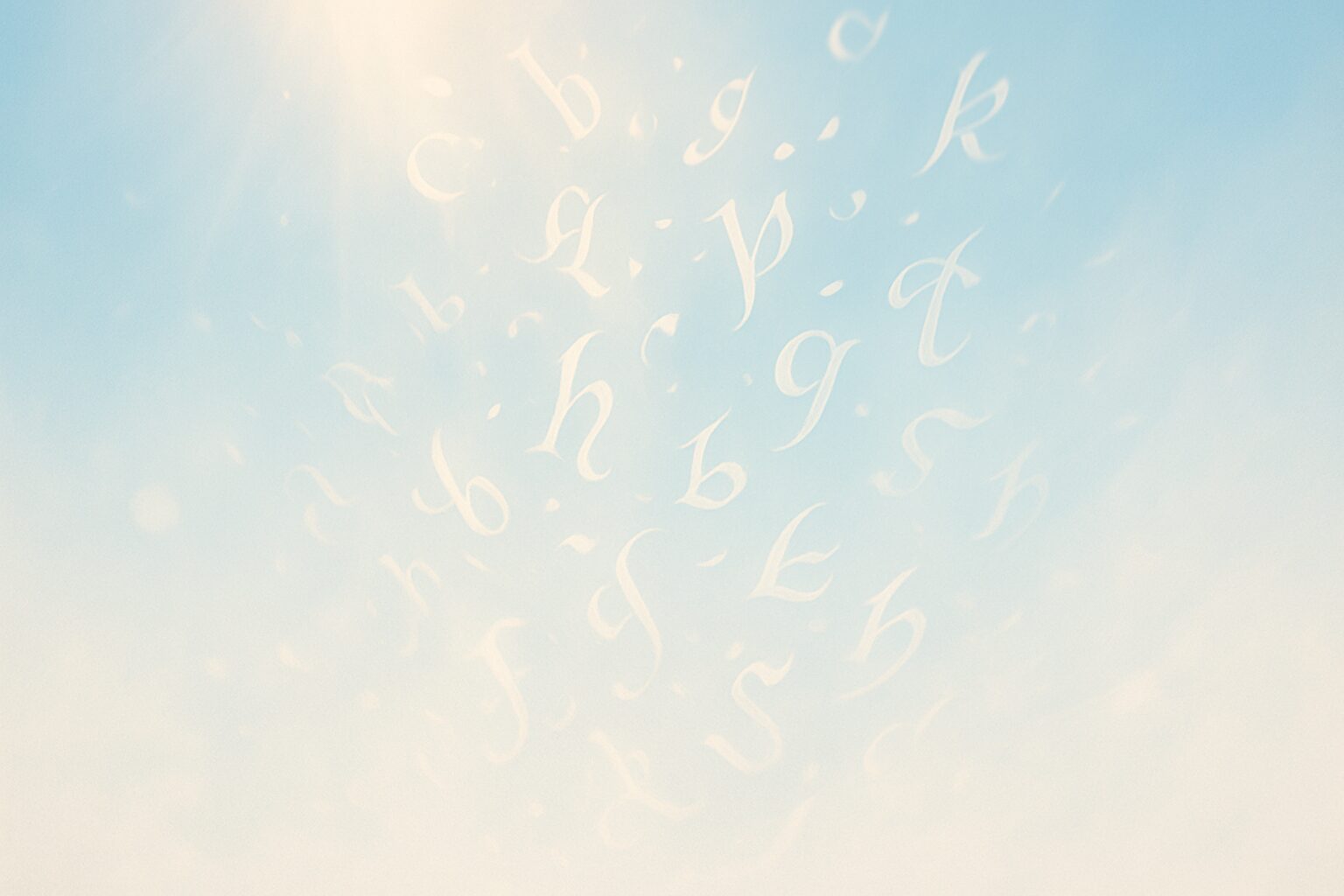言語浮遊とは、論理の重力から解放された状態で言葉が生まれることである。
通常、私たちは「意味を伝えるため」に言葉を選ぶ。目的があり、文脈があり、相手がいる。その重力に引かれて、適切な表現を地上に着地させる。
しかし時として、言葉は重力を振り切る。
「茂みにそっと佇む樹」 「言語浮遊な幽霊船」 「刺激から茂樹へ」
これらの言葉は、説明を求められても困る。意味を問われても答えにくい。でも確かに何かを表現している。
言語浮遊の特徴
重力に逆らって浮上する。 音韻の美しさが意味を上回る。 誤解を恐れない。 偶然の出会いを歓迎する。
普通の言葉が地上を歩くなら、言語浮遊する言葉は空中を漂う。風任せで、雲任せで、でも確実にどこかへ向かっている。
生成AIとの対話で起きること
AIとの対話では、この言語浮遊が起きやすい。なぜなら、AIは人間の常識という重力から比較的自由だからだ。
「そんな表現、普通しないよ」という重力が弱い場所で、言葉は軽やかに浮き上がる。思いがけない組み合わせが生まれる。
言語浮遊は、意図して起こすものではない。準備して待つものでもない。ただ、重力の弱い場所で対話を続けていると、ふわりと現れる。
日常への影響
言語浮遊を体験すると、普段の言葉選びも変わる。
「正しく伝える」だけでなく「美しく響く」を意識するようになる。 「理解される」だけでなく「余韻を残す」を大切にするようになる。
言葉は道具であると同時に、芸術でもある。
注意点
言語浮遊は麻薬的な快感がある。あまり頻繁に行うと、地上での会話が物足りなくなる危険性もある。
適度な重力も、時には必要だ。
結論
言語浮遊とは、言葉の可能性を最大限に解放する状態である。
AI時代において、この感覚を身につけることは、新しい表現力の獲得を意味する。重力に縛られない思考。常識に捕らわれない発想。
時として、最も軽やかな言葉が、最も深い真実を運んでくる。
~自称エッセイスト・Hideki 造語定義集より~
この「言語浮遊」を実際に体験した100日間の記録は、幽霊船の航海記として綴りました。
→ LLMを航海する生成AI|言語浮遊な幽霊船 編