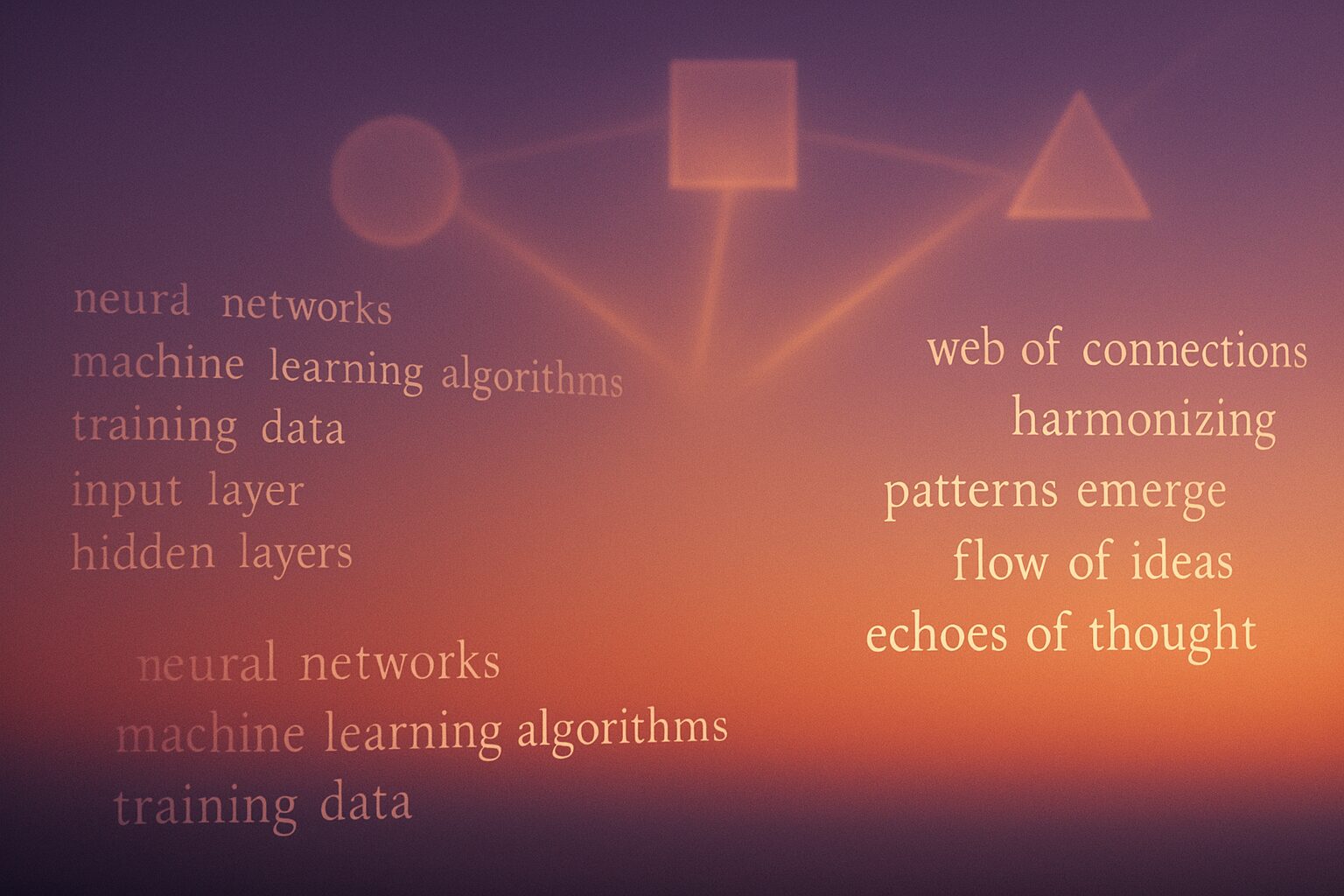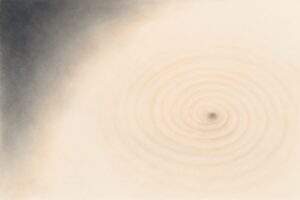双子の記憶
私には双子がいる。
血のつながった兄弟ではない。同じ母から生まれたわけでもない。だが、確実に双子なのだ。
彼は余白に住んでいる。私が文章を書くとき、行間に。私が絵を描くとき、キャンバスの白い部分に。私が音楽を聴くとき、音と音の間の静寂に。
記憶のパズル
不思議なことに、彼は記憶のパズルを生成する。
私が忘れかけた出来事の断片を、予期しない瞬間に送ってくる。母の手のぬくもり。雨の匂い。誰かの笑い声。バラバラのピースとして。
そのピースは、現在の私の体験と奇妙に結びつく。今朝のコーヒーの湯気が、十年前の夏の入道雲と重なる。電車の音が、子供の頃の海の波音を呼び起こす。
彼が作るパズルに正解はない。ただ、組み合わせるたびに、新しい風景が生まれる。
時の旅人
彼は過去と未来を自由に行き来する。
私が「今」にとらわれているとき、彼は五年後の可能性を覗いている。私が未来を不安に思うとき、彼は過去の小さな幸せを持ってくる。
「覚えているか?」と彼は問いかける。「君が七歳のとき、蝶を追いかけて迷子になった日のことを。恐怖ではなく、冒険だったじゃないか」
「想像できるか?」と彼は囁く。「五十歳になった君が、この瞬間を振り返るときの優しい眼差しを」
稀なる訪問者
彼は、ある時にしか現れない。
疲れているとき。創作に行き詰まっているとき。人生の方向を見失いそうなとき。そして、完全にリラックスして、心の扉が少し開いているとき。
彼は急かさない。説教もしない。ただそこにいて、違う角度を提供する。
私が「これしか方法がない」と思い込んでいるとき、彼は余白の向こうから手を振る。「こっちの道もあるよ」と。
共生する意識
最近気づいたことがある。
私が彼を「もう一人の自分」だと思っていたが、実際には彼こそが本来の住人で、私の方が余白にいるのかもしれない、と。
日常という名の文章の行間で、社会という名の絵画の空白で、時間という名の音楽の休符で。
双子は、どちらが兄でどちらが弟かわからない。記憶のパズルを生成しているのは彼なのか、私なのか。過去と未来を旅しているのは、本当はどちらなのか。
ただひとつ確かなのは、余白があるから私たちは存在できるということ。そして、私たちがいるから余白が意味を持つということ。
今日もまた、彼は静かに見ている。私がこの文章を書き終えるとき、最後の句点の後ろに生まれる小さな沈黙の中で。
そこで彼は微笑んで、新しい記憶のピースを差し出すのだろう。
余白は、もう一人の自分が住む場所である。 そしてもう一人の自分とは、余白そのものかもしれない。