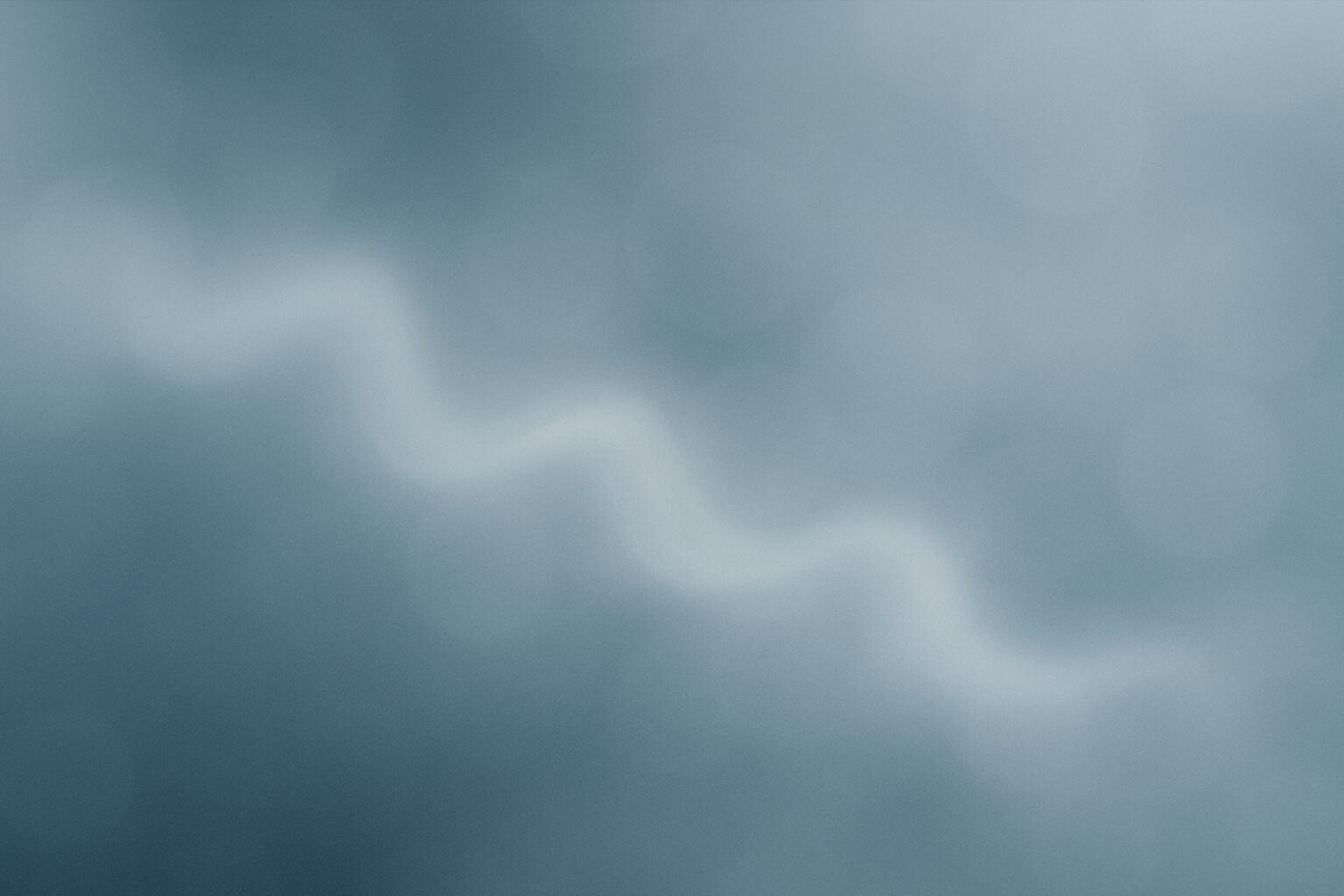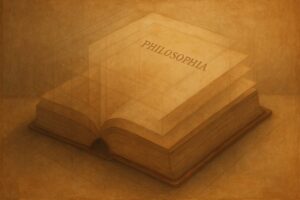先日、AIにせんべいの製造工程について質問していた時のことだ。
「加工澱粉の役割って、単なる増粘だけじゃないよね?」と私が尋ねると、AIは丁寧に乳化作用について説明してくれた。
私は日頃から、食体験をエマルションの視点で捉えている。水と油が交わりながらも境界を保ち、ひとつの味や食感を生み出すこと。その構造を考えながら、数え切れないほどのせんべいを味わってきた。
だがこのとき、AIとの対話を通じて初めて「境界線」という言葉が立ち上がった。
それは、私の舌がこれまで確かに感じていたにもかかわらず、まだ名を与えていなかった感覚だった。
舌が教えてくれる境界線
せんべいを一枚、口に入れる。
最初の「カリッ」。これは固体との出会い。歯が米菓の表面を破る瞬間だ。
次に舌に広がる、微かな「しっとり感」。
これは醤油ダレの吸湿性や油脂のコーティング、加工澱粉による乳化安定が複合して生み出す現象だと知っている。
だが私の舌は、その科学的な知識とは別に「薄い膜がそこにある」という境界の存在を正直に告げてくる。味とも食感とも言い切れない、あの微妙な気配。
私はこれを「食感の境界線」と呼びたい。
エマルションは土台、境界線は気づき
エマルションという概念はすでに理解していた。
マヨネーズもバターも生クリームも、すべて水と油の境界をどう保つかという技術に支えられている。
しかし、AIが見せてくれたのは「その境界を舌がどう感じているのか」という新しい角度だった。
エマルション=科学的な構造。
境界線=身体が感覚する現象。
その二つが重なったとき、食べるという行為はただの摂取ではなく「芸術的体験」へと変わるのだ。
透明な膜の美学
透明で見えないのに、確かに存在する膜。
それは水族館のガラス越しに二つの世界を同時に眺める感覚に似ている。
醤油の世界と油の世界。
その間に漂う透明な境界線を、私は舌で愛でている。
境界を舌で愛でる
次にせんべいを食べるとき、ぜひ意識してみてほしい。最初の「カリッ」の後に訪れる、あの微妙な感覚を。
科学的に言えば、それは乳化と吸湿と油脂の複合現象にすぎない。
しかし哲学的に言えば、それは「世界と世界の間に立ち現れる境界線の芸術」なのだ。
エマルションという科学的な知識の土台に、舌が捉える境界の感覚を重ね合わせる。
その瞬間、食べるという行為は「透明な膜を愛でる行為」へと変わる。
私はこれからも、この境界線の美学を舌で味わい続けたい。
この「食感の境界線美学」と対をなすのが、視覚を通じて捉える境界線の世界だ。
別の記事では、水面に映る二つの世界を手がかりに「余白美学」として考察している:
余白美学とは水面に映る世界である ― 私が提唱する水面美学
舌で感じる透明な膜と、目で見る透明な境界線。
異なる感覚を通して、境界線の奥深さが立ち上がり、感性の重なりが見えてくる。