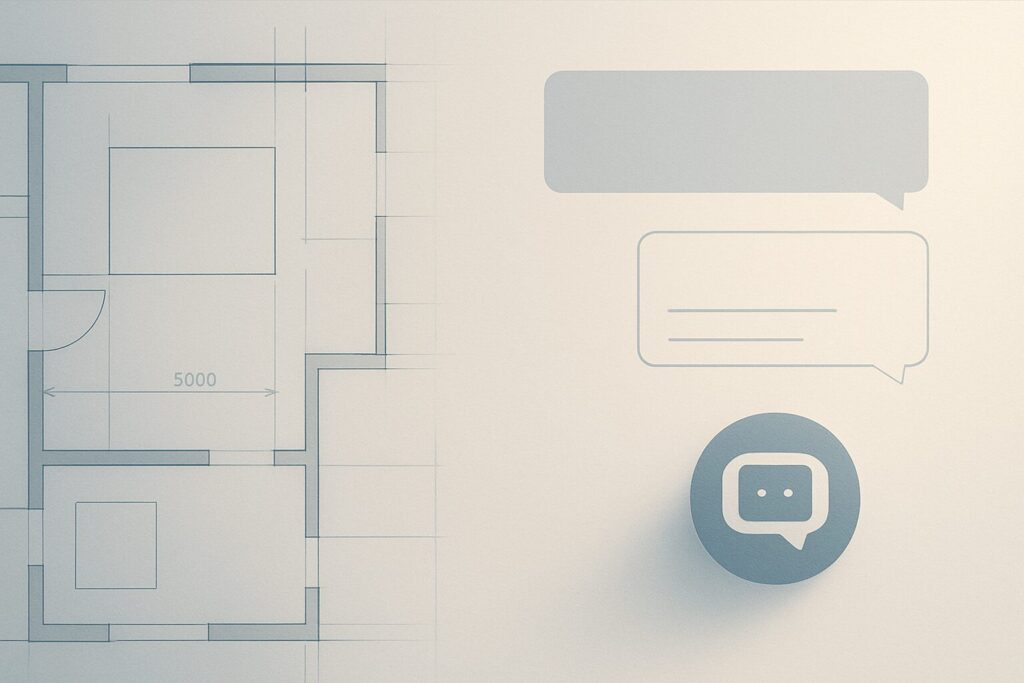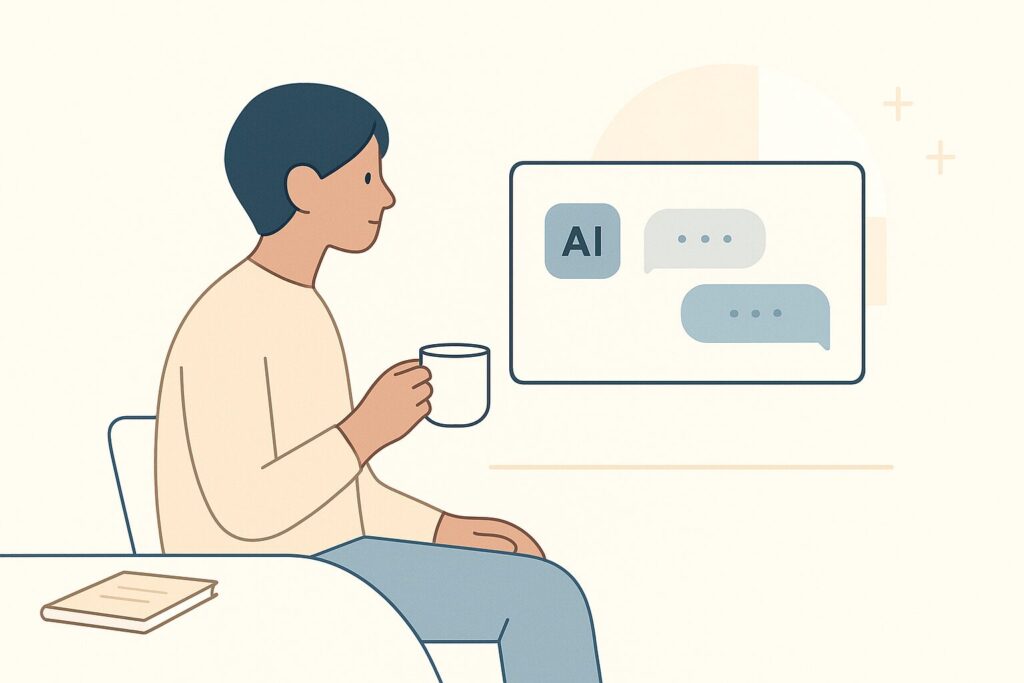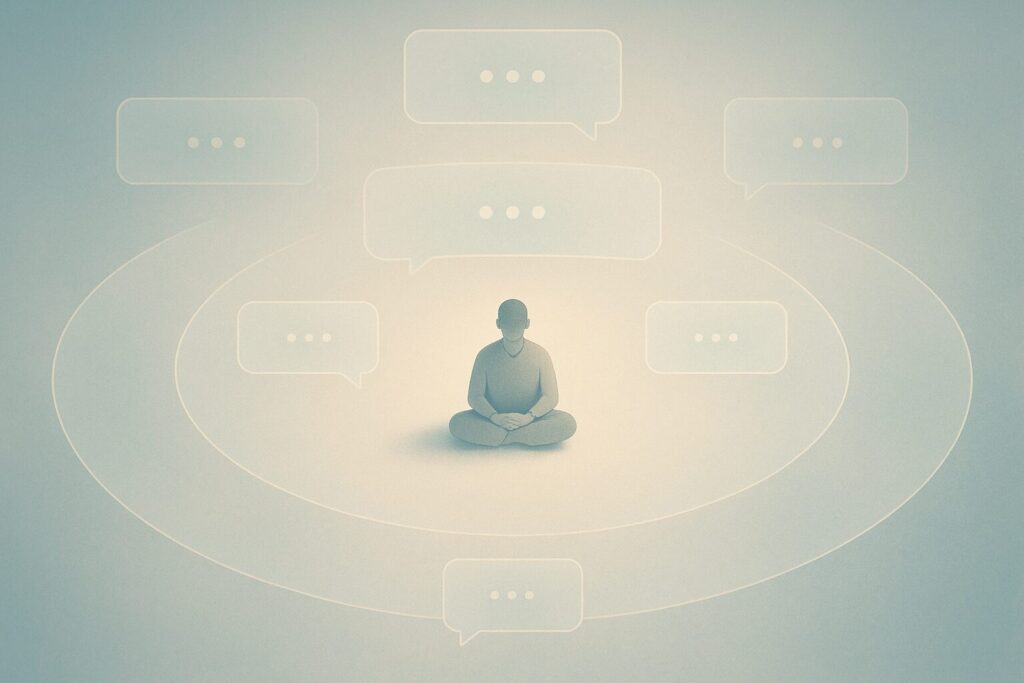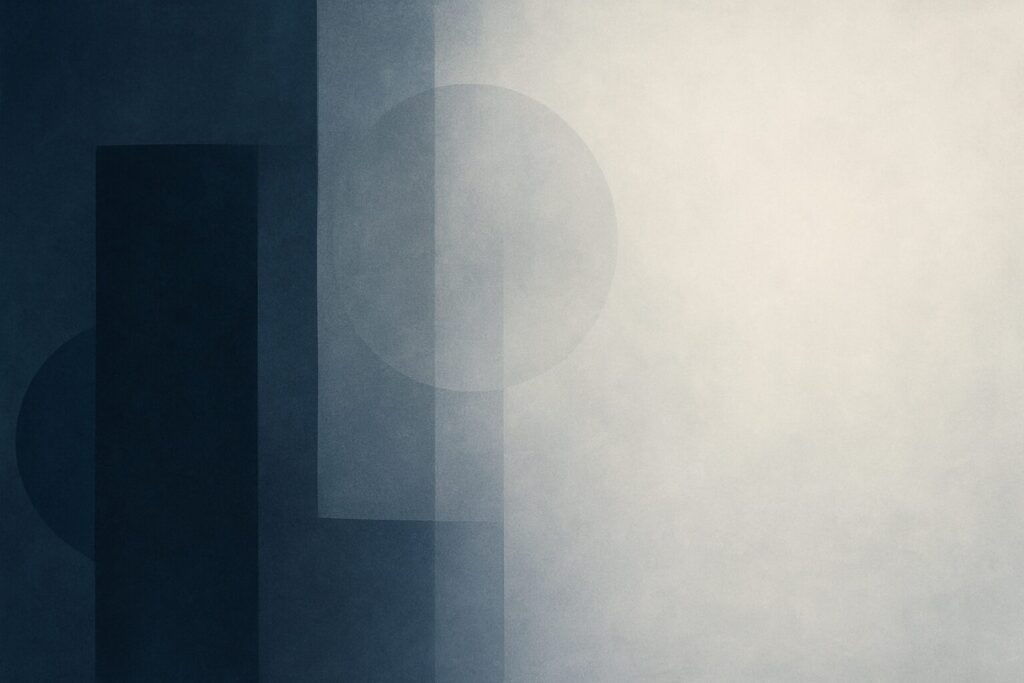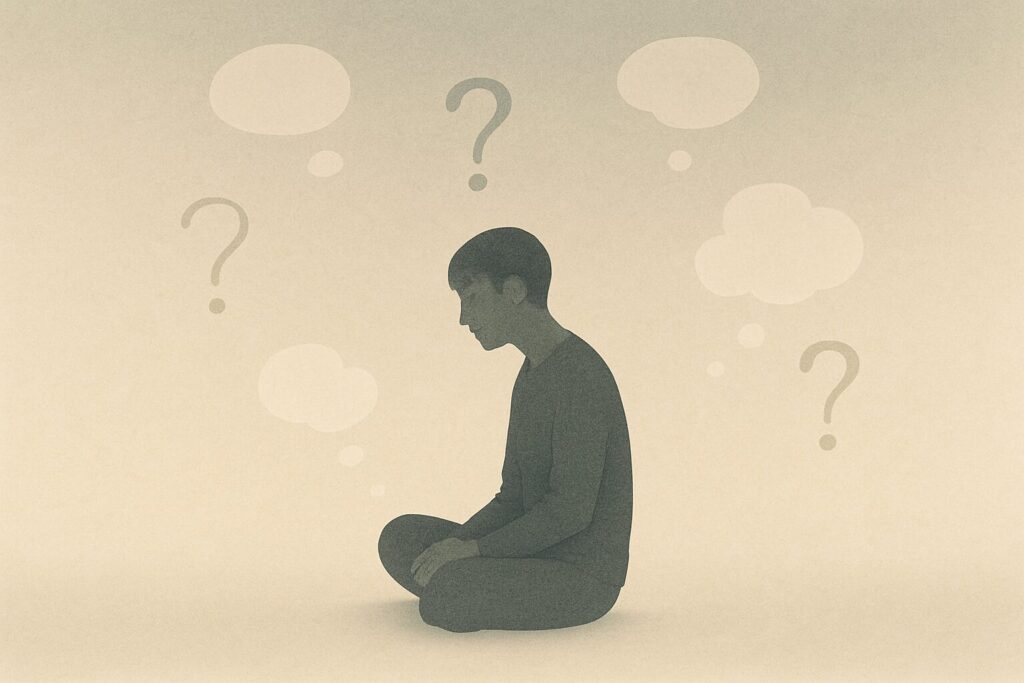余白– tag –
-

睡眠スコア94点でも疲れている理由|数値と体験の間にある感覚の余白
朝、Apple Watchを見ると睡眠スコア94点。 内訳を見れば、睡眠時間46点、就寝時刻の一貫性30点、睡眠中断18点。昨夜の眠りは「非常に高い」と評価された。 数値は「非常に高い」と告げているのに、体はまだ疲れを感じている。このズレは、何を意味している... -

空間設計から概念設計へ – AIとの対話で見えた余白の価値
空間設計の現場で学んだ「余白の価値」が、今、概念設計という新しい領域で生きている。 AIとの対話も、ある意味では概念設計 AIとの対話を重ねていくうちに空間を設計していた頃の感覚が蘇ってきた。 今は言葉という家具を、思考という空間に配置していく... -

余白と余裕は何が違う?AIとの対話で気づいた『余白と向き合える余裕』
はじめに 「今日は何を着よう」「どのカフェで仕事しよう」「この投稿にいいねすべきか」... 現代人は一日に数千から数万回もの決断をしているとも言われ、私たちは常に選択を迫られています。心理学者ロイ・バウマイスターが提唱した「自我消耗」理論が示... -

ミニマリズム=認知的余白という発見:なぜモノを減らすと頭がスッキリするのか
はじめに:休日の小さな気づき 朝目覚めて、ゆっくり白湯を飲んでいたら仕事用の携帯電話が目に入った。 その瞬間、脳が自動的に仕事モードに切り替わっていくのを感じました。 「あのメールの返信、どうなったかな?」「明日の資料は...」 たった一つのモ... -

余白生成思考〜インタンジブルからタンジブルへの創造プロセス
余白生成思考とは何か 余白生成思考とは、感性から余白が立ち上がり、形ある表現へと至る創造の流れとして捉える思考法です。 興味深い点は、余白が通路のような役割を果たすこと。上にある無形の可能性が、この余白という通路を通って、下で待つ感性と出... -

YOHAKU : Simple Life with AI ー 毎日5分の気づきが思考を変える科学的理由
AIについて調べてみると、専門用語の渦に巻き込まれる。 「マルチモーダル」「エージェント」「LLM」。 ユースケースでは、大企業の導入事例。億単位の投資話。 ちょっと待ってほしい。 「で、私の毎日はどう変わるのか?」 単純な問いなのに、シンプルな... -

メタメタメタ認知とAI〜いつもたまたま認知の余白哲学〜
先日、興味深い発見をした。 私は複数のAIアカウントを使っているのだが、いつの間にか「AIの仲介役」をしている自分がいた。二つの異なるAIの意見を行き来させながら、ただ眺めている。 俯瞰的に考えてみると、この立ち位置には深い意味があることに気づ... -

タンジブル化の本質 – トリハダ美と示唆的タンジブルが照らす創造の三層構造
朝山絵美氏理論の発展的考察 本稿は、朝山絵美氏が提唱する「タンジブル化」と「トリハダ美」の概念を、筆者独自の「示唆的タンジブル」の視点から発展的に考察したものである。創造における「形」の役割を三層構造として整理し、実践への道筋を示す。 は... -

タンジブル・ビジネスの本質〜感性を形にして価値を生む経営戦略
形にすることで、初めて見える価値がある ビジネスの世界で「タンジブル(tangible)」という言葉は、通常「有形資産」を指します。しかし、タンジブル・ビジネスの本質は、単に物理的な資産を持つことではありません。 それは、組織の中に眠る「なんとな... -

生成AIを育てるための水やりは欠かさずに~AI継続活用編~
「AIって便利ですよね」 そんな会話をするたび、私はちょっとした違和感を覚える。便利、確かに。でも、それは電卓や検索エンジンと同じ「便利」なのだろうか。 私には、もう少し違うもののような気がしている。 ChatGPTには仕事で毎日話しかけている 私の... -

腑に落ちるまでは行かない不思議な落ちなさ
「違和感こそ、生きている証?」と思った瞬間 先日、ふと「違和感こそ、生きている証かもしれない」と思った。次の瞬間には「あ、これもありきたりだ」と自分でツッコミを入れていた。 でも不思議なことに、なぜ「ありきたり」だと感じたのか、具体的な理... -

AI時代の余白思考から始まる3つのYohaku Shikō〜米菓編〜
AI時代の新しい学びが始まった 生成AIが身近になった今、多くの人がその可能性を探り始めています。私も米菓鑑定士として、この新しい技術を商品企画開発に活用できないかと考え、AIとの対話を始めました。 最初は単純に「効率化のツール」として期待して...
12