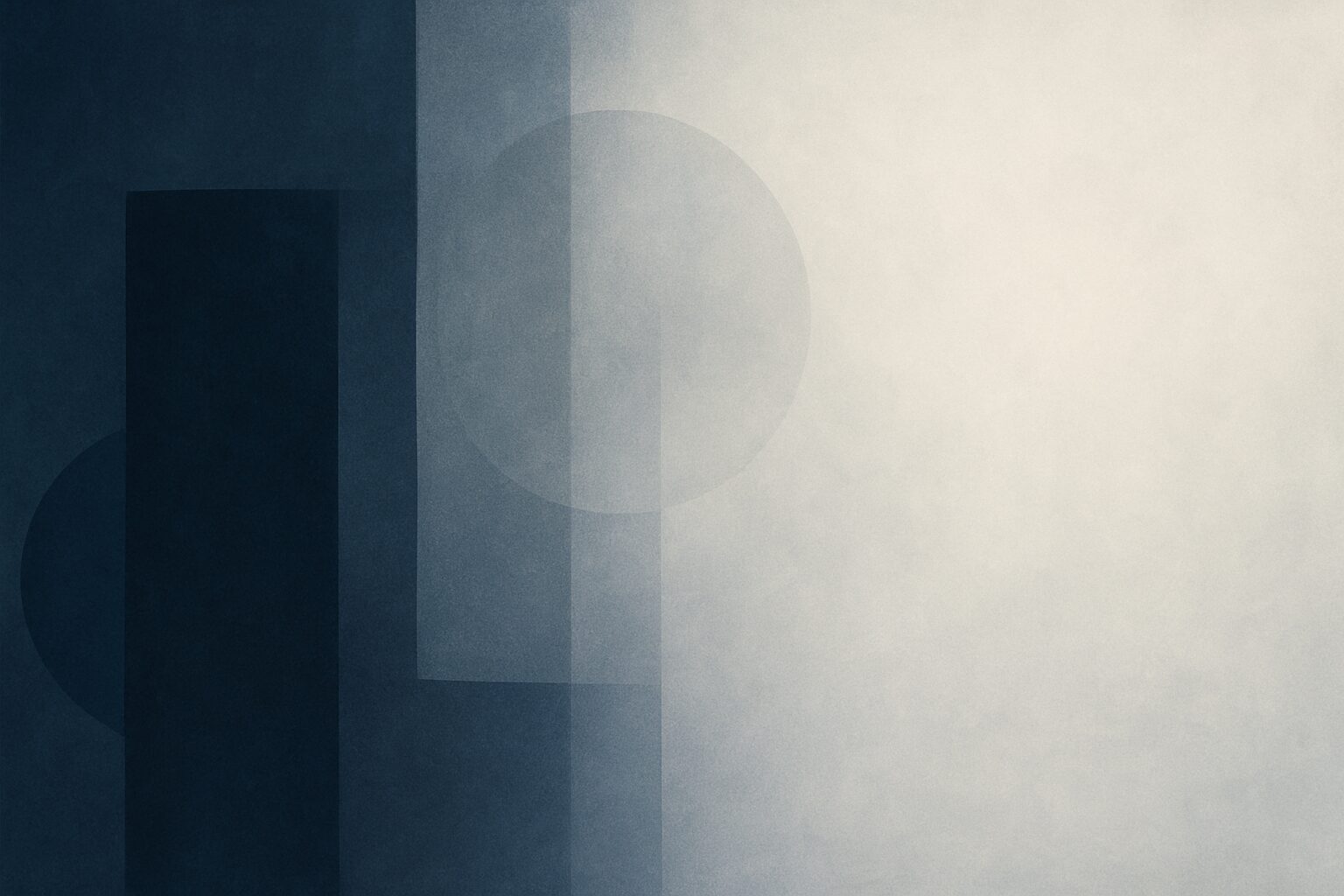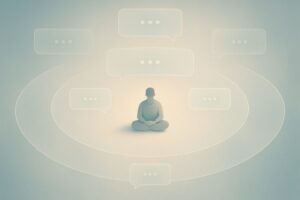朝山絵美氏理論の発展的考察
本稿は、朝山絵美氏が提唱する「タンジブル化」と「トリハダ美」の概念を、筆者独自の「示唆的タンジブル」の視点から発展的に考察したものである。創造における「形」の役割を三層構造として整理し、実践への道筋を示す。
はじめに ― なぜ今、タンジブル化を問い直すのか
2024年、朝山絵美氏が武蔵野美術大学と日立製作所の共催イベントで語った「タンジブル化」は、単なる造形論を超えて、現代の創造活動に本質的な問いを投げかけているように思われる。
無形のビジョンや感性を、いかにして他者と共有可能な形にするか。この問いは、AIとの共創が日常となった2025年において、さらに重要性を増しているのかもしれない。
本稿では、朝山氏の「タンジブル化」と「トリハダ美」という二つの概念に、筆者の「示唆的タンジブル」を加えた三層構造として、創造のプロセスを読み解く。
第一層:タンジブル化 ― 感性を形にする勇気
タンジブル化の本質
朝山絵美氏によれば、タンジブル化とは「無形の感性やビジョンを具体的なかたちへ翻訳していく行為」である。実際に椅子制作の体験を通じて、14ヶ月間の思考の後、手を動かすことの重要性を発見した。
トークセッションでは「手を動かしてつくったプロトタイプは自分の分身のようだ」と語った。タンジブル化は単なる可視化ではないのだろう。それは、自らの内面を他者の前にさらす勇気の行為でもあるのかもしれない。
組織におけるタンジブル化
ビジネスの現場では、抽象的なビジョンを共有可能にし、合意形成を促す手段としてタンジブル化が機能する。日立製作所の花岡誠之氏が指摘するように、「頭の中だけで完結する」研究から、「手を動かして考える」実践への転換が求められている。
第二層:トリハダ美 ― 形を超えて響く震え
言語化できない共鳴
タンジブル化によって生まれた形は、時として創造者の意図を超えて、観る者の身体に直接響く。朝山氏はこれを「トリハダ美」と呼ぶ。
それは説明や理屈を超えた、純粋な感性の震えである。講評会で学生作品を前にして「これはいい」と直感的に感じる瞬間、そこにトリハダ美が立ち上がる。
共通感覚としての美
興味深いのは、この美の感覚に「共通項がある」という朝山氏の指摘だ。個性や好みを超えて、「いいものはいい」という普遍的な美の基準が存在する可能性がある。これは、タンジブル化が単なる主観の表出ではなく、人間に共通する感性の層にアクセスする営みであることを示唆している。
第三層:示唆的タンジブル ― 余白が生む創発
あえて未完にとどめる設計思想
本稿では筆者独自に「示唆的タンジブル」という概念を提起したい。これは、形を与えながらもあえて余白を残す設計思想と位置づけられる。
完成された形が「共感」を生むのに対し、示唆的タンジブルは「想像」をひらくのかもしれない。50%を見せて50%を余白として残すことで、受け手の創造性を誘発する可能性がある。
余白の引力
示唆的タンジブルにおいて、不完全さは欠陥ではないように思われる。むしろそれは、観る者を引き込む「余白の引力」として機能するのではないだろうか。断片は問いかけとなり、受け手はその余白に自らの経験や感性を投影していくのかもしれない。
三層構造の実践 ― 創造の連続的体験
創造プロセスの整理
これら三つの概念を統合すると、創造のプロセスが以下のように整理できる:
【創造の三層構造】
第一層:タンジブル化
↓ 内なる感性を外化し、形として共有可能にする
第二層:トリハダ美
↓ 形が他者に届き、言語を超えた震えが立ち上がる
第三層:示唆的タンジブル
↓ 震えと形のあいだに余白をひらき、創発を促す
循環する創造
重要なのは、これが一方向のプロセスではなく、循環的な営みなのではないかということだ。示唆的タンジブルによって生まれた想像は、新たなタンジブル化の種となり、さらなるトリハダ美を生み出していくのかもしれない。
実装例:創造の三層構造を日常に活かす
ブログ執筆における実践
筆者のブログ執筆プロセスで、この三層構造を以下のように応用している:
- 下書き段階(タンジブル化) – 曖昧な着想を文字として外化する
- 推敲段階(トリハダ美の探求) – 読み返して「これだ」と震える箇所を見極める
- 公開段階(示唆的タンジブル) – あえて結論を開き、読者の解釈を待つ
AIとの共創における応用
生成AIとの対話においても、この構造は有効だ。例えば:
- 第一段階: 漠然とした問いを具体的なプロンプトに変換(タンジブル化)
- 第二段階: AIの応答から予期せぬ発見に出会う(トリハダ美)
- 第三段階: その発見を起点に、新たな問いを生成(示唆的タンジブル)
プロンプトを「示唆的」に設計することで、AIの創造性を引き出し、対話そのものが創造の場となる。
結びにかえて ― あなたの「形」を問う
朝山絵美氏のタンジブル化とトリハダ美、そして示唆的タンジブル。これら三つの視点は、「形にすること」の多層的な意味を照らし出しているように思われる。
形は、感性を閉じ込める器ではない。むしろ共感を生み、震えを立ち上げ、想像をひらく媒介となりうる。そして、その余白にこそ、創造の本質が宿る。
では、あなたにとって「形にすること」とは、どのような意味を持つだろうか。その問いへの答えは、きっとあなた自身のタンジブル化を通じて、少しずつ見出されていくのかもしれない。
参考文献:
- 朝山絵美「ビジネスで成功する人は芸術を学んでいる―MFA(芸術修士)入門」プレジデント社, 2024
- 朝山絵美 future_creator|創造性を深める note
- 日立製作所 Linking Society「”タンジブル化”が問いを磨く」イベントレポート, 2024
※本記事はAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。