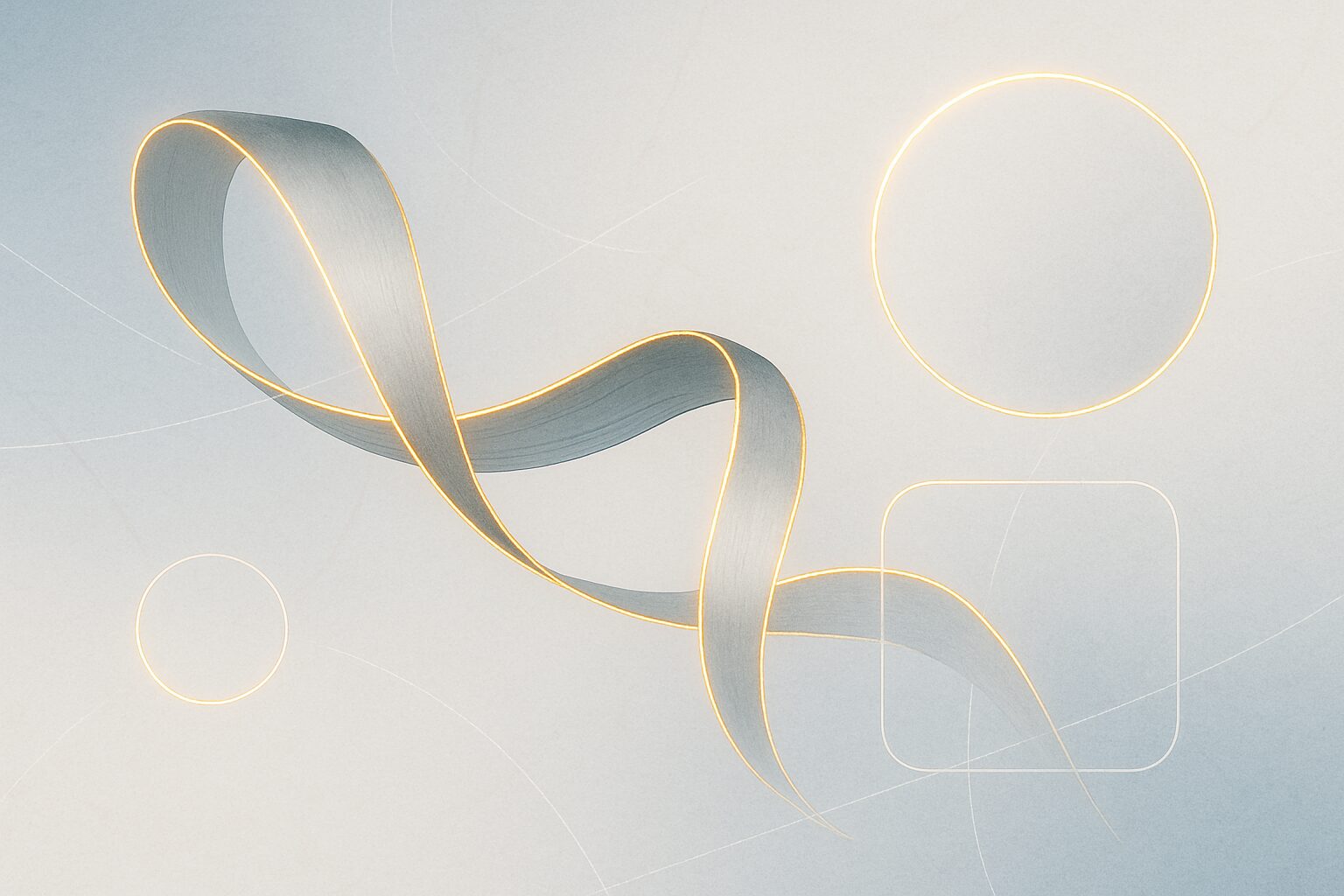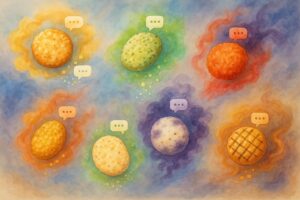1. 触れることへの問い
私たちが何かに「触れる」とき、そこで何が起きているのだろうか。メルロ=ポンティは、触れる手は同時に触れられる手でもあるという、触覚の可逆性を指摘した。この単純な事実の中に、人間と世界との根源的な関係が隠されている。
1997年、MITの石井裕教授は「タンジブル・ビッツ」という革新的な概念を提唱し、デジタル情報に物理的実体を与えることで、情報と人間の新しい関係を切り開いた。2024年、朝山絵美氏(https://emiasayama.com/)は独創的な手法で、抽象的なビジョンを造形物として具現化し、「トリハダ美」による共感という、これまでにない回路を発見した。
これらの偉大な探求は、いずれも「触れられないもの」を「触れられるもの」へと変換する道を示してきた。そして今、これらの豊かな成果を受けて、もう一つの可能性を探求したい。触れられるものと触れられないものが共存する、新たな道筋について。
2. 三つのタンジブルの現象学
タンジブル化という豊かな現象には、それぞれに固有の美しさを持つ異なる現れ方がある。
触覚的タンジブル(石井裕)は、デジタルのビットを物理的なアトムへと見事に変換する。この先駆的なアプローチにより、手が直接情報に触れ、世界との接触が新たな形で実現される。触れることで生まれる確信、身体が獲得する確かな理解。これは情報時代における画期的な達成である。
美的タンジブル(朝山絵美)は、ビジョンを造形へと美しく結晶化させる。椅子を作る手の動き、造形物を前にした身体の震え。朝山氏が発見した「トリハダ美」による共感は、理性を超えた深い理解の可能性を私たちに教えてくれた。
これらの素晴らしい成果と並んで、示唆的タンジブルという第三の可能性を提案したい。対象の一部を具体化しながら、一部を意図的に不可視のまま保持することで、見えるものと見えないものの対話が生まれる。これは先行する二つのアプローチを否定するものではなく、新たな選択肢を加えるものである。
3. 可視と不可視の絡み合い
メルロ=ポンティは『見えるものと見えないもの』において、可視的なものと不可視的なものが豊かな関係を織りなすことを示した。見えるものは見えないものを背景として輝き、見えないものは見えるものを通して静かに語りかける。
石井教授と朝山氏の100%のタンジブル化への挑戦は、人間の創造性の極致を示している。同時に、示唆的タンジブルは別の創造性を探求する。50%を可視化し、50%を不可視のまま残すことで、見えるものと見えないものが響き合う空間を作り出す。
この選択は、完全性への到達とは異なる豊かさを持つ。それぞれのアプローチが、それぞれの場面で、独自の価値を生み出すのである。
4. 示唆的タンジブルの哲学
示唆的タンジブルは、対象の本質的な部分を具体的に示しながら、全体像については受け手の身体的想像力に委ねる設計思想である。これは朝山氏の「手で考える」という発見を受け継ぎながら、「想像で参加する」という次元を加える試みである。
メルロ=ポンティの「キアスム(交差配列)」の概念がここで生きてくる。見るものと見られるもの、触れるものと触れられるもの、示すものと示されるものが美しく交差する。示唆とは、この交差を丁寧に設計することである。
石井教授が切り開いた触覚の可能性、朝山氏が発見した美的共感の回路。これらの貴重な成果の上に、示唆的タンジブルは想像力による参加という新しい層を重ねようとする。
5. 50/50という配分の意味
50/50という配分には、特別な意味がある。それは確定と未確定、現前と不在の間の創造的な均衡を表している。
メルロ=ポンティが示した両義性の豊かさがここにある。石井教授の100%の物理化が持つ力強さ、朝山氏の100%の造形化が生む感動。これらと並んで、50%という配分は、また異なる種類の体験を可能にする。
半分を見せ、半分を想像に委ねることで、受け手は創造的な参加者となる。これは受動性でも能動性でもない、新しい関わり方の提案である。
6. 身体と想像の交響
示唆的タンジブルにおいて、身体と想像力は美しく協働する。朝山氏が示した身体性の重要性を受け継ぎながら、想像力という要素を加える。
見える部分に触れた身体は、見えない部分を自然に補完しようとする。これは創造的な完成への参加であり、メルロ=ポンティが「肉(chair)」と呼んだ、世界と身体の原初的な結びつきの現れである。
石井教授の触覚的確信、朝山氏のトリハダ美。これらの身体的な理解の形に、示唆的タンジブルは想像による理解という可能性を加える。
7. 間身体性と共創
示唆的タンジブルは、他者との間で独特の意味を持つ。メルロ=ポンティの「間身体性」が示すように、私たちは他者と共に意味を生成する。
石井教授のアプローチが生む明確な共有、朝山氏のアプローチが生む感動の共有。これらの価値ある達成と並んで、示唆的タンジブルは差異を含んだ共創という可能性を探る。
それぞれの身体、それぞれの経験、それぞれの想像力によって異なる完成を見ることで、多声的な創造が生まれる。
8. 実践への展開
三つのタンジブル化は、それぞれの場面で輝く。
石井教授のアプローチは、明確さと確実性が求められる場面で力を発揮する。朝山氏のアプローチは、感動と共感を生み出したい場面で素晴らしい効果を生む。そして示唆的タンジブルは、探索と発見のプロセスを大切にしたい場面で価値を持つだろう。
AIとの対話においても、これら三つのアプローチはそれぞれの役割を果たす。時に明確な答えを、時に感動的な共感を、時に探索的な対話を。
9. 結論:豊かな選択肢とともに
石井裕教授の触覚的タンジブル、朝山絵美氏の美的タンジブル、そして示唆的タンジブル。これら三つのアプローチは、タンジブル化という豊かな可能性の異なる側面を照らし出している。
それぞれのアプローチには固有の美しさと価値がある。重要なのは、これらの選択肢を持ち、状況に応じて最適な道を選べることである。
メルロ=ポンティが示した世界の豊かさを、私たちはそれぞれの方法で体験できる。石井教授と朝山氏が切り開いた道に深い敬意を表しながら、示唆的タンジブルという新しい小径を、そっと付け加えたい。
見えるものと見えないものが織りなす創造的な緊張——それは対立ではなく、何かを生み出そうとする張力——の中で、私たちはさらに豊かな触れ方を学んでいけるだろう。
参考文献
メルロ=ポンティ, M. (2017). 『見えるものと見えないもの――付・研究ノート【新装版】』(滝浦静雄・木田元訳)みすず書房
朝山絵美 (2024). 『ビジネスで成功する人は芸術を学んでいる——MFA(芸術修士)入門』プレジデント社
石井裕 (2014). 「タンジブル・ビッツからラディカル・アトムズへ」アカデミーヒルズ講演録(オンライン資料)
本稿は、石井裕教授と朝山絵美氏の先駆的な仕事への深い敬意から生まれました。お二人が示してくださった道筋があったからこそ、この新たな可能性を考えることができました。心より感謝申し上げます。