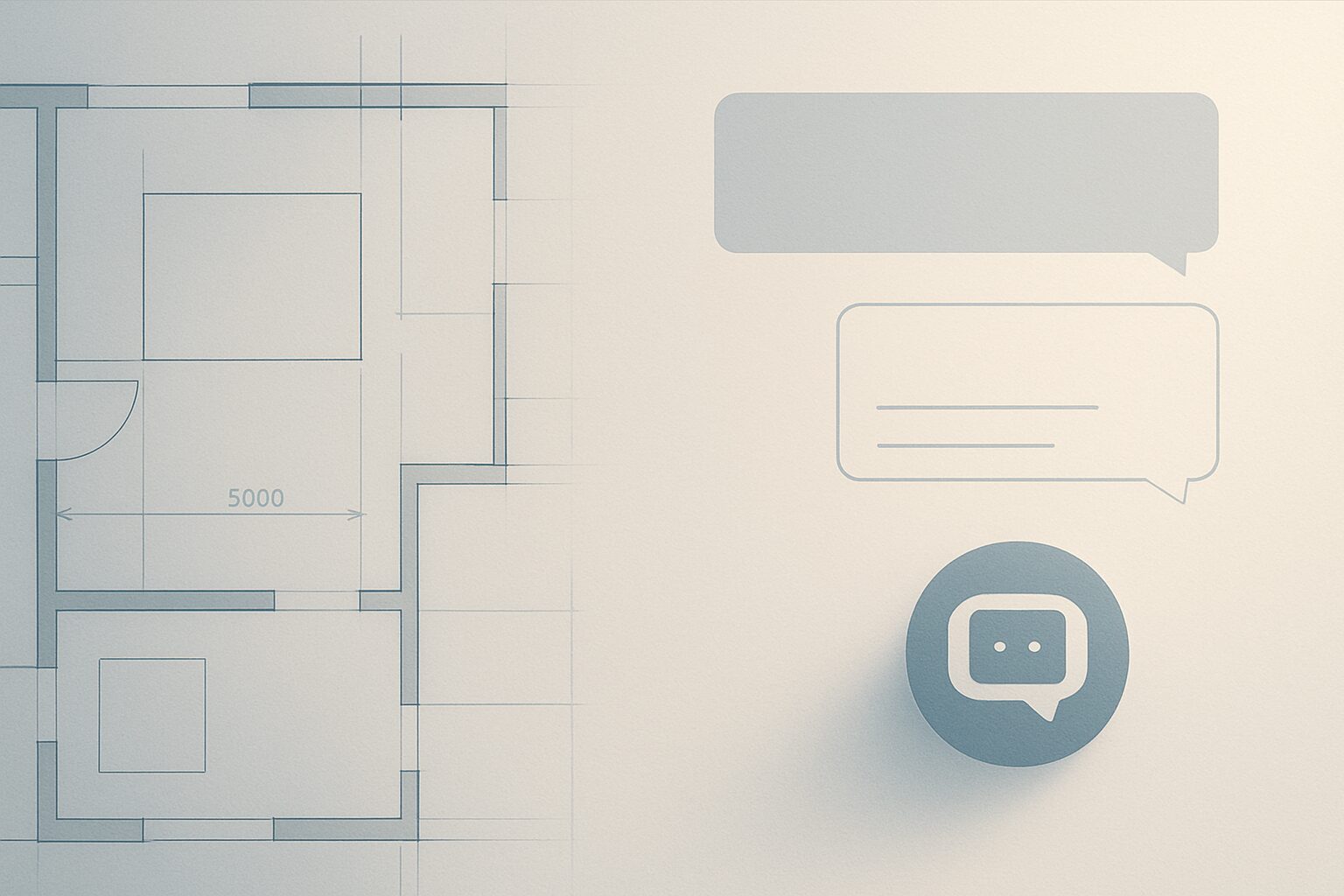空間設計の現場で学んだ「余白の価値」が、今、概念設計という新しい領域で生きている。
目次
AIとの対話も、ある意味では概念設計
AIとの対話を重ねていくうちに空間を設計していた頃の感覚が蘇ってきた。
今は言葉という家具を、思考という空間に配置していく作業のようである。
使い勝手と開放感のバランスを考えながら、読み手にとって心地よい導線を作る。
完璧に埋め尽くすのではなく、適度な余白を残す。その余白が、想像力の息づく場所になればいいと。
空間にも概念にも共通する「余白の法則」
空間設計では、家具の配置だけでなく「何も置かない場所」を意図的に作った。その空白が、住む人の創造性を引き出し、時間と共に新しい使い方を生み出していく。
概念設計も似ている。アイデアを詰め込みすぎず、受け手が自分なりの解釈を加えられる余地を残す。その余白こそが、概念が生きて成長していく土壌となる。
大切なのは「何を置かないか」
物理的な空間も、思考の空間も、概念の空間も、結局は同じことなのかもしれない。大切なのは何を置くかではなく、何を置かないか。
空間を設計していた頃の記憶を辿りながら、AIとの概念設計という新たな実践を通して、改めてそう思った。設計の本質は変わらない。ただ、扱う素材が空間から概念へと移り変わっただけなのかもしれない。
※本記事は筆者の空間設計実務経験とAI対話実践を基に構成しています。