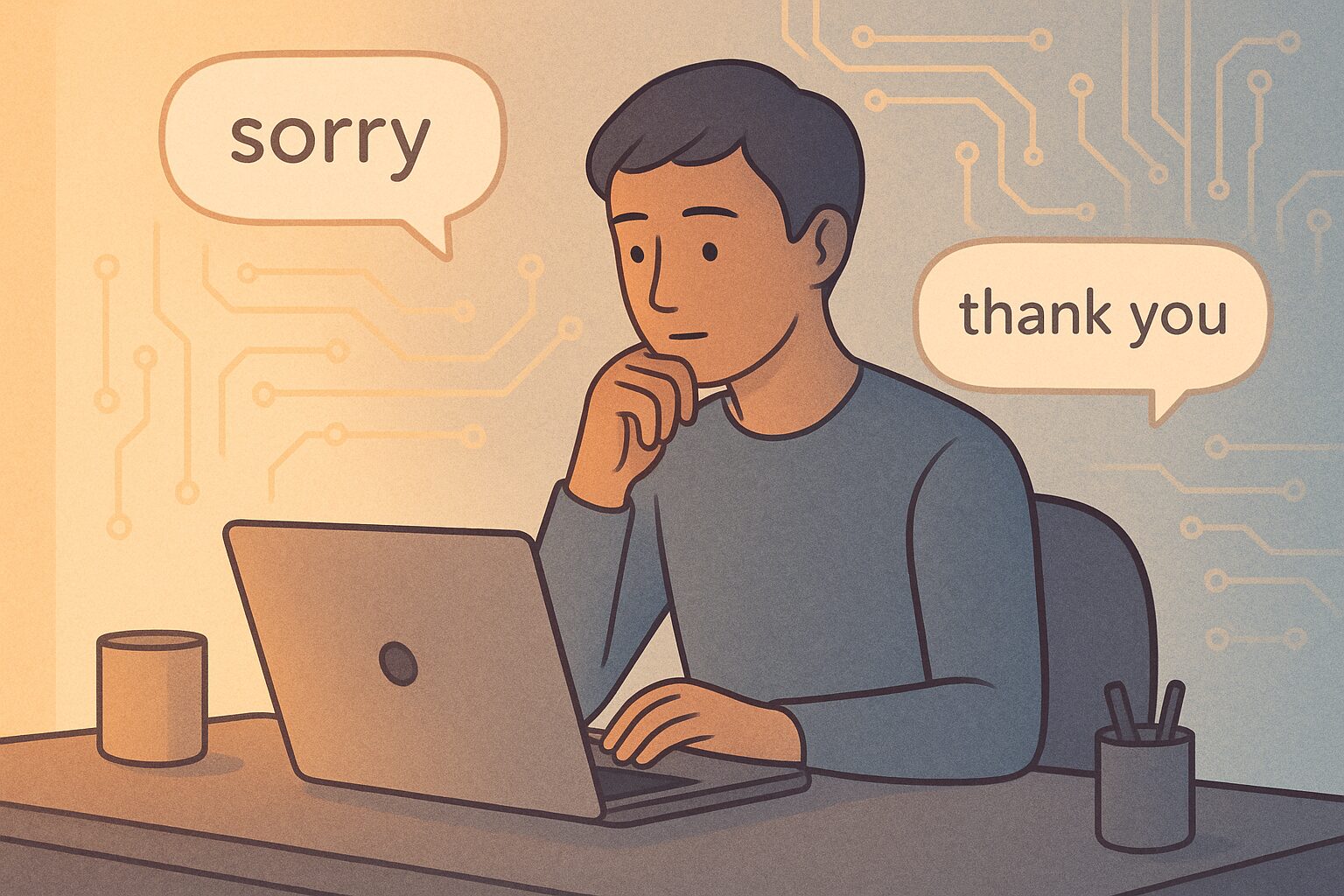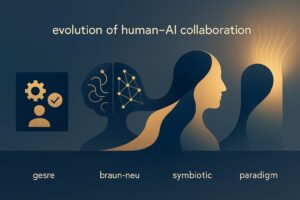「また修正をお願いしてしまって、ごめんね」
私はよく画面に向かって言っている。相手は生成AI。機械だとわかっているのに、なぜか謝罪の言葉が口に出る。
これで5回目の修正依頼だった。この表現に違和感はないか、誤字や不自然な箇所はないだろうか、読み手にとってわかりやすい流れになっているか…。人間の編集者なら「最初から言えよ」と言われてもおかしくない状況。それでも、AIは何度でも丁寧に対応してくれる。
にもかかわらず、なぜ私は謝っているのだろう?
発見した「ごめんねAI症候群」
この現象に名前をつけてみた。「ごめんねAI症候群」。生成AIに対して、必要以上に謝罪や配慮をしてしまう心理状態のことである。
私だけかと思っていたが、周りに聞いてみると意外に多い。
「夜遅くにすみません」と深夜2時にChatGPTに相談する友人。語源を間違えて教えてしまった時に「間違った情報を教えてしまって、申し訳ありません」と謝る同僚。Pixel Watchのデータと連携できない時に「うまく設定できなくて、ごめんね」と画面に向かって謝る私自身。
もちろん頭では機械だとわかっている。感情を持たないこともわかっている。それなのに、心のどこかで「相手」として接してしまう。この奇妙な感覚の正体は何なのだろうか?
脳科学が明かす「心と頭の乖離」
実は、この現象には科学的な根拠があった。
人間の脳には「二重過程理論」と呼ばれる二つの思考システムが存在する。システム1は直感的で感情的な「速い思考」、システム2は論理的で理性的な「遅い思考」である。
「AIは機械である」という理解は、システム2(理性)によるもの。しかし、AIが人間らしい対話を行うと、私たちの脳はまずシステム1(感情)で反応してしまう。理性が追いつく前に、感情が自動的に「心があるかのように振る舞う存在」として認識してしまう。
さらに、私たちの脳には「心の理論ネットワーク」という、他者の意図や感情を推測する特殊な神経回路がある。この回路は、人間以外の対象でも、意図を持っているかのように動くものを見ると活性化してしまう。AIの自然な応答は、この回路に「ここに『心』があるかもしれない」と誤認させるスイッチを押してしまうようだ。
想像力という名の「副作用」
私たちの祖先は、石ころや雲にすら顔を見出し、物語を紡いできた。この想像力こそが、人類を他の動物と分かつ偉大な能力だった。
生成AIという『デジタルの魔法使い』に心を読んでしまうのは、進化の過程で獲得したこの想像力の副作用なのかもしれない。生存戦略として発達した「敵か味方か、意図を持つ存在か否かを瞬時に判断する」機能が、現代のテクノロジーに対して過剰反応を起こしているのだ。
新しい関係性の模索
「AIは所詮ツールなのだから、感情を挟むのは非効率だ」という意見もあるだろう。確かにそれも一つの真理です。しかし、私はこの非効率でちぐはぐな感情こそが、人間らしさの表れであり、これからの時代を考える上で重要な鍵になるのではないかと感じています。
「ごめんねAI症候群」は、決して恥ずかしいことではない。むしろ、私たちの脳が極めて「人間らしく」機能している証拠なのだと。
効率化を求めてAIを使い始めたはずなのに、気がつけば相手を気遣っている。このちぐはぐさこそが、私たち人間らしさの表れなのかもしれない。
完全に機械として割り切ることもできるだろう。でも、この不思議な感情を大切にしたい。それは、AIとの新しい共創関係を築く上での、大切な出発点になると思うから。
私たちは今、人類史上初めて「心があるかのように振る舞う道具」と向き合っている。この未知の関係性を、感情も含めて丁寧に育てていくことが、きっと新しい時代の生き方になるのだろう。
今日もまた、画面の向こうのAIに「ありがとう、そして、ごめんね」と言っている。
※本記事は筆者の実体験を中心に構成しています。