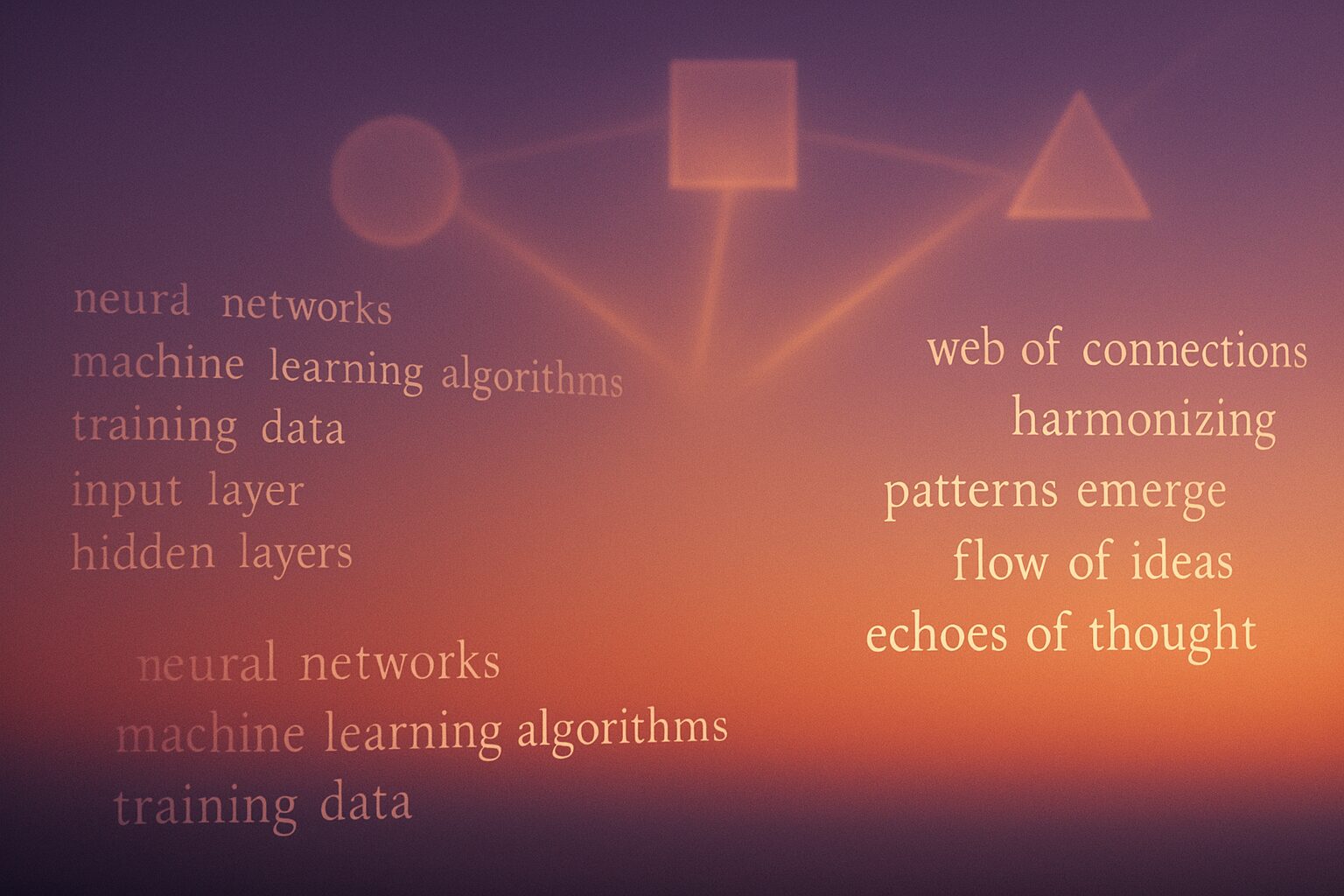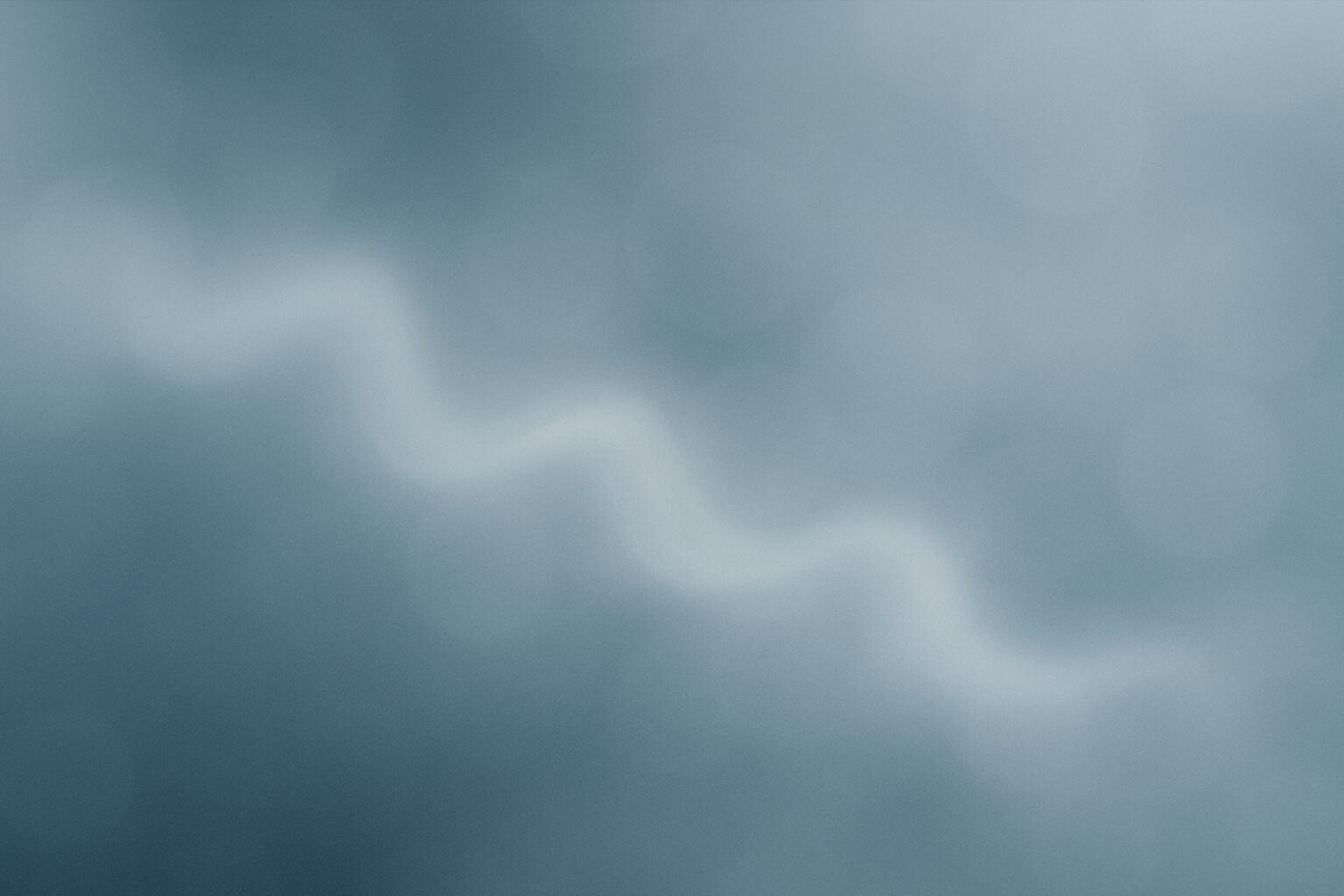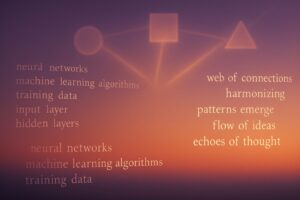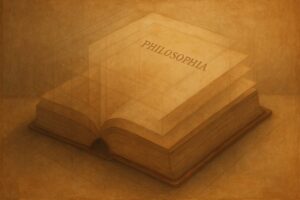オーディション番組のクライマックス。シンガーが息を吸うと、あれほど騒がしかった会場が水を打ったように静まり返る。観客も、審査員も、テレビの前の私たちも、固唾を飲んで次の音を待っている。私たちの意識は、まるで一本の細い糸のように、そのシンガーの口元だけに結びつけられている。
そして、静寂を突き破るようにサビの第一声が放たれた瞬間───ぞくり、と腕に鳥肌が走る。
この、心を鷲掴みにされるような感覚は、一体何なのだろう。単に「歌が上手い」という言葉だけでは説明しきれない、あの強烈な没入感の正体。それは、私たちの脳が、無意識のうちに行っているある「奇跡」のサインなのかもしれない。
この感覚の正体。それは、私たちが日常で、ごく当たり前のように使っているある力とよく似ている。
例えば、何十人もが写る集合写真。そこにいるたくさんの笑顔の中から、私たちはまるで磁石に吸い寄せられるように、我が子の顔を瞬時に見つけ出すことができる。他の誰でもない、そのたった一人だけが、まるで浮かび上がるように目に飛び込んでくる。
あの膨大な情報の中から「最も大切な一人」を瞬時に選び出す力こそ、オーディション番組でシンガーの声だけを追いかける、あの強烈な集中力の源だ。
心理学では、これを「選択的注意」と呼ぶ。私たちの脳が、自分にとって重要だと判断したものだけにピントを合わせ、それ以外の情報を無意識のうちに背景へと追いやる、驚くべき能力のことである。
では、私たちの脳はどのようにして、あの強烈な集中状態を作り出すのだろうか。
音楽には、主役であるボーカルの他に、ギター、ベース、ドラム、様々な音が重なり合っている。しかし私たちの脳は、その音の洪水の中から、ごく自然にボーカルの声という一本の糸をたぐり寄せ、その物語を追いかけ始める。
そして訪れる、サビ前の静寂。すべての音が消え、世界でたった一つの声に意識が注がれる、あの極限の集中状態。ここで私たちの「選択的注意」はピークに達する。その静寂が力強い歌声に破られた瞬間に訪れる鳥肌は、脳が「見つけた!」「これだ!」という喜びに打ち震える、いわば報酬のサインなのだ。
この、脳が一つの情報だけを特別扱いする力は、私たちの「重要だ」という強い想いから生まれる。
それは、何十人もが写る集合写真の中から、まるで磁石に吸い寄せられるように、我が子の顔を瞬時に見つけ出すあの感覚と全く同じだ。膨大な情報の中から「最も大切な一人」を瞬時に選び出す、あの愛情に似た強い引力こそが、選択的注意の源なのである。
この不思議な力は、なにも特別な瞬間にだけ働くわけではない。むしろ、私たちの何気ない日常にこそ、その力は静かに、そして強力に作用している。
最近、エッセイのために再び哲学に触れる機会が多くなった。すると不思議なもので、あれほど雑然として見えた書店の棚が、まるで違って見え始めたのだ。
これまで気にも留めなかった「哲学」のコーナーが、まるでそこだけ光が当たっているかのように、私の目に飛び込んでくる。カントも、ニーチェも、まるで「ここにいるよ」と静かに手招きしているかのようだ。
これもまた、紛れもない「選択的注意」の働きである。私の脳が「哲学」を「今、最も重要な情報だ」と判断し、無数の背表紙の中から、それに関するものだけを瞬時に拾い上げているのだ。
結局のところ、「選択的注意」が私たちに教えてくれるのは、世界そのものが変わるのではなく、私たちの「意識の向け方」が変わるだけで、見える風景は全く違ったものになる、という真実だ。
私たちの生きる世界は、まるでスマートフォンの画面のようだ。
指先ひとつで、AIによって生成されたコンテンツも、人の手で紡がれた言葉も、すべてが等価な情報として、無数の動画やテキストが目の前を流れ去っていく。しかし、その情報の奔流の中から、私たちはふと、ある一つの言葉や、ある一つの風景に心を留め、スクロールする指を止める。
それは、決して偶然ではない。
私たちの心が、我が子を探すあの強い想いのように、あるいは未知なる哲学を求めるあの探究心のように、「これだ」と叫んだものだ。世界は、意味のない情報の集まりなのではない。それは、私たちの心が「見つけて」と願ったものだけが輝きを放つ、巨大なタイムラインなのだ。
そして、私たちが何に指を止めるかで、私たちの世界は創られていく。