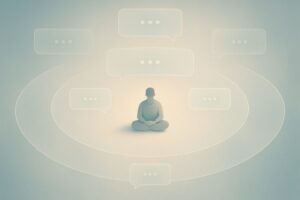煎餅をひとくちかじる。その瞬間に響く「パリッ」という音は、ただの食感ではない。
音は耳を通じて身体に刻まれ、どこか遠い記憶を呼び起こす。縁側に射しこむ午後の陽ざし、祭りの夜に漂う醤油の香り、冬の炬燵に散らばった小さなあられ――。
ここで立ち上がるのは「具体」と「想像」の交差である。
本稿で扱う「示唆的タンジブル」という概念は、その交差を照らし出そうとする筆者の造語だ。これは、対象の核心を身体で確かに捉えつつも、その全体像は受け手の想像力に委ねるという設計思想である。
哲学者メルロ=ポンティは、世界と身体が交差する原初の感覚を「肉(chair)」と呼んだ。触れる/触れられる、見る/見られる――。その相互浸透を彼は「交差配列(キアスム)」と表現した。
米菓はまさに、日常の中に小さなキアスムを差し込む装置なのかもしれない。
煎餅を割るときに響く音、口に広がる香り、舌に残る余韻。
どの感覚に心が引き寄せられるかは、人によって異なる。ある人は音に、ある人は香りに、また別の人は懐かしい記憶に。
この「揺らぎ」こそが示唆的であり、それぞれの世界を開いていく。
だからこそ、煎餅を噛むことは小さな哲学的実践である。
具体と想像の比率を確かめながら、私たちは世界と自分との接点を静かにかみしめている。
ひと口ごとに――世界をもう一度、口の中で確かめているのだ。
補記
本稿で扱った「示唆的タンジブル」については、別の記事により詳しくまとめてあります。
→ 示唆的タンジブル ― 見えるものと見えないものの創造的緊張