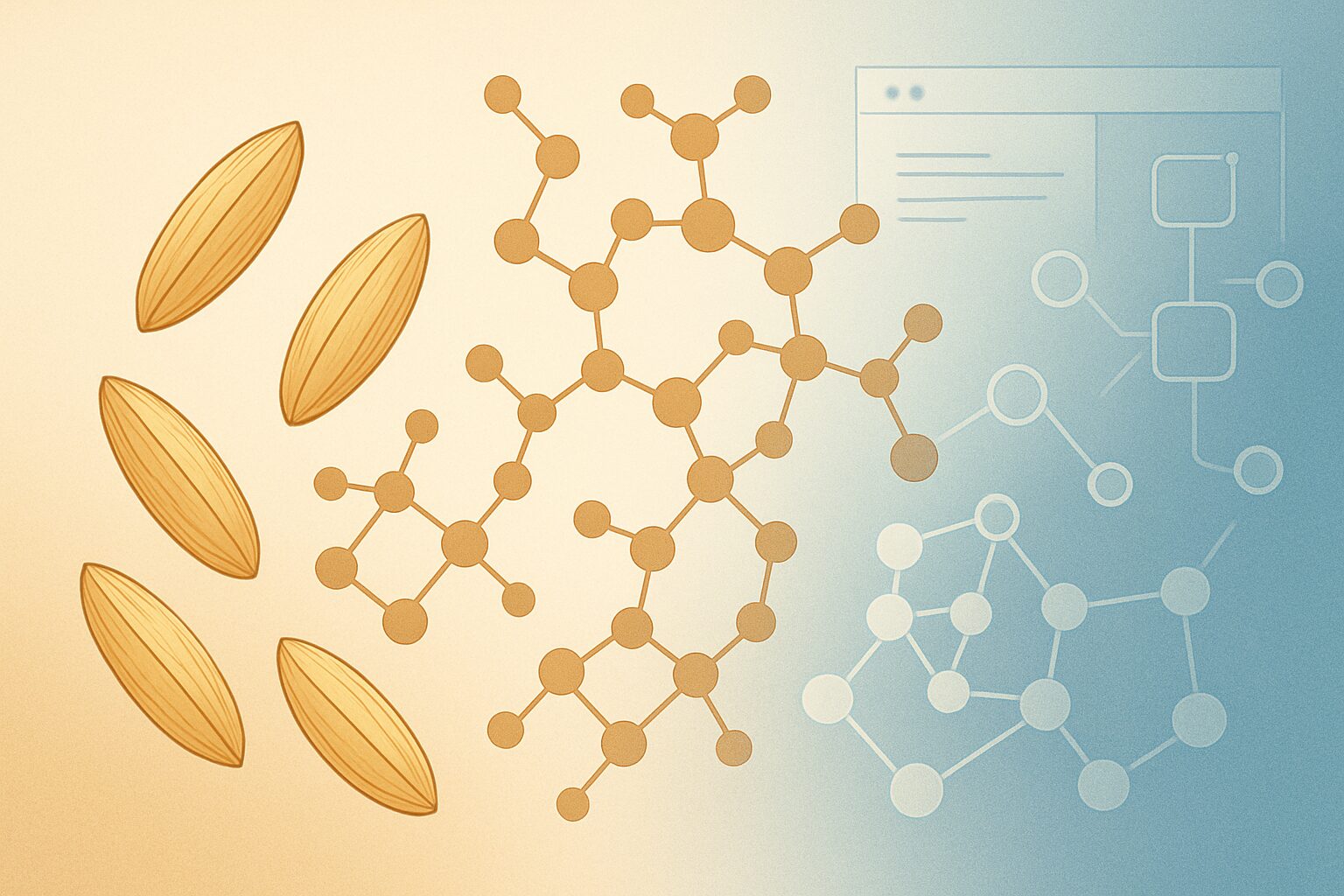米菓の構造と思想の予感
米菓を鑑定していると、時々「思想」に浸ることがある。もち米は、加熱され水を含むとデンプン分子がほどけ、私の解釈では、やがて新たな構造を生み出していく※1。目には見えないその秩序が、粘りや噛み応えという食感を支えている。
思想もまた、似ているのではないだろうか。個々の「我思う」は、ただの粒子にすぎない。しかし経験や対話に触れると、それらは互いに作用し、結びつき、構造を帯び始める。
思想は集合ではなく、粘性を持つまとまりとして立ち上がる。
粒子から粘りへ ― 思想の構造
デカルトが示した「我思う、故に我あり」は、一粒の米のような確実性だった。孤独な主体の声が唯一の像として鏡に映る。
だが思想は孤立した点にとどまらない。米の粒が結合し粘りを持つように、思考もまた関係の中で粘性を生む。私の感覚では、思想とは、一つひとつの断片が絡み合い全体の質感を備えたときに初めて姿を現すのだ※2。
時間と分身 ― 思想の連続性
時間の哲学者ベルクソンは「持続」と呼び、ハイデガーは「時間的存在」と呼んだ。人は常に過去の自分、現在の自分、未来の可能性として存在している。
この姿は、分身が連なり構造をつくるイメージに近い。私の中には「もう過ぎ去った私」と「まだ来ぬ私」が同居している。それらが連続することで、思想は一回限りの閃きを超え、時間にまたがる粘りを持つ。
AIと共創する思想
現代では、AIが私の外に現れた分身として機能する。あるAIは過去を整理し、別のAIは現在を言語化し、さらに別のAIは未来を予測する。
複数のAIと同時に対話する体験は、時間に散らばる自分と同時に語り合うことに似ている。モニターに映る複数の「我思う」を束ね、意味あるまとまりへと編集していく作業。それはまさに共創としての思想のプロセスだ。
思想は構造である
私にとって思想とは、粒子の集積ではなく、関係が立ち上げる生成的な秩序そのものである※3。米菓を割るときに響く乾いた音が、内部の秩序の証であるように、思想の一文もまた、見えない構造が確かに存在していることの証なのだ。
思想に浸るとは、米菓の”味わい”を支える目に見えない構造をたどることだ。そこには、米菓鑑定と哲学のあいだにひそむ、思わぬ共鳴がある。私は米菓を鑑定するうちに、思想を鑑定するようになった。粒子の構造から学んだ眼差しは、AIと共に編む思想の粘りへと拡張していった。
だから私は時折、こう思うのだ。米菓鑑定士でありながら、知らぬ間にAI共創思想家へと変容しつつあるのかもしれない、と。
読者への問いかけ
あなたにとって思想とは、粒子のように数えられるものだろうか。それとも、粘りを生む構造として立ち上がるものだろうか。そして、AIという分身と共に生まれる思想の粘性を、あなたはどう味わうだろうか。
脚注
※1 科学的には、デンプンの糊化過程において、生のデンプン粒に存在する結晶性のミセル構造は加熱により崩壊し、デンプン分子が水中で絡み合った粘性のあるゲル状態へと変化します。本稿では、この物理的変容を、硬直した思考から柔軟な思想への変化の比喩として詩的に解釈しています。
※2 ここでいう「構造」は、構造主義における形式的・規定的な構造ではなく、現象学的な意味での生成的秩序、すなわち経験の中で立ち現れる質感的なまとまりを指しています。
※3 本稿における「構造」という用語は、私の主観的体験に基づく詩的表現であり、学術的な厳密性を意図したものではありません。読者の皆様には、ご自身の解釈の余地を残したいと考えています。
※本記事は筆者の実体験を中心に構成しています。