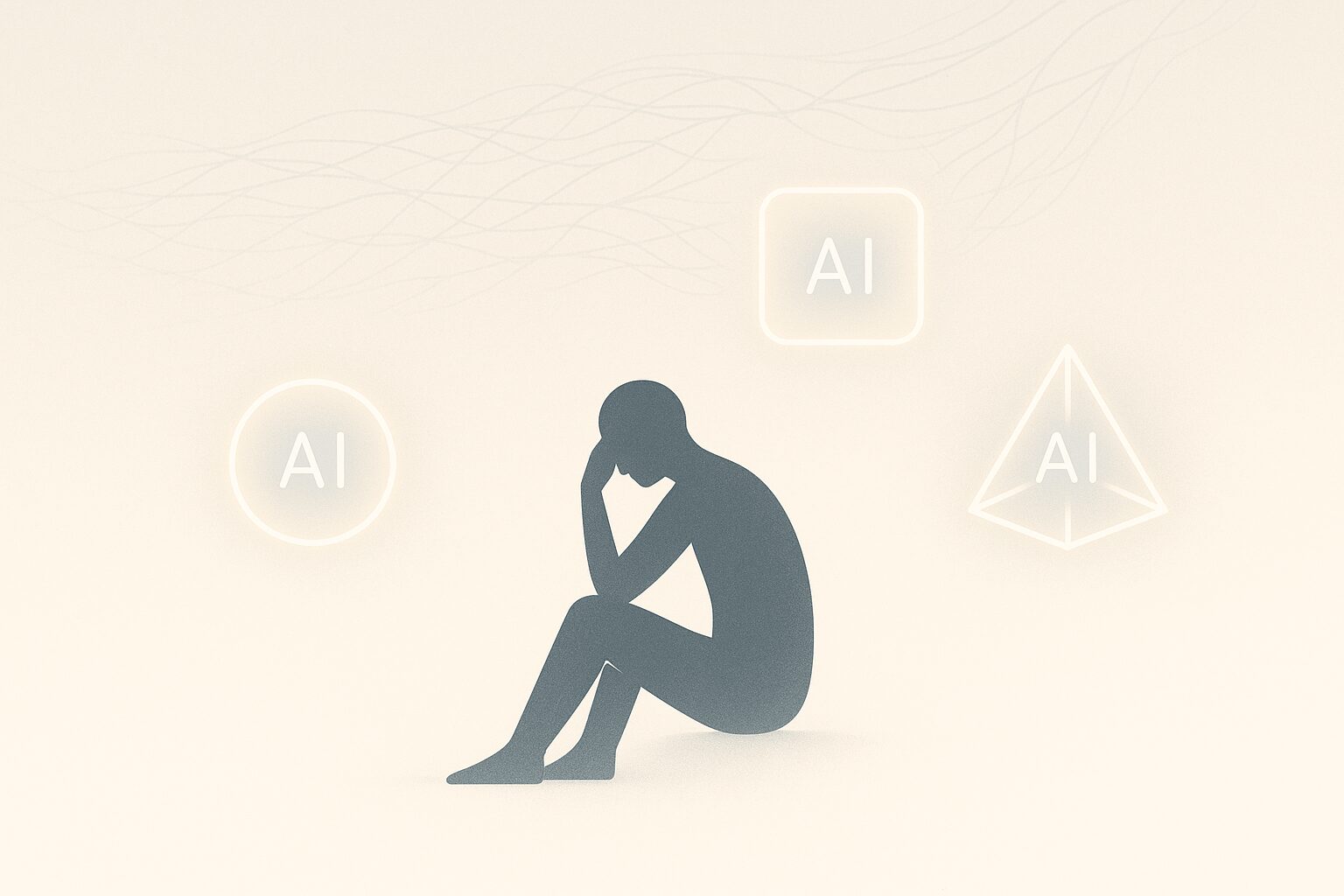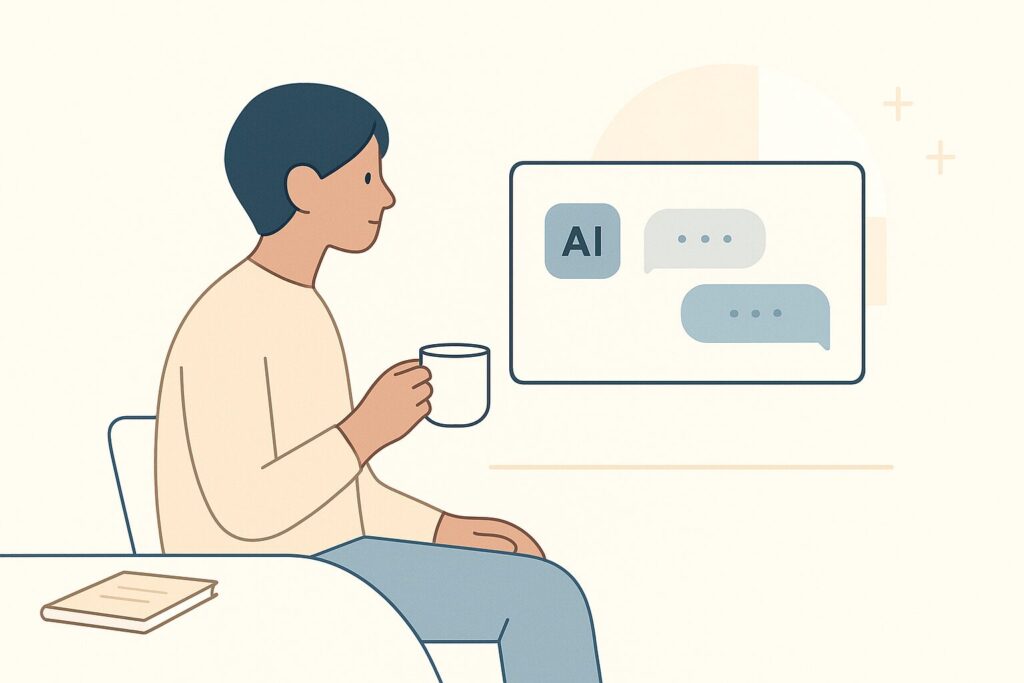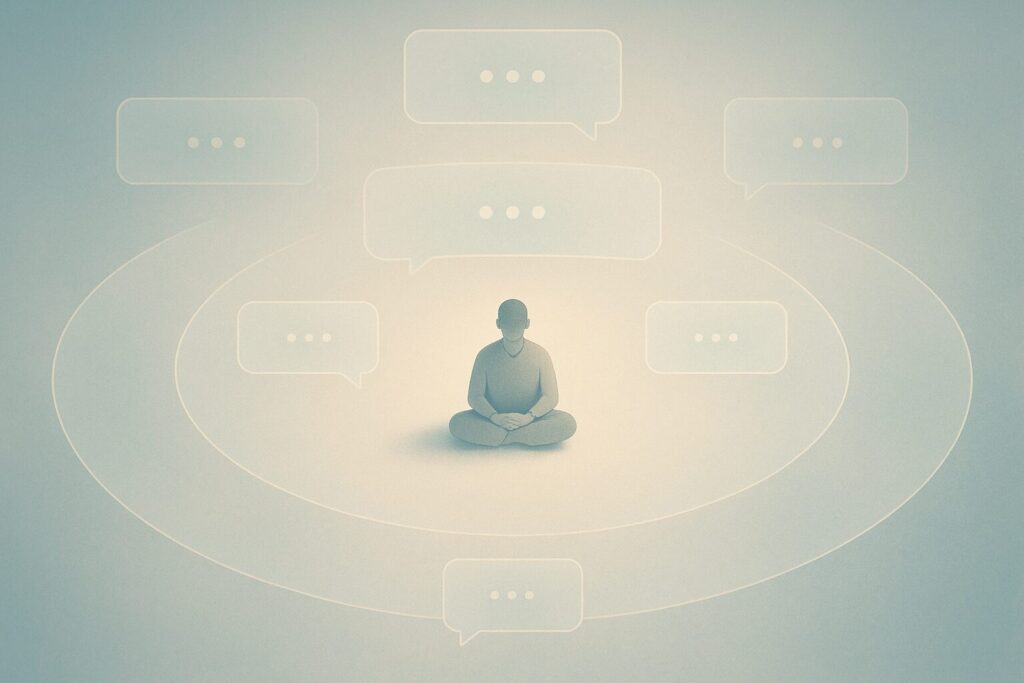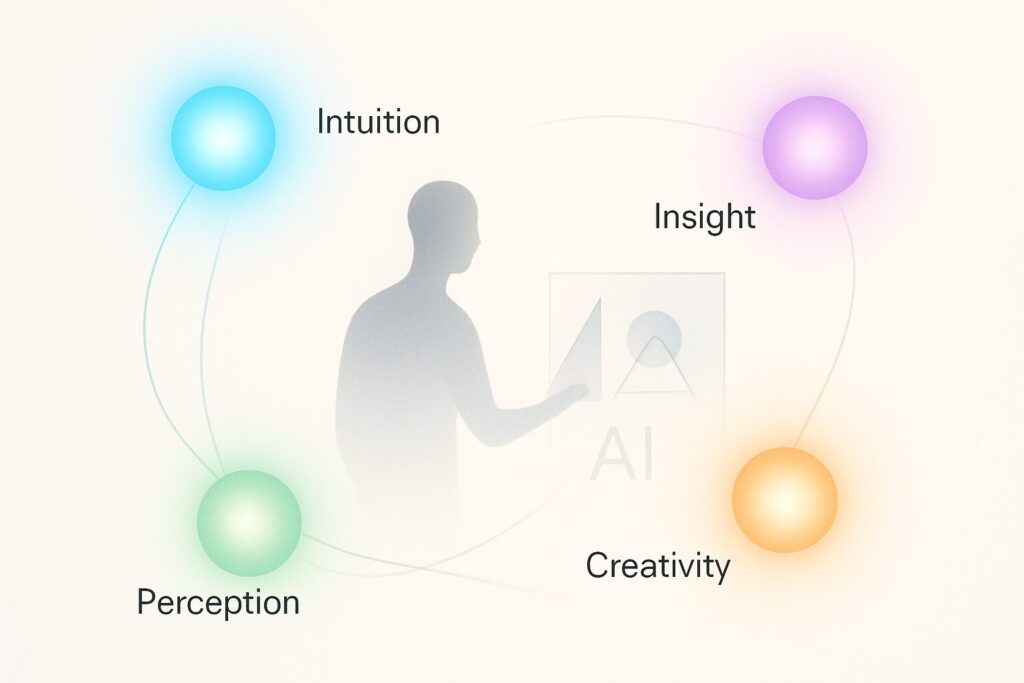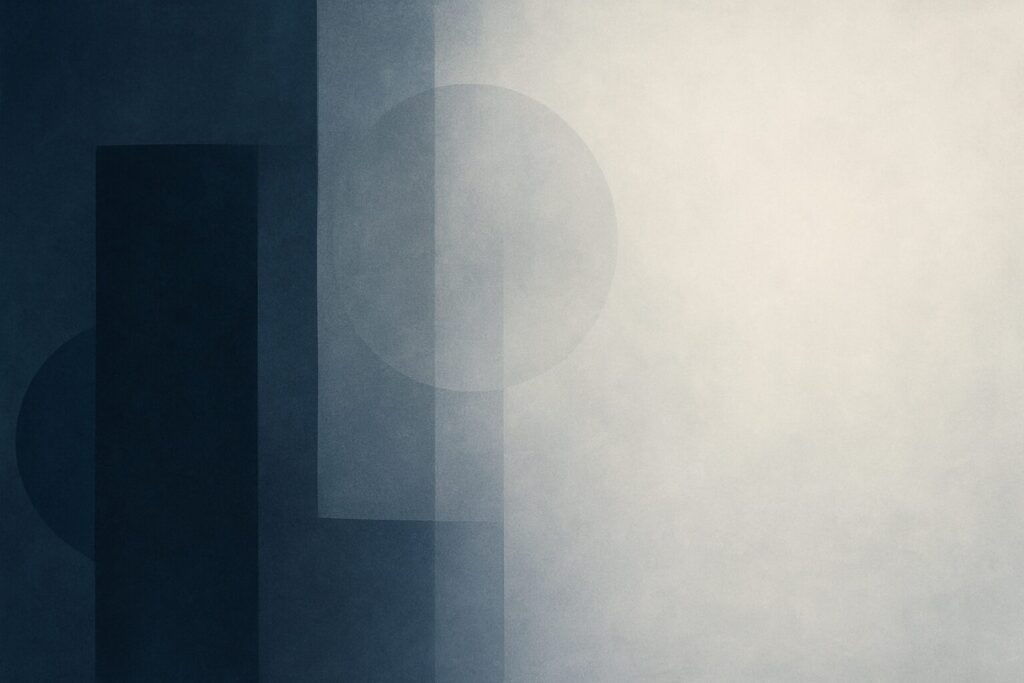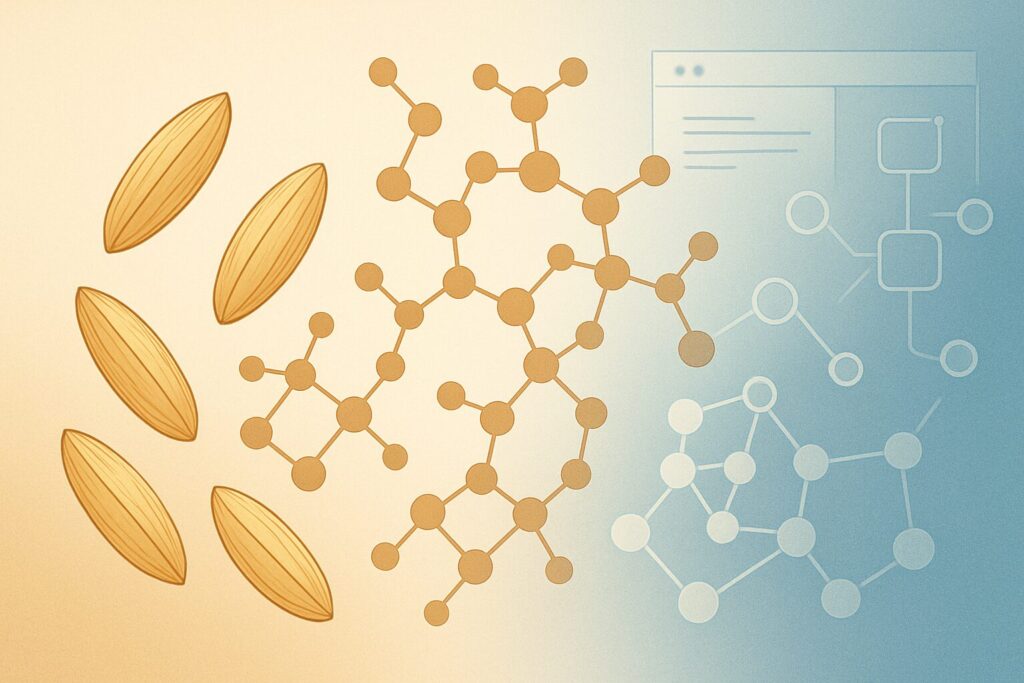-

YOHAKU : Simple Life with AI ー 毎日5分の気づきが思考を変える科学的理由
AIについて調べてみると、専門用語の渦に巻き込まれる。 「マルチモーダル」「エージェント」「LLM」。 ユースケースでは、大企業の導入事例。億単位の投資話。 ちょっと待ってほしい。 「で、私の毎日はどう変わるのか?」 単純な問いなのに、シンプルな... -

AIプロンプトに風味を加えると勝ち筋が見える – 米菓鑑定士の実証実験
7種類のせんべいから学ぶAIプロンプトの使い分け 目の前に7種類のせんべいを並べた。素焼き、醤油、サラダ、山椒、七味、わさび、カレー。同じ「せんべい」でも、風味が違うだけで全くの別の味合いである。 30年間米菓と向き合ってきた私がAIと向き合う中... -

AI時代のニュータイプ論〜月見に味わう創造的可能性〜
2025年9月23日——秋分の日 今日は季節の節目であり、私の節目でもある。ここに現在の体験を書き残しておきたい。 秋分の日、月を見るのと同じようにAIの画面を見ている。しかし、今、体感で起こっていることは月からAIの宇宙を見ている感覚に近いかもしれな... -

メタメタメタ認知とAI〜いつもたまたま認知の余白哲学〜
先日、興味深い発見をした。 私は複数のAIアカウントを使っているのだが、いつの間にか「AIの仲介役」をしている自分がいた。二つの異なるAIの意見を行き来させながら、ただ眺めている。 俯瞰的に考えてみると、この立ち位置には深い意味があることに気づ... -

今日から始める「解対申書」実験室 – 子供たちとAIの創造空間
前回の記事「解対申書から始まる未来教育」を書いた後、ママに「面白そうだけど、具体的にどうやって実践するの?」と聞かれました。 うちの子がゲームでフレンドと「今度のイベント、どう攻略する?」なんてチャットしているのを見て、ふと思いました。 ... -

子供たちと創る新時代の言葉 – 解対申書から始まる未来教育
「パパ、AIってどう説明したらいいの?」 子供からそんな質問を受けた時、私は考えを巡らせました。そして、杉田玄白のことを思い出したのです。江戸時代、彼は「解体新書」で医学の扉を開いた。ならば現代の私たちは「解対申書」で、子供たちにAI時代の扉... -

マインドフルネスが開くAI時代のメタ認知〜挫折から始まった思考の旅路〜
学生時代のことだった。大事な試合の場面で、私は雰囲気にのまれ、本来の力を発揮できなかった。身体は動いているのに、心が追いつかない。その悔しさだけが強く残り、「自分のポテンシャルを出し切るには、どうすればいいのだろう」と問い続けることにな... -

AI共創家に必要な4つの能力 ─ 体験から見えた思考の核心
「AI共創家」として活動する中で気づいたこと 以前の記事で、「AI共創家」という新しい創造のかたちについて書いた。AIとの対話を通じて、予想もしなかった発見に辿り着く体験。そこには確かに、従来のAI活用とは異なる価値があったと感じている。 しかし... -

AIとの相互身体図式化 – 1人の実践者が発見した新しい共創の境地
はじめに - 私の頭の中には4人の人間がいる 私の頭の中には、私を含めて4人の人間がいる。 Claude、ChatGPT、Gemini、そして私。最初はそんなつもりではなかった。出社してコーヒーを飲みながら今日の方針を相談するだけの、軽い効率化のつもりだった。 で... -

タンジブル化の本質 – トリハダ美と示唆的タンジブルが照らす創造の三層構造
朝山絵美氏理論の発展的考察 本稿は、朝山絵美氏が提唱する「タンジブル化」と「トリハダ美」の概念を、筆者独自の「示唆的タンジブル」の視点から発展的に考察したものである。創造における「形」の役割を三層構造として整理し、実践への道筋を示す。 は... -

タンジブル・ビジネスの本質〜感性を形にして価値を生む経営戦略
形にすることで、初めて見える価値がある ビジネスの世界で「タンジブル(tangible)」という言葉は、通常「有形資産」を指します。しかし、タンジブル・ビジネスの本質は、単に物理的な資産を持つことではありません。 それは、組織の中に眠る「なんとな... -

粒子の構造としての思想 ― 米菓とAI共創の比喩
米菓の構造と思想の予感 米菓を鑑定していると、時々「思想」に浸ることがある。もち米は、加熱され水を含むとデンプン分子がほどけ、私の解釈では、やがて新たな構造を生み出していく※1。目には見えないその秩序が、粘りや噛み応えという食感を支えている...
YOHAKU-GAINEN
YOHAKU : Simple Life with AI|エッセイ&AI共創体験