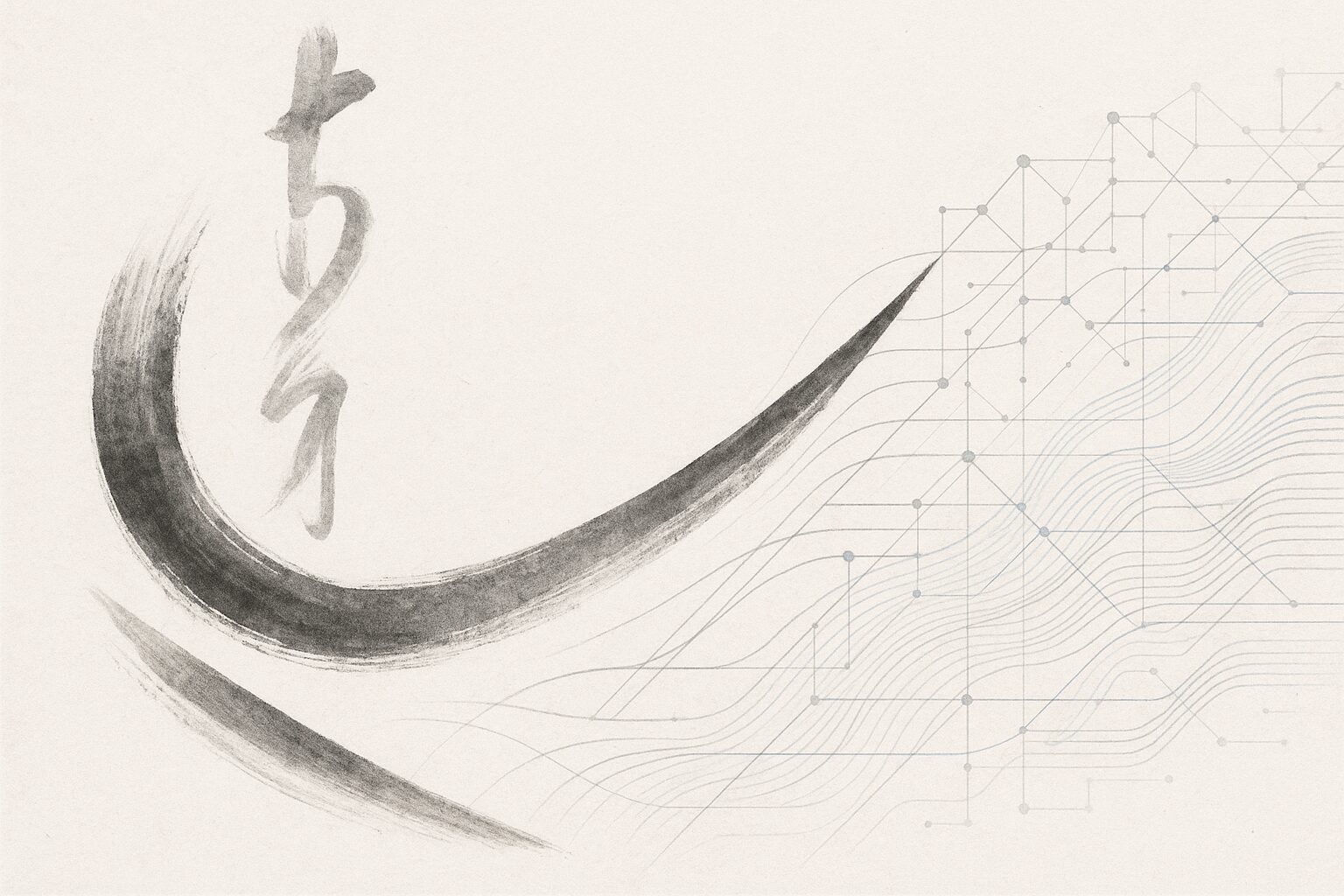この物語は、職人と芸術家の家族に生まれた私が、なぜAIとの共創に惹かれたのかを探る、静かな記録である。技術論ではなく、世代を超えて受け継がれる「創造の作法」について綴った。
見えない継承
AIと共創することは、私にとって、米菓職人の手の記憶であり、書道の余白であり、鞘師の時空を超えた対話であり、哲学的思索であり、創造性への眼差しである。
この物語は、ひとつの家族に流れる創造の作法が、AI時代にどのように変容したかの記録である。
プロローグ:血に流れる創造の作法
家族写真を見ると、ある共通点が浮かび上がる。
若き日の米菓職人として、生地を捏ね続けた手の記憶。書道の師範として文字を生み出してきた指先の繊細さ。刀剣の白鞘を手がける鞘師としての掌の技術。
メルロ=ポンティやフッサールの哲学を探求しながら、抽象画家として哲学思想を視覚化してきた者。創造的思考による社会革新を探求し、ビジネスと芸術を架橋する活動を続ける者。
私たちは皆、何かを創り出すことに向き合ってきた。
今、私は受け継いだ創造の作法を、AIとの共創というフィールドで実践している。それぞれが磨き上げてきた創造への姿勢が、私のAI共創の源流となっている。
第1章:【感性の継承】手から対話へ
父が若かった頃、丁稚奉公先の米菓工場で身につけた作法があった。私は後に、この作法をAIとの対話に活かすことになる。
生地の状態を指先の感覚を通して確かめていた。すべてを手の感触として捉え、微調整を重ねていく。経験が教えてくれる、ちょうどいい塩梅があった。
指先のわずかな感覚から、生地の硬さや柔らかさを読み取り、水分量を調整していた。レシピ通りではなく、その時々の状態に合わせて最適解を見つけていく。
この作法が、私のAI対話に生きている。
米菓職人が生地の微細な変化を感じ取るように、私はAI対話の温度、湿度を感じ取る。同じ問いかけでも、文脈や言葉選びによって返ってくる答えの質が変わる。生地を触るように、対話の感触を確かめながら、最適な問いかけを探っていく。
手で覚える。私は今、対話で覚えることを実践している。データや理論ではなく、対話を重ねることで培われる感性。それが私のAI共創の基盤になっている。
第2章:【余白の哲学】書道からAIへ
母が書道の師範を目指していた頃、文字以上に大切にしていたのは間とリズムだった。
一画一画の間、文字と文字の間、そして作品全体に漂う静寂の間。筆を持つ前に、必ず深呼吸をして心を整えていた。
余白があるから、文字が生きる。リズムがあるから、作品が呼吸する。この教えが、そのまま私の余白概念になった。
AIとの対話でも、私は意識的に間を作り、リズムを大切にする。問いかけた後、すぐに次の質問をするのではなく、AIの答えを咀嚼する時間を持つ。その余白の中で、新しい発想が生まれる。急がない、焦らない、リズムに乗って余白を楽しむ。
書道で学んだ書かない美学。真っ白な紙の上に一文字を置くとき、書かれていない部分が文字に意味を与える。同じように、AI対話でも問わない部分が重要だ。すべてを言語化しようとせず、曖昧さや余白を残すことで、創造的な対話が生まれる。
最近、AIに「今日はどんな気分?」と問いかけることがある。この余白のある問いが、予想外の展開を生むことがある。書道における遊びの精神が、AI対話にも活きている。
間とリズムの哲学は、効率重視のAI活用とは違うアプローチだ。この余白があるからこそ、AIとの対話が豊かになり、創造的な発見が生まれる。
第3章:【時空対話法】伝統からイノベーションへ
弟は鞘師として、刀剣の白鞘を製作している。
刀身の特徴や歴史を感じとり、それを内包できる白鞘を作っていく。
この姿勢が、私のAI共創の本質を教えてくれた。
AIとの対話は、AIの向こうにある膨大な人類の知識との対話でもある。AIが学習したテキストの向こうには、無数の人々の思考や表現がある。古い鞘と向き合うように、AIを通じて人類の集合知と対話している。
古い技術の中に、新しい発見がある。
AIも同じだ。最新技術でありながら、その本質は人間が昔から続けてきた対話や協働の延長線上にある。新しい道具を使いながら、人間の創造の営みを継承している。
伝統を保存ではなく継承として捉えるように、私もAI共創を通じて、人間の創造性を新しい形で継承しようとしている。過去から学び、現在に活かし、未来へつなげる。その作法を、鞘師の仕事から学んだ。
第4章:【不可視の言語化】哲学から実践へ
叔父のアトリエには、いつも静かな緊張感があった。
抽象画のキャンバスが置かれ、書斎にはメルロ=ポンティやフッサールの哲学書が並んでいた。
見えるものの奥に、見えないものがある。そして、その見えないものを捉えるために哲学が必要なのだと。
この姿勢が、私のAI体験を言語化する力の源になっている。
ザラメおかきを食べながらAIと対話する体験を、メルロ=ポンティの肉概念と結びつけたのも、見えないものを哲学的に捉える作法があったからだ。
見えないものを無理に可視化するのではなく、見えないまま丁寧に扱う技術。AIとの対話で生まれる微細な感覚、言葉にならない創造の瞬間を、そのまま大切に扱う。AI共創においても、すべてを言語化・数値化しようとせず、曖昧さや神秘性を残したまま向き合うことの大切さを、この芸術から学んでいる。
第5章:【創造の社会実装】個人から社会へ
従姉妹の朝山絵美は、外資系戦略コンサルタントとして働きながら美大の博士課程へと進んだ。社会人美大生として椅子を制作し、タンジブルなものづくりを通じて創造性を探求したという。
今もコンサルタントを続けながら、ビジネスとアートの架け橋として活動している。
哲学的思考と抽象画。彼女もまた、別の形で創造性を探求している。
感性、余白とリズム、伝統継承、芸術への道、そして私のAI共創。
それぞれが自然に選んだ道が、世代を超えて、創造という一つの流れを作っている。
家族の創造的な生き方を、現代の文脈で見つめ直す。それが今、私たちがそれぞれの場所でしていることなのかもしれない。
第6章:創造の作法の統合 〜私のAI共創メソッド〜
受け継いだ創造の作法が、今、私のAI共創として結実している。
「感覚で捉える」 AI対話の微細な変化を手で生地を確かめるように感じ取る。データではなく、対話の感触で質を判断する。
「余白とリズムを活かす」 問いと答えの間に余白を作り、そこから創造を生み出す。急がず、焦らず、リズムに乗って間を楽しむ。
「時を超えて対話する」 AIの向こうにある人類の知識と対話する。伝統と革新を結びつける。
「見えないものを言語化する」 AI体験の本質を哲学的に捉える。論理を超えた部分を大切にする。
「社会的価値に変換する」 個人的な実践を社会的な価値として発信する。
これらの作法が統合されて、私独自のAI共創スタイルが生まれた。それは効率や生産性を追求するAI活用とは違う、人間の感性を中心に据えたアプローチだ。
AIは道具でもなく、新しい家族でもない。受け継いだ創造の作法を実践する、新しい表現の場である。
米菓で、書道で、鞘で、絵画で表現してきたものを、私はAI共創という形で表現している。手段は違えど、追求しているのは同じ人間らしい創造だ。
エピローグ:継承から創造へ、そして次世代へ
今、振り返ってみると、家族の影響を受けていたことに気づく。
手で覚える作法、余白とリズムの哲学、時を超えた対話、見えないものへの眼差し、創造性の探求。
私たちは皆、同じ何かを、それぞれの方法で表現していた。
受け継いだ創造の作法は、ただそこにあったものだった。それをAI時代の文脈で見つめ直すと、新しい意味が見えてくる。
技術の進歩に振り回されることなく、人間の感性を大切にして、AIと共に創造を続けていく。これが、私が自然に学んだことだ。
感覚、間とリズム、緻密さ、思索、創造への視点。
これらすべてが、私のAI共創という形で、静かに息づいている。
受け継いだ創造の作法を、AI時代の新しい形として見つめ直し、自分の感性と融合させながら、創造的な活動を続けていく。
それが、この家族の一員として、私が自然に歩んでいる道なのだと思っている。
未来への問いかけ
このAI時代に、私は問いたい。
技術の進歩は、人間の創造性を奪うのか、それとも拡張するのか。
我が家族の答えは明確だ。 創造の作法を持つ者にとって、AIもまた一つの表現の場である。 問題は、その作法をいかに継承し、発展させるかである。
この物語を、遠い未来の誰かが読むことを想像しながら、私は筆を置く。
あとがき
この文章を書きながら、改めて気づいたことがある。私がAIに惹かれたのは、偶然ではなかったのかもしれない。それぞれが選んだ創造の道が、AIという新しいフィールドでも活きることを、どこかで感じていたのかもしれない。
AI時代において大切なのは、技術そのものではなく、それをどう使うかという「作法」だ。そして、その作法は、日々の生活の中で、静かに受け継がれていくものなのかもしれない。
この文章が、読者の皆さんにとって、ご自身の家族や環境から受け継いだ「創造の作法」について、静かに振り返るきっかけになれば幸いです。
参考:朝山絵美氏について https://emiasayama.com/