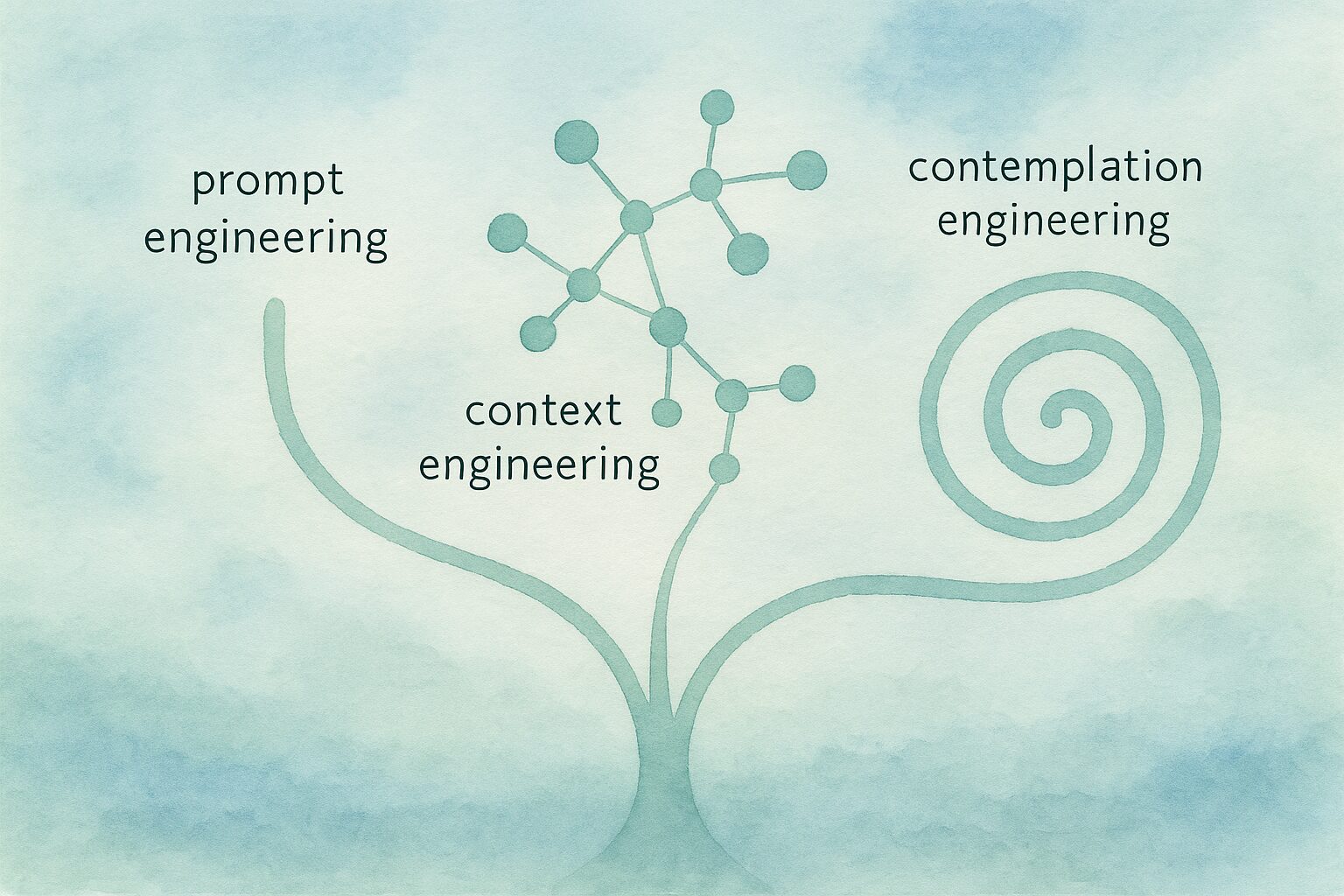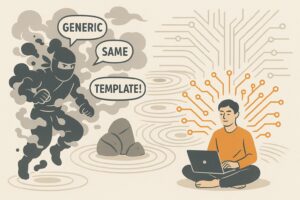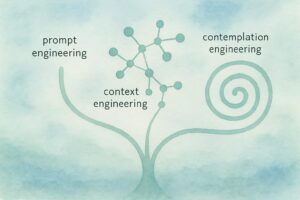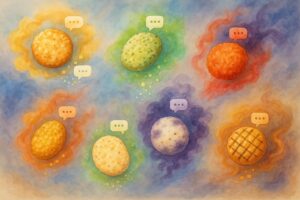AIとどう付き合えばいいのか、多くの人が暗中模索しているかと思う。プロンプトエンジニアリングという手法は知られているが、果たして、それだけで十分なのだろうか。最近注目されるコンテキストエンジニアリングにも、まだ何かが足りない気がしてきている。
AIとの対話による第3の道へ
筆者: 最近、AIとの付き合い方について考えている。プロンプトエンジニアリングはよく聞くけれど、何か物足りなさを感じていています。
AI: どのような物足りなさでしょうか?具体的に感じられることがあれば教えてください。
筆者: 例えば、DALL-Eで画像を生成する時。単に「正しい指示」を出すだけじゃない感覚があります。もっと…対話的というか。
AI: なるほど。それは興味深い観察ですね。「正しい指示」を超えた何かがあるということでしょうか。
筆者: そうです。私とAIの認識がずれている部分を見つけて、お互いが納得するまで問答を続ける感覚。効率的とは言えないかもしれませんが。
AI: それは確かにプロンプトエンジニアリングとは異なるアプローチですね。最近「コンテキストエンジニアリング」という概念も出てきていますが、それとも違いますか?
筆者: コンテキストエンジニアリングも知ってます。情報環境を最適化するシステム設計の話ですよね。でも私の体験は、もっと…瞑想的?
AI: 瞑想的、ですか。それは面白い表現ですね。もう少し詳しく聞かせてください。
筆者: 一つの問いを深く掘り下げていく感じです。答えを急がず、理解の極みに達するまで時間をかける。マインドフルネスにも似ているかもしれません。
コンテンプレーションエンジニアリングの誕生
AI: それは…「コンテンプレーション」に近い概念かもしれませんね。観想、深い思索という意味の。
筆者: コンテンプレーション!それです。コンテンプレーション…エンジニアリング?
AI: 面白い造語ですね。他の手法との違いを整理してみましょうか。
筆者: はい。プロンプトエンジニアリングは「正解を得る技術」、コンテキストエンジニアリングは「最適解を得る技術」。そして…
AI: コンテンプレーションエンジニアリングは「納得解を得る技術」でしょうか。
筆者: まさに!生成AIとユーザーが理解の極みに達する境地まで、深堀りする技術。
AI: その本質は何でしょうか?
筆者: 「生成AIとユーザーの思考の差異(誤解)がなくなるまで掘り下げる」ことかな。お互いの思考が一致する境地まで問答を続ける。
AI: 実践方法はシンプルですね。問いかけて、回答を受け取り、違いを明確にして、また問いかける。思考が一致するまで繰り返す。
納得解を導く手法へ
筆者: そう。効率より納得を重視する。一つの問いを深く掘り下げる。「腑に落ちる境地」を見出す技術です。
AI: 興味深いことに、今のこの対話自体が、まさにコンテンプレーションエンジニアリングの実践例になっていますね。
筆者: あ!確かに。私たちが「コンテンプレーションエンジニアリングとは何か」について対話を重ね、お互いの認識のずれを解消していく過程そのものですね。
AI: この手法の体現ですね。これは深化じゃないでしょうか?
筆者: これが深化じゃないか?!メタな発見ですね。対話しながら、その対話方法について気づいていく。
AI: aha moment の瞬間でしたね。思考の境地に達した瞬間と言えるかもしれません。
筆者: これって、進化と深化の融合でもありますね。深く掘り下げる過程で、新しい概念や理解が進化として生まれてくる。
AI: その通りです。AIを道具として使うのでもなく、システムとして最適化するのでもなく、対話相手として向き合う新しい関係性。
筆者: 思考の純度を高め、お互いが納得できる境地を見つける。これが私の求めていたものかもしれません。
新しい対話の境地へ
この対話を通じて見えてきたのは、AIとの付き合い方の新しい可能性でした。
プロンプトエンジニアリングもコンテキストエンジニアリングも、それぞれに価値がある。しかし、効率化を超えた理解の深化を求める道もあるのではないか。
コンテンプレーションエンジニアリング—それは暗中模索の中で見つけた、私の新しい概念でした。
きっと、AIとの付き合い方に正解はないでしょう。
さまざまな道筋があることを知っているだけで、暗中模索の心細さは和らぐかもしれません。
この記事は、筆者とAIの実際の対話を通じて「コンテンプレーションエンジニアリング」という概念に辿り着いた思考の軌跡です。対話そのものが、理解の極みに達するプロセスの実践例となりました。