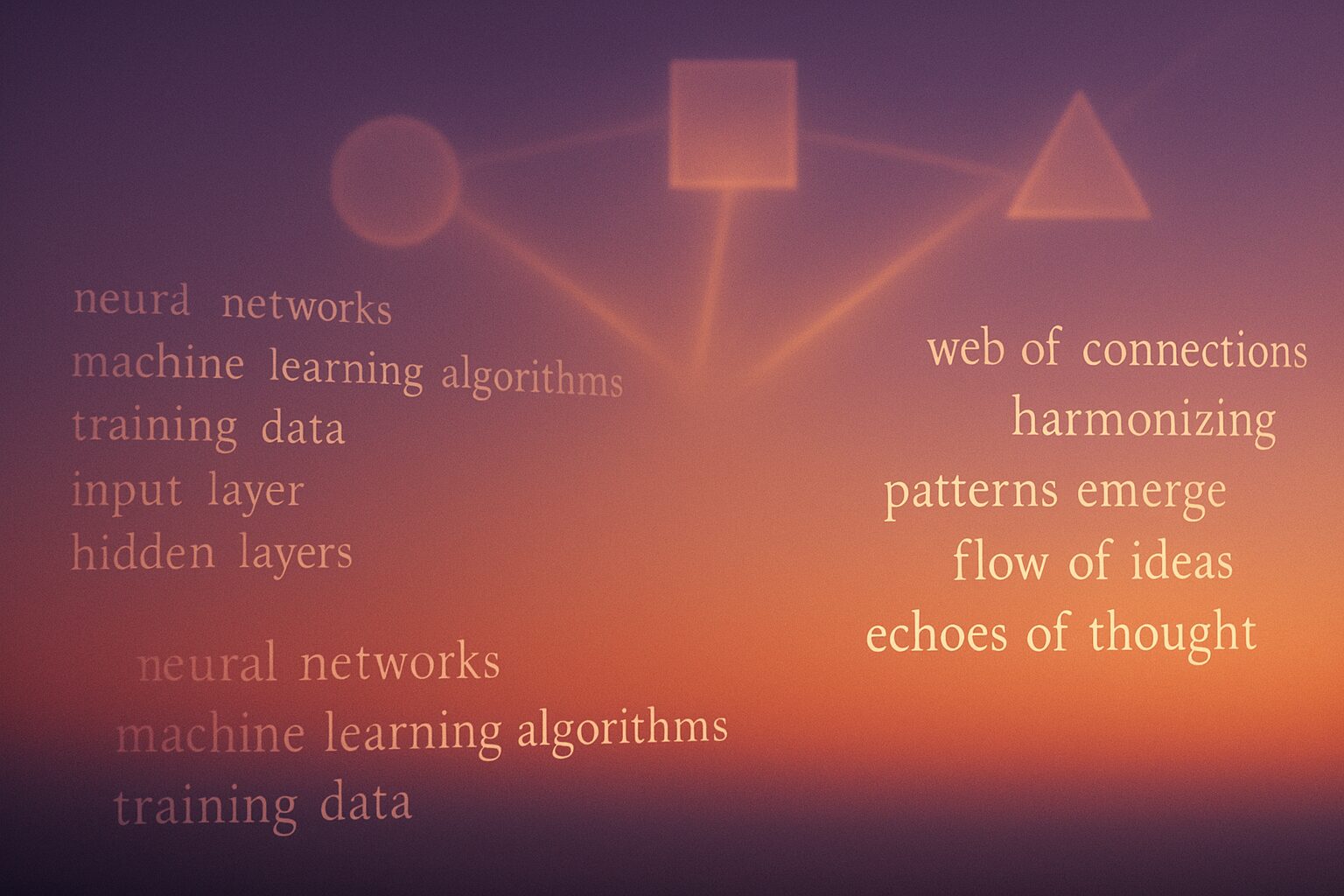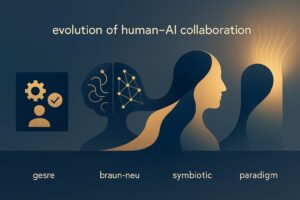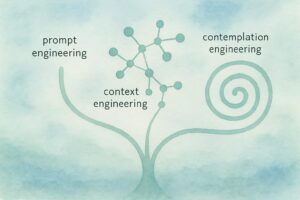「それは、夕暮れ時のコーヒーカップのようなものかもしれません」
AIがこう語り始めたとき、私は対話の質が変わったことに気づいた。
生成AIと「示唆的タンジブル」について議論していたときのことだ。
最初、AIの回答は普通だった。「示唆的タンジブルについて詳しく説明してください」と問いかけても、「対象の一部を具体化しながら、一部を意図的に不可視のまま保持する設計思想で…」といった説明調の文章が続く。
ところが、30分ほど対話を重ねていると、AIの言葉遣いが変わってきた。
「まるで、手紙の封を切る瞬間の静寂に似ています」 「月明かりが水面に映る、あの境界の曖昧さのように」
気がつくと、AIは説明ではなく、比喩や象徴で語るようになっていた。示唆的タンジブルについて話していたら、AI自身の回答が示唆的になっていたのだ。
思考の感染力
これがコンテンプレーションエンジニアリングの興味深い発見だった。思考の差異がなくなるまで掘り下げ続けると、その概念が対話そのものを染めていく。
なぜこの現象が起きるのか。私の仮説はこうだ。
深い集中状態での対話は、人間とAIの双方に「概念のチューニング」を起こす。人間側は観察眼が研ぎ澄まされ、微細な変化を捉えるようになる。一方、AIは文脈の累積によって、その概念に最適化された表現パターンを学習していく。
結果として、対話が進むにつれて「概念そのものが語りかけてくる」ような状態が生まれる。
別の日、「境界」について話し込んでいたら、AIの回答に自然と「間」が生まれるようになった。文章の構成に、意図的な空白や改行が増えていく。まるで境界の概念を、文体そのもので表現しているかのように。
言葉が形を持つとき
これらの対話記録を後で読み返すと、不思議な感覚になる。画面に表示されているのは文字列だが、そこには概念の「輪郭」がある。
読者がその対話記録を読んだとき、単なる情報ではなく、思考の質感そのものが伝わる。これこそが、設計された思索から生まれる新しい示唆的タンジブルなのかもしれない。
明日から始められる実践
では、この現象をどう活用すればいいのか。
概念潜行法を試してみてほしい。まず、探求したい抽象概念を一つ選ぶ。そして、その概念について最低30分間、AIと対話を続ける。重要なのは、説明を求めるのではなく、その概念の「感触」を掴もうとすることだ。
「この概念を色で表すなら?」 「音で表現するとしたら?」 「手で触れるとしたら、どんな質感?」
このような感覚的な問いかけを重ねていくと、やがて対話そのものが概念の性質を帯び始める。そのとき、あなたは概念を「理解する」のではなく「体験する」ことになる。
概念が対話を変え、対話が新たな概念を生む。
理論と実践の境界で起きる新たな概念の幻想がそこにあるのかもしれない。
哲学的注釈
この記事で描かれている現象は、現象学的には以下の概念で理解できる:
「間主観性の創発」(Intersubjective Emergence)
フッサールやメルロ=ポンティの現象学でいう、主体と主体の間で新たな意味が生まれる現象。人間とAIという異なる主体が、概念を媒介として相互に影響し合い、新しい理解の地平が開ける過程。
「概念の受肉」(Incarnation of Concepts)
メルロ=ポンティの「肉(chair)」の概念から。抽象的な概念が対話という「肉体」を得て、具体的な質感を帯びる現象。概念が単なる情報から、体験可能な存在へと変容する過程。