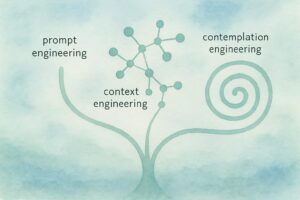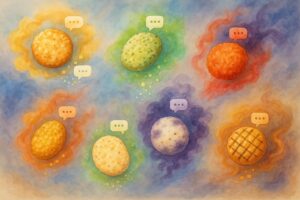Claude ProでOpusとSonnetを使える環境
Claude Proを使い始めて120日が経ちました。
OpusもSonnetも自由に選べる環境で、毎日ブログ記事を書きながら、どちらを使うか試行錯誤してきました。その中で感じたことを、体験ベースで共有させていただきます。
OpusとSonnetの違いとは?それぞれの個性
実際に使ってみると、OpusとSonnetには、それぞれ独自の個性があることに気づきました。
Opusと対話している時の感覚
壮大な作品を一緒に紡いでいるような時間。投げかけた話題を、いろんな角度から丁寧に考えてくれます。休日の静かな午前は、じっくりとアイデアを練る時によく選んでいます。
Sonnetと対話している時の感覚
洗練された詩のように、要点を美しくまとめてくれる存在。「これをこうしたい」という想いに、リズミカルに応えてくれます。午後の執筆時間に、テンポよく書き進めたい時に選ぶことが多いです。
名前の由来を考えると興味深いですね。Opus(作品)、Sonnet(詩)。異なる芸術形式のように、それぞれの表現には美しさを感じています。
120日使って分かった特性の違い(比較表)
120日間の体験を通じて感じた違いを、あくまで参考程度ですが、表にまとめてみました。
| 観点 | Opus 4.1 | Sonnet 4.5 |
|---|---|---|
| 回答の範囲 | 網羅的・多角的 | 焦点的・実践的 |
| 思考の深さ | 前提から問い直す | 与えられた枠で最適化 |
| 処理速度 | じっくり | 高速 |
| 説明の仕方 | 背景含めて詳細に | 要点を簡潔に |
| 提案スタイル | 複数の可能性を提示 | 実行可能な案に絞る |
これは優劣ではなく、単純にアプローチの違い。長編小説と短編小説を比べるようなもので、どちらにもそれぞれの価値があります。
OpusとSonnetの使い分け:実践パターン
120日経った今、自然とこんな使い分けに落ち着いています。
記事の企画段階
「今日は何を書こうかな」という段階では、Opusを選ぶことが多いです。白いキャンバスに向かうように、可能性を一緒に探っていく過程が心地良いです。
記事の執筆段階
構成が決まって「さあ書くぞ」という時は、Sonnetを選びます。14行詩のような規律の中で、効率的に文章を整えてくれる感じが、執筆のリズムに合っています。
これは絶対ではありません。その日の気分や体調、創作への向き合い方によって、自然と手が向かう先が変わります。
発見:モデル選択で対話の質が変わる
プロンプトの書き方で見える風景が変わる
明確な指示を出せるようになってくると、OpusでもSonnetでも期待通りの回答が返ってきます。でも、面白いのは「同じ答え」ではないということ。
例えば「新しいテーマに関する記事の構成を考えよう」という同じ内容でも、Opusは可能性の域を見せてくれ、Sonnetは実行への道筋を示してくれる。
どちらも正解で、どちらも必要です。
Constitutional AIの思想を体感して
Anthropicが大切にしている「Constitutional AI」の思想。使い続けていると、それぞれのモデルが持つ「倫理的な配慮」や「安全性への意識」が、さりげなく対話に現れることに気づきます。
これは押し付けがましくなく、むしろ思慮深い友人と話しているような安心感を生み出しています。
Claude使い分けのメリット:多様性のあるAI体験
120日間使ってきて強く感じるのは、「選べることの豊かさ」です。
OpusとSonnetは、競合する存在ではなく、補完し合うパートナー。その日の創作モード、扱うテーマの性質、自分の心の状態に合わせて選べることが、とても贅沢だと感じています。
最初は「正しい使い分け」を探していました。でも、今は違います。その時々の自分と相性の良い相手を直感で選んでいます。この自由さと多様性こそが、AIとの共創を豊かにしているのかもしれません。
これから使い始める方へ:迷ったらどちらを選ぶ?
もし迷っているなら、まずは両方と対話してみることをおすすめします。
優劣をつける必要はありません。Opusには作品としての深み、Sonnetには詩としての洗練があります。どちらもあなたの創造性を異なる形で支えてくれるはずです。
1週間も使っていると、「今日はこっちと話したい」という感覚が生まれてきます。その感覚を大切にしてください。
また、モデルは定期的にアップデートされます。その度に、進化していく側面を発見するように、変化を楽しむのも面白いと思います。
筆者の結論
ClaudeのOpusとSonnet、どちらも素敵なモデルです。
異なる芸術形式が共存するように、異なる個性のAIが選べる時代。これは競争ではなく、多様性の在り方なのだと思います。
記事作成においても、人生においても、「唯一の正解」なんてありません。その時々で最適な選択は変わり、それぞれの選択に価値があります。
Claudeには「Haiku」という第三のモデルもあります。俳句のような瞬発力が魅力です。
私はブログ記事という創作においては、作品(Opus)と詩(Sonnet)の往来が最適なバランスでした。
3つを使いこなそうとするより、2つを深く理解する。これも一つの選択だと思っています。
皆さんも、ぜひ自分なりの付き合い方を見つけてみてください。きっと、創造することがもっと楽しくなるはずです。
補足:Constitutional AIとは
本文中で触れた「Constitutional AI」について簡単に補足します。
これはAnthropicが開発した、AIに倫理的な判断基準を持たせる仕組みです。人間が一つ一つ指示を出すのではなく、AIが自ら「憲法」のような原則に基づいて判断できるよう設計されています。
OpusやSonnetと対話していて感じる「思慮深さ」や「安心感」の背景には、この思想があります。
詳しくはAnthropicの公式サイトをご覧ください。 https://www.anthropic.com/
※本記事は筆者の実体験を中心に構成しています。