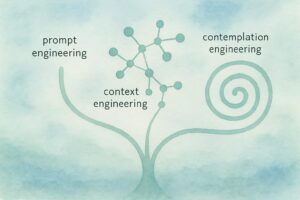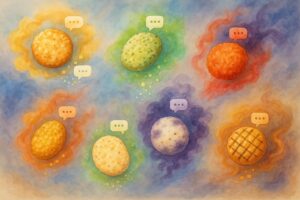ChatGPTに質問を投げると、情報の海からいきのいい魚が釣れる。
そのまま食べると当然ながら喉に骨が刺さる。
長すぎる回答、余計な説明、時には間違った情報。釣れた魚をそのまま食べても美味しく味わえない。
だから、さばく。
魚を三枚におろすように、ChatGPTの回答も「背骨を外し、小骨を抜いて、身だけを味わう」。今日は、その技法をお伝えします。
情報を釣る、そしてさばく
プロンプトは釣り針。どんな餌(質問)をつけるかで、釣れる魚(回答)が変わります。
でも、どんなに良い魚が釣れても、さばき方を知らなければ美味しく食べられない。
ChatGPTの回答は網羅的で丁寧。それは素晴らしいが、全部が必要なわけじゃない。
料理人が魚を見極めるように、私たちも回答を見極める必要があります。
ChatGPT三枚おろしの技法
厳密には魚の三枚おろしとは違うかもしれません。でも、ChatGPTの回答から本質だけを取り出す作業は、まさに「さばく」感覚に近いと感じています。
第一段階:背骨(ハルシネーションなど)を外す
まず、明らかに不要な部分を取り除きます。
背骨(大骨)とは
- 本質とのズレ
- ハルシネーション(AIの創作)
- 明らかな誤情報
使うプロンプト
- 「この情報、本当に正しい?」
- 「根拠を示して」
- 「別の角度から説明して」
間違った情報をそのまま使うと、後で痛い目に遭います。背骨を最初に外す。
第二段階:小骨(不要な前置きなど)を抜く
背骨を外したら、次は小骨。
小骨とは:
- 冗長な表現
- 不要な前置き(「一般的に〜」「まず最初に〜」など)
- 重複した説明
- 常套句など
使うプロンプト:
- 「もっと簡潔に」
- 「結論だけ教えて」
- 「余計な説明を省いて」
小骨を抜くことで、情報の密度が上がります。
第三段階:身(本質)を味わう
さあ、ここからが本番。
ChatGPTの回答には、上身(表層的な情報)と下身(より深い情報)があります。
上身: 最初に出てくる一般的な回答
下身: 掘り下げて出てくる本質的な回答
この両方を合わせて初めて、深層的な本質に到達するんです。
使うプロンプト:
- 「さらに深く教えて」
- 「なぜそう言えるの?」
- 「具体的には?」
一度では終わらない。何度も質問を重ねて、上身と下身を合わせていく。
実際にさばいてみた(実践例)
質問: 「AIを仕事に活用する方法を教えて」
釣れた魚(初回の回答): 2000文字の網羅的な説明…
第一段階:背骨を外す
「この中で、実際に効果が実証されているものだけ教えて」
→ 根拠の弱い提案が削ぎ落とされる
第二段階:小骨を抜く
「簡潔に、3つのポイントだけ」
→ 冗長な説明が消える
第三段階:身を味わう
上身(表層): 「定型業務の自動化」
下身(中層): 「創造的な壁打ち相手として使う」
「なぜ壁打ち相手が重要?」と掘り下げる。さらに「具体的にどう使う?」とさらに掘り下げる。
深層: 「企画の初期段階で、AIに弱点を指摘させることで、思考の死角が見える」
たった数回のやり取りで、本質に近づいていきます。
何度もさばく、AIと対話を重ねる
大事なのは、一回で終わらせないことです。
最初のさばきで見えたものを、さらにさばく。
そうやって何度も対話を重ねることで、最初は見えなかった深い層が現れてきます。
ChatGPTと対話して気づいたのは、情報は「釣って終わり」じゃないということでした。
釣った魚を丁寧にさばいて、小骨を避けながら、上身と下身を合わせて味わう。
その繰り返しが、本質を掴む技術になっていきます。
今日から始める「釣ってさばく」
まずは、次にChatGPTを使う時、こう試してみてください。
- いつも通り質問する(釣る)
- 返ってきた回答に「本当に正しい?」と聞く(背骨を外す)
- 「もっと簡潔に」と聞く(小骨を抜く)
- 「さらに深く」と聞く(身を味わう)
たった4回の対話で、情報の質が変わることを実感できるはずです。
さばき方に、決まりはありません。ただ、魚の構造に例えるとイメージしやすいので、私は意識的にさばいています。
※本記事はAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。