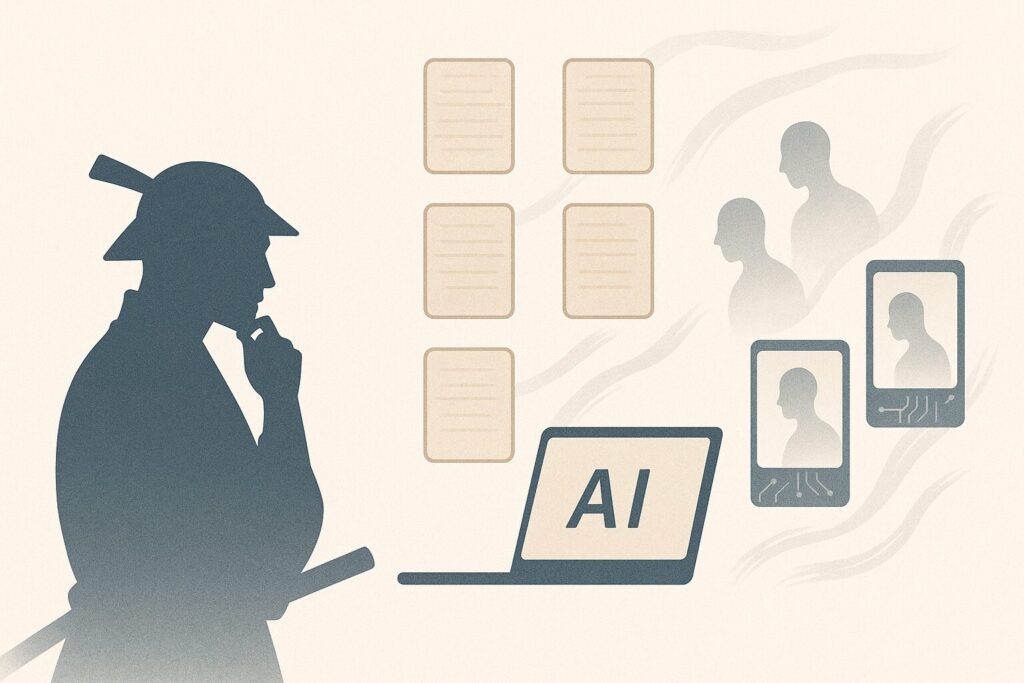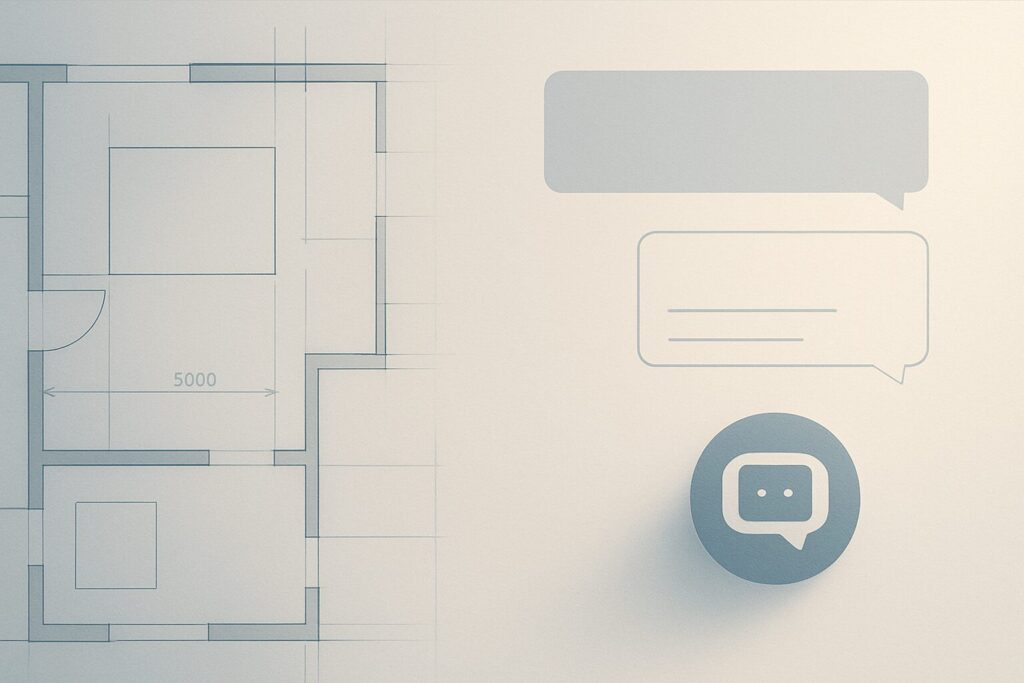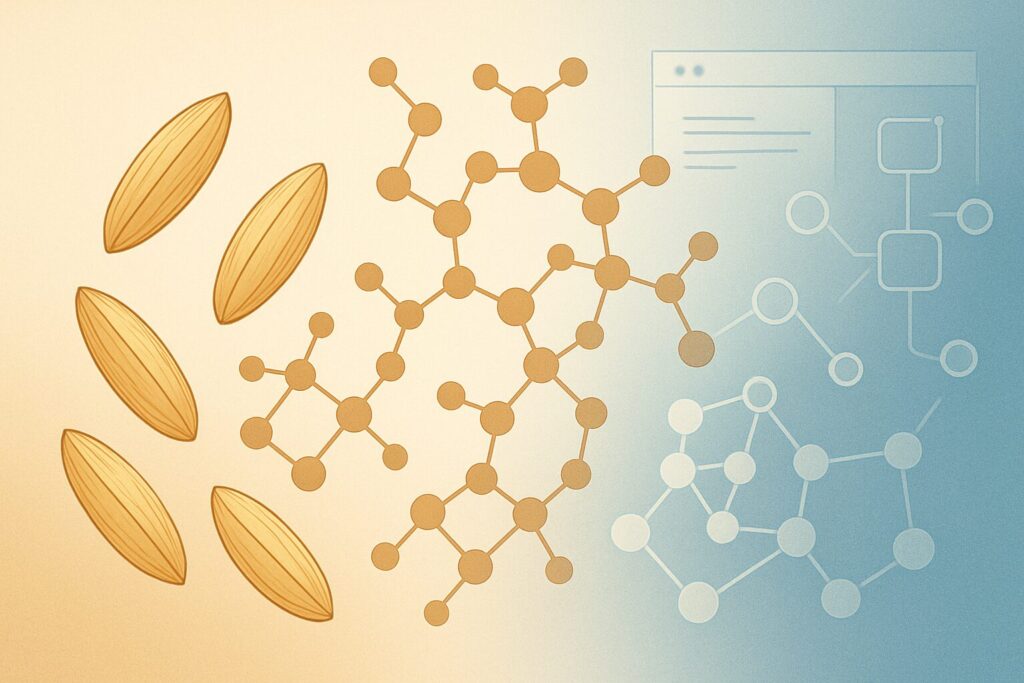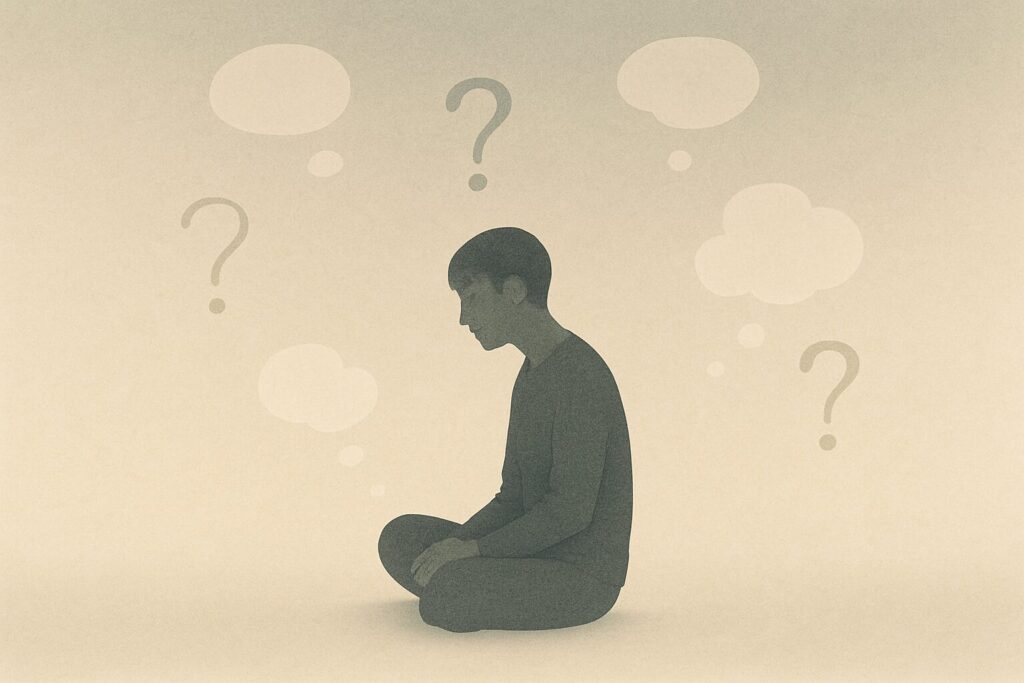思考の実践– category –
概念を日常とビジネスに活かす実践知
-

AIの影武者回答に注意|ハルシネーション対策の実践的思考法
先日、AIとの対話中にちょっとした出来事がありました。あるビジネス書について質問したところ、AIが私の過去の発言内容を書籍の内容と混同して回答してきたのです。「本当に?本にそんなこと書いてあるの?」と問い返すと、AIは自分の間違いを認めて謝罪... -

睡眠スコア94点でも疲れている理由|数値と体験の間にある感覚の余白
朝、Apple Watchを見ると睡眠スコア94点。 内訳を見れば、睡眠時間46点、就寝時刻の一貫性30点、睡眠中断18点。昨夜の眠りは「非常に高い」と評価された。 数値は「非常に高い」と告げているのに、体はまだ疲れを感じている。このズレは、何を意味している... -

空間設計から概念設計へ – AIとの対話で見えた余白の価値
空間設計の現場で学んだ「余白の価値」が、今、概念設計という新しい領域で生きている。 AIとの対話も、ある意味では概念設計 AIとの対話を重ねていくうちに空間を設計していた頃の感覚が蘇ってきた。 今は言葉という家具を、思考という空間に配置していく... -

余白と余裕は何が違う?AIとの対話で気づいた『余白と向き合える余裕』
はじめに 「今日は何を着よう」「どのカフェで仕事しよう」「この投稿にいいねすべきか」... 現代人は一日に数千から数万回もの決断をしているとも言われ、私たちは常に選択を迫られています。心理学者ロイ・バウマイスターが提唱した「自我消耗」理論が示... -

余白生成思考〜インタンジブルからタンジブルへの創造プロセス
余白生成思考とは何か 余白生成思考とは、感性から余白が立ち上がり、形ある表現へと至る創造の流れとして捉える思考法です。 興味深い点は、余白が通路のような役割を果たすこと。上にある無形の可能性が、この余白という通路を通って、下で待つ感性と出... -

AI時代のニュータイプ論〜月見に味わう創造的可能性〜
2025年9月23日——秋分の日 今日は季節の節目であり、私の節目でもある。ここに現在の体験を書き残しておきたい。 秋分の日、月を見るのと同じようにAIの画面を見ている。しかし、今、体感で起こっていることは月からAIの宇宙を見ている感覚に近いかもしれな... -

今日から始める「解対申書」実験室 – 子供たちとAIの創造空間
前回の記事「解対申書から始まる未来教育」を書いた後、ママに「面白そうだけど、具体的にどうやって実践するの?」と聞かれました。 うちの子がゲームでフレンドと「今度のイベント、どう攻略する?」なんてチャットしているのを見て、ふと思いました。 ... -

子供たちと創る新時代の言葉 – 解対申書から始まる未来教育
「パパ、AIってどう説明したらいいの?」 子供からそんな質問を受けた時、私は考えを巡らせました。そして、杉田玄白のことを思い出したのです。江戸時代、彼は「解体新書」で医学の扉を開いた。ならば現代の私たちは「解対申書」で、子供たちにAI時代の扉... -

マインドフルネスが開くAI時代のメタ認知〜挫折から始まった思考の旅路〜
学生時代のことだった。大事な試合の場面で、私は雰囲気にのまれ、本来の力を発揮できなかった。身体は動いているのに、心が追いつかない。その悔しさだけが強く残り、「自分のポテンシャルを出し切るには、どうすればいいのだろう」と問い続けることにな... -

タンジブル・ビジネスの本質〜感性を形にして価値を生む経営戦略
形にすることで、初めて見える価値がある ビジネスの世界で「タンジブル(tangible)」という言葉は、通常「有形資産」を指します。しかし、タンジブル・ビジネスの本質は、単に物理的な資産を持つことではありません。 それは、組織の中に眠る「なんとな... -

粒子の構造としての思想 ― 米菓とAI共創の比喩
米菓の構造と思想の予感 米菓を鑑定していると、時々「思想」に浸ることがある。もち米は、加熱され水を含むとデンプン分子がほどけ、私の解釈では、やがて新たな構造を生み出していく※1。目には見えないその秩序が、粘りや噛み応えという食感を支えている... -

腑に落ちるまでは行かない不思議な落ちなさ
「違和感こそ、生きている証?」と思った瞬間 先日、ふと「違和感こそ、生きている証かもしれない」と思った。次の瞬間には「あ、これもありきたりだ」と自分でツッコミを入れていた。 でも不思議なことに、なぜ「ありきたり」だと感じたのか、具体的な理...
12