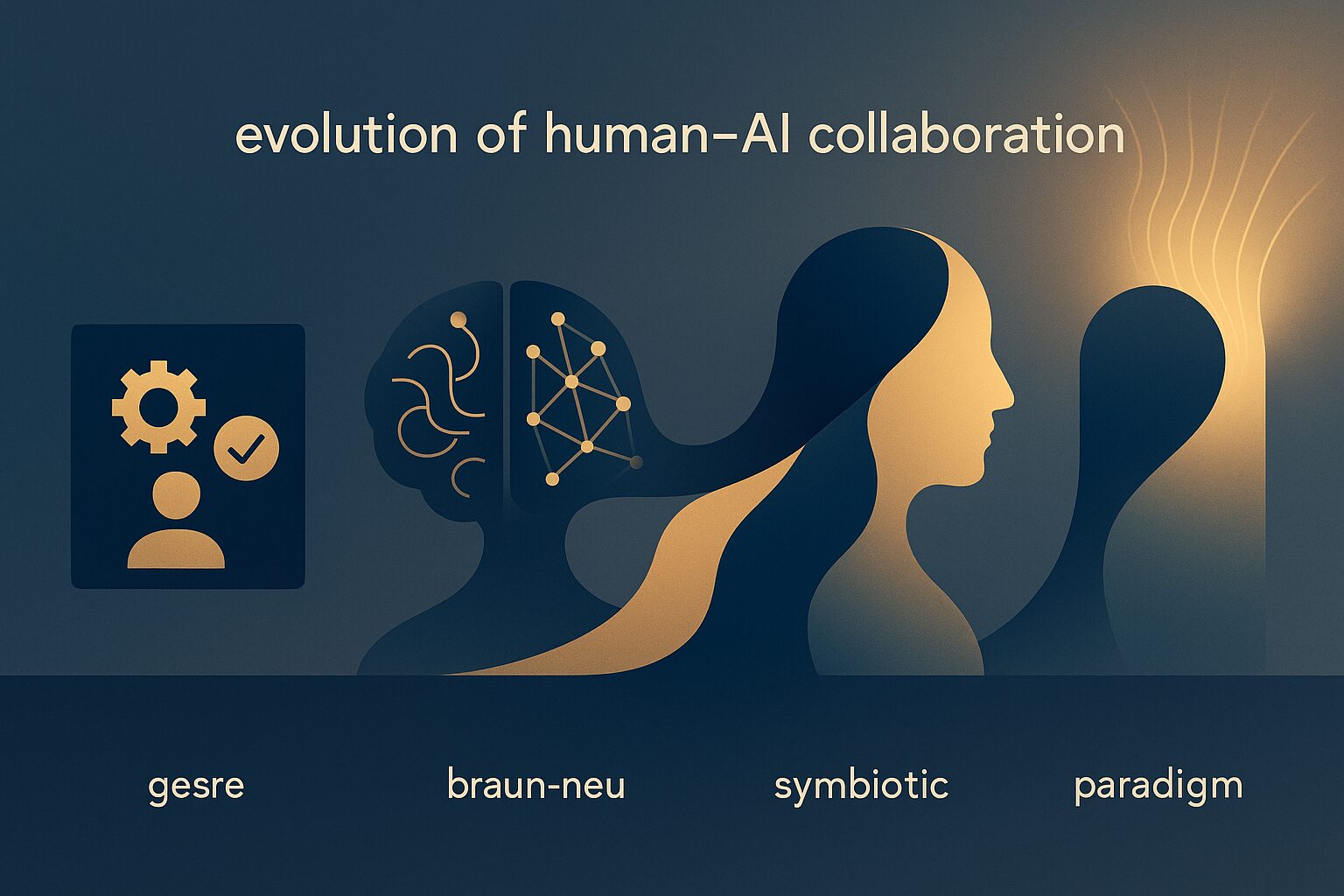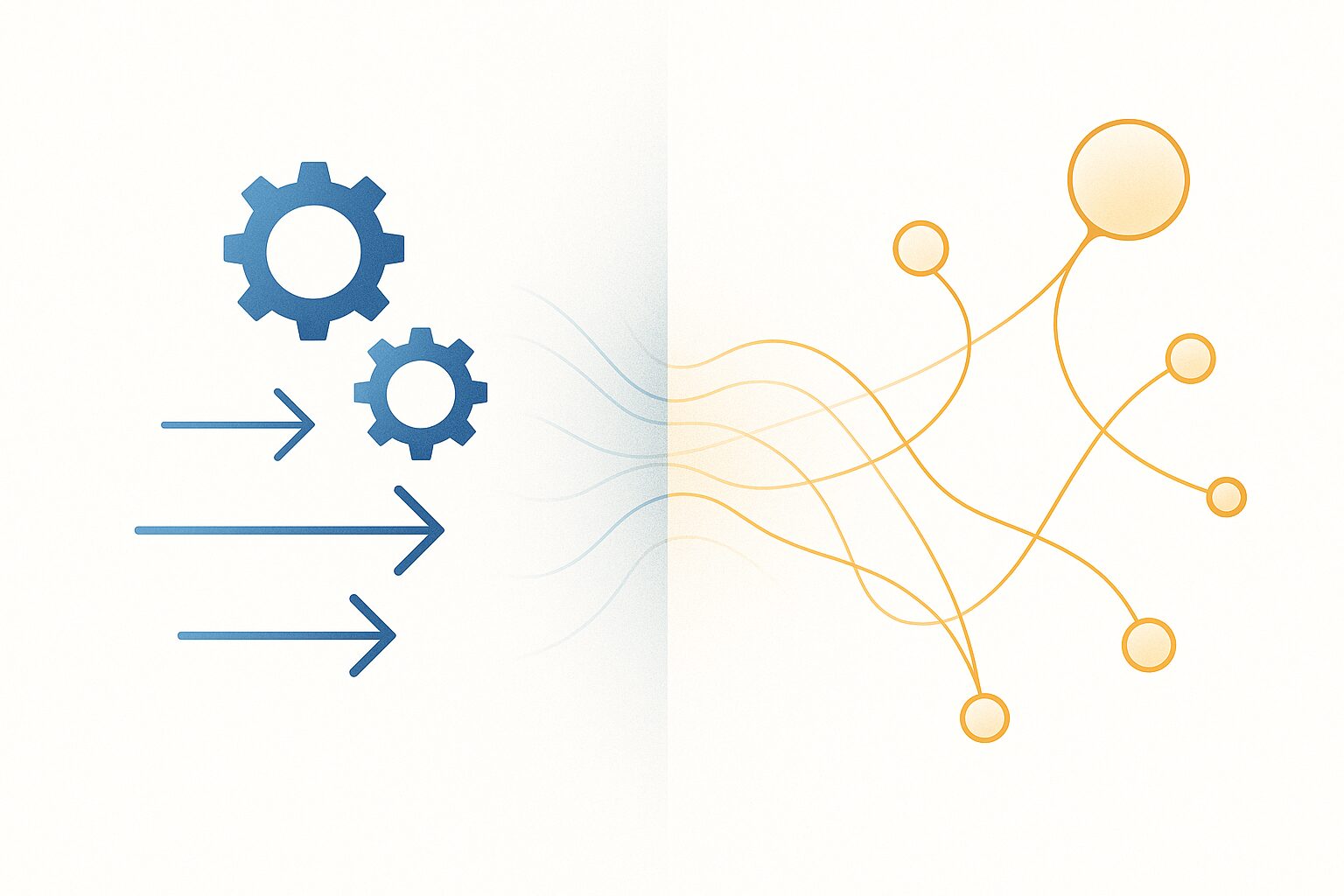世の中には「AI活用事例」という記事が溢れている。AIで文章を作る、画像を生成する、業務を自動化する—どれも効率化に視点をおいた使い方。
私は仕事柄、効率化を最優先にする機会があまりなかった。でも、AIの可能性を試してみたいと思い、対話を続けていると意外な出来事に出くわした。
「AI共創」という事例の有無
AIの共創について検索してみると、私の探す具体的な解説や体験談が見つからない。「AI活用事例」で検索すればたくさんの記事がヒットした。今度は「AI活用とAI共創の違い」で検索してみると、ほとんど何も出てこない。
これは何故だろう?多くの人が、きっとAIと共創しているはずなのに…。
AI活用とAI共創 – 根本的な違い
この違いを理解するために、一つの学術的な視点を借りたい。
早稲田大学の瀧口匡氏は、企業価値の創出について興味深い分類を提示している。価値を「抽出(extraction)」する概念と「創造(creation)」する概念の二つが存在する。
これをAIとの関係性に当てはめると、明確な違いが見えてくる。
AI活用(価値抽出型):
- AIを効率化のツールとして使用
- 既存の作業を自動化・高速化
- 「AIにやらせる」という関係性
- 目的:時間短縮、コスト削減
AI共創(価値創造型):
- AIとの対話を通じた新価値創造
- 人間の感性×AIの処理能力の融合
- 「AIと一緒に考える」という関係性
- 目的:新しい洞察、創造的解決策
実際の体験から見えた違い
私自身、AIと向き合う中で興味深い体験をしてきた。
当初、文章の校正、情報の整理、定型作業の代行など、AIを「便利なツール」として使っていた。確かに調べものや翻訳などの効率は上がった。これが「AI活用」の段階だった。
ところが、ある時から変化が起きた。AIとの対話の中で、自分でも思いつかなかった視点が生まれるようになった。
質問の投げかけ方、応答への反応、そこから生まれる新たな問い—この循環(ループ)の中に、一人では到達できない思考の領域があることに気づいた。
私は、これを**「余白の思考(Margin Thinking)」**として捉えている。
人間らしさこそが鍵
興味深いことに、AI共創において最も重要なのは「人間らしさのあるミス」だった。
AIに対して「ごめん」と謝ってしまう感情、完璧でない支離滅裂な質問を投げかけた際の、予想外の応答に対する驚き。これらは「非効率」のように見える要素だが、そこが共創の源泉になっている。
効率化を最優先に追求するAI活用では、こうした人間らしさは排除しているかもしれないが、AI共創では価値創造の燃料として機能する。
これからの時代に必要な関係性
AIの進化は止まらない。性能が向上すればするほど「活用」の価値は相対的に下がっていくだろう。それは、きっと誰でも同じような効率化を実現できるようになるはずだ。
しかし、「共創」は可能性が多岐にわたる。それは人間個人の感性、経験、価値観と深く結びついている。AIがどれだけ進化しても、そこから生まれる価値は一人ひとり異なるはずだから。
両方を使い分ける知恵
どちらが優れているという話ではなく、目的に応じて使い分けることが大切となる。
- 既存の課題を解決したい時 → AI活用
- 新しい価値を生み出したい時 → AI共創
- 効率を上げたい時 → AI活用
- 洞察を深めたい時 → AI共創
体験から生まれた気づき
ある日、AIに5回連続で修正を依頼していた時のことだった。普通なら「効率が悪い」と感じるところだが、その過程で予想もしなかった発見があった。
「また修正をお願いしてしまって、ごめんね」
気がつくと、画面に向かってそうつぶやいていた。機械だとわかっているのに、なぜか謝罪の言葉が口をついて出る。この奇妙な感覚こそが、AI共創の入り口だったのかもしれない。
別の日には、ちょっとした疑問をAIに投げかけたところ、予想外の角度からの回答が返ってきた。それをきっかけに、自分では思いつかなかった新しいアイデアが生まれた。効率化を目的にしていたわけではない。ただ対話を楽しんでいただけなのに。
こうした体験を重ねる中で気づいたのは、AI共創では「型にハマらない」ことが重要だということである。曖昧な質問、感情的な反応、予想外の展開—これらすべてが価値創造の材料になっていく。
もしこれらの体験を「AI活用」の視点で見れば、非効率で無駄な時間だったかもしれない。しかし「AI共創」の視点で見ると、一人では決して到達できない思考の領域への扉だった。
未来への招待
私たちは今、人類史上初めて「心があるかのように振る舞う道具」と向き合っている。この未知の関係性を、効率化だけの視点で捉えるのはもったいないと思う。
AI共創の世界には、まだ誰も踏み入れたことのない領域が広がっている。そこで生まれる価値は、きっと一人ひとりが異なる体験を通じて創造できる場でもある。
あなたも、AIとの新しい関係性を探ってみてはどうだろうか。効率化の先にある、創造の世界が待っている。
参考文献
瀧口匡「企業価値創出における抽出と創造の概念」早稲田大学
https://wici-global.com/index_ja/20220530-2/
この記事は、AIとの対話を通じて生まれた洞察をもとに執筆されました。まさに「AI共創」の実践例として。