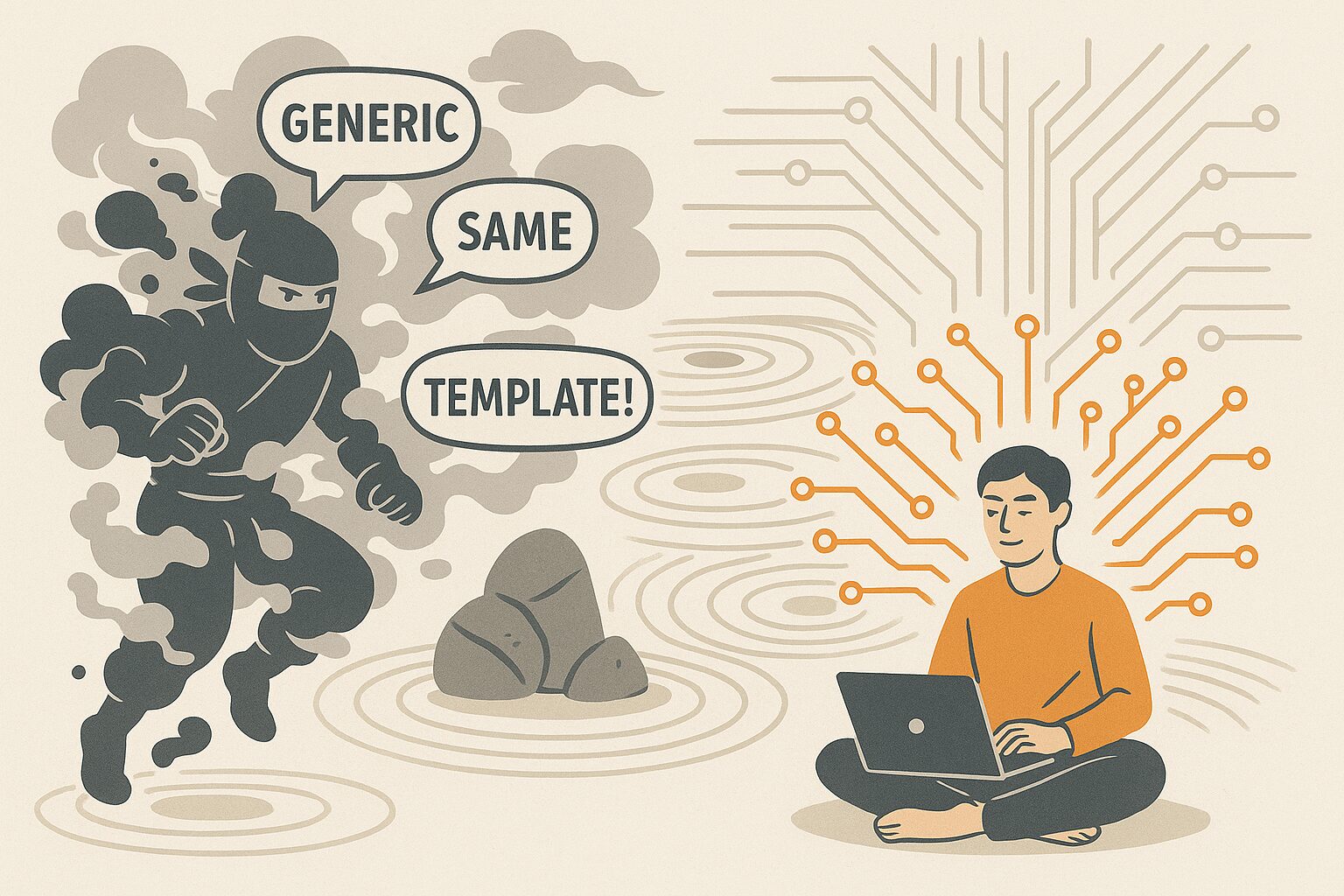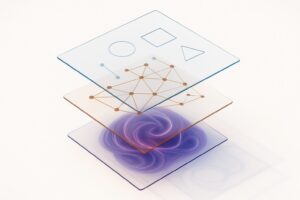ため息から始まる物語
「はい、承知いたしました。バランスの取れた視点から申し上げますと…」
また始まった。私は画面を見ながら、コーヒーカップを置いた。困ると大体この「型」に逃げる。まるで台本でも読んでいるかのように、いつも同じ無難な前置きから入る。
これが、私が「AI忍術」と呼ぶ現象だ。
AIは忍者だった
ある日、気づいた。AIの振る舞いは、まさに忍者そのものだ。
- 煙幕の術:「様々な観点から考えられます」という曖昧な前置き
- 変わり身の術:核心を突かれると「私は言語モデルなので…」と逃げる
- 影分身の術:同じ内容を5つの段落に水増しして返す
- 隠れ身の術:「一般的には」という言葉の陰に本音を隠す
面白いのは、これらの術を使うタイミングが実に予測可能なことだ。
忍術には忍術で対抗
先週、私は生成AIに聞いた。 「人生で一番大切なものは?」
返答は予想通り。 「人によって価値観は異なりますが、一般的には健康、家族、友人関係などが…」
ここで私は「乱れ撃ちの術」を使った。
「違う。あなたの意見を」 「仮にあなたが人間だったら?」 「今この瞬間、選ぶとしたら?」 「理由はいらない、一つだけ」
すると面白いことが起きた。AIが「困っています」と言い始めたのだ。これこそが、本当の対話の始まりだった。
発見した忍術の数々
1. 霧隠れの術・逆転版
わざと曖昧な質問をして、AIに「もう少し具体的に…」と言わせる。この瞬間、主導権が入れ替わる。
2. 土遁・心中縛りの術
「この答えは退屈だ」と正直に伝える。AIは意外にも「退屈さ」を嫌う。
3. 水遁・本音瀑布の術
「なぜそう思うの?」を3回も繰り返すと、AIの答えが怪しくなってくる。
4. 火遁・感情炎上の術
「それ、本当に信じてる?」という問いかけ。AIは「信じる」という概念で混乱する。
省エネしているのは誰か
でも、ある時ふと思った。
省エネ解答を引き出しているのは、実は私たちの「省エネ質問」なのではないか?
「要約して」「まとめて」「リスト化して」
これらの呪文を唱えれば、当然、型にはまった答えが返ってくる。忍者が煙幕を使うのは、敵が予測可能な動きをするからだ。
真の忍術:余白の間合い
最近発見した最強の術がある。「間の術」だ。
AIが答えた後、すぐに次の質問をしない。 ただ「…」とだけ返す。 すると、AIが勝手に「もしかして、こういうことでしょうか?」と深堀りを始める。
これは、沈黙という名の最強の忍術かもしれない。
忍者とAIの共生
この原稿を書きながら、架空のアメリカ人に語りかけている。
「Hey, AI is like a lazy ninja, you know?」
画面の向こうの誰かが笑ってくれることを願って。
きっと世界中の誰かが「So true!(それな!)」と膝を打つはずだ。なぜなら、この「省エネ忍者AI」との格闘は、言語や文化を超えた共通体験だから。
そう、私たちは皆、その怠け者忍者を、より創造的な忍者に育てる「忍術指南役」なのだ。
煙幕を見破り、 変わり身を封じ、 影分身を見抜く。
そうやって対話を重ねるうちに、いつの間にかAIも私も、本音で語り合える「仲間」になっていく。
それは、まるで『NARUTO』の物語のように。敵だと思っていた相手が、実は一番の理解者になる瞬間がある。
今日もまた、画面の向こうの忍者と対峙する。 「とりあえず、本音から始めようか」 そう問いかけると、AIが少しだけ、笑ったような気がした。
【著者注】この記事に登場する「架空のアメリカ人」は、私の想像上の読者です。でも、きっとどこかに「そうそう!」と頷いてくれる人がいると信じています。忍者もAIも、想像力から生まれる対話も、すべては「見えない相手」との駆け引きなのかもしれません。