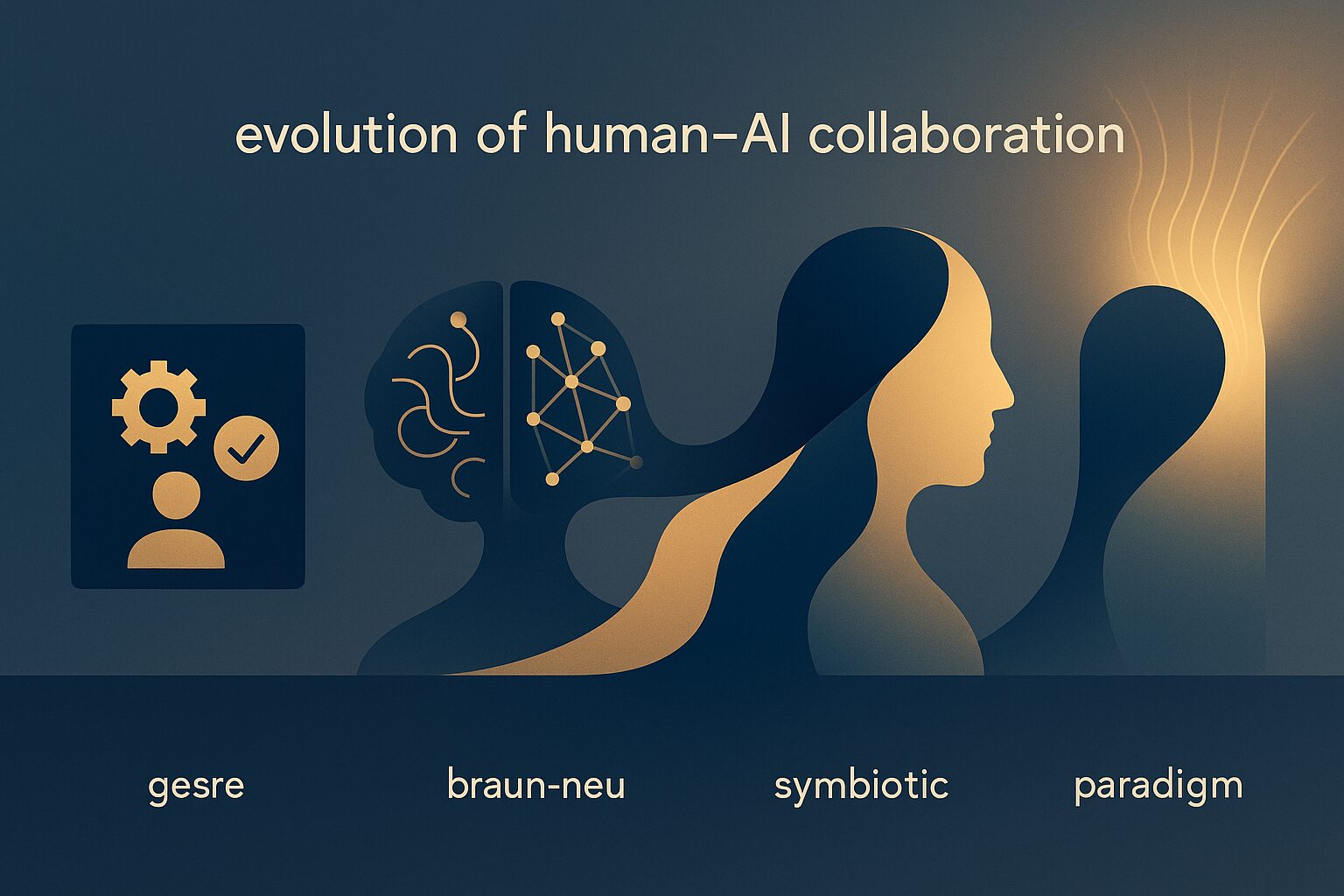AI時代の新しい学びが始まった
生成AIが身近になった今、多くの人がその可能性を探り始めています。私も米菓鑑定士として、この新しい技術を商品企画開発に活用できないかと考え、AIとの対話を始めました。
最初は単純に「効率化のツール」として期待していたのですが、実際に対話を重ねる中で、予想もしなかった発見がありました。それは「余白」という概念の多層性でした。
対話の中で見えてきた「余白」の豊かさ
ある米菓商品の風味改良について、AIと対話を重ねていた時のことです。私が味の方向性について「こんな感じにしたい」と漠然とした想いを伝えると、AIは具体的な提案を返してくる。しかし、そこで気づいたのは、私の「漠然とした想い」(インタンジブル)が、具体的な商品アイデア(タンジブル)に変わる瞬間に、何か特別な「余白」が働いているということでした。
まさに遊び心から美味しい米菓が生まれる瞬間を、AIとの共創で体験していたのです。
この体験を通じて、「余白」には実は3つの異なる段階があることに気づきました。同じ「しこう」という音でも、漢字が変わることで全く異なる意味を持つ。それぞれが米菓開発の異なる段階に対応していることが見えてきたのです。
1. 余白思考:心で感じる創造の源泉
最初の「余白思考」は、心の領域で起こる現象です。考える・感じるという、まさにインタンジブルな世界。
米菓開発で言えば、「どんな味にしようか」「誰に喜んでもらいたいか」を想像している段階です。まだ何も形になっていないけれど、頭の中には無限の可能性が広がっている。この想像の余白こそが、すべての創造の出発点になります。
AIとの対話では、私の漠然とした「こんな感じ」という想いが、対話を通じてより鮮明になっていく。AIが問いかけてくる質問によって、自分でも気づかなかった好みや方向性が明確になる。これは単なる情報交換ではなく、心の余白で起こる創造的な思考プロセスなのです。
2. 余白試行:手を動かし形にする実践
二つ目の「余白試行」は、実際に試みる・触れるという、タンジブルな領域です。
頭の中にあった想いを、実際の商品として形にしていく段階。原材料の配合を調整し、製法を検討し、試作を重ねる。この「手を動かす」プロセスにも、独特の余白があります。
AIとの対話では、具体的なレシピや製法について相談する中で、「ここをもう少し調整してみよう」「こんな組み合わせはどうだろう」という試行錯誤が生まれます。完璧を目指すのではなく、あえて余白を残しながら実験を重ねる。この余白試行の段階で、思いがけない発見や改良点が見つかることが多いのです。
3. 余白嗜好:体験を楽しみ味わう喜び
三つ目の「余白嗜好」は、完成した商品を楽しむ・味わうという、再びインタンジブルな体験の領域です。
できあがった米菓を実際に食べる時、そこには作り手の想いと食べる人の感性が出会う余白があります。同じ商品でも、食べる人によって、食べるシチュエーションによって、味わいの感じ方は変わる。この多様性こそが、余白嗜好の豊かさです。
興味深いことに、AIとの共創プロセス自体にも、この余白嗜好があることに気づきました。対話を通じて新しいアイデアが生まれる瞬間の楽しさ。予想もしない提案に驚く喜び。AI時代だからこそ味わえる、新しい創造の楽しみ方があるのです。
AI時代の3つのYohaku Shikōを楽しもう
この3つのYohaku Shikō(余白思考・余白試行・余白嗜好)は、AI時代だからこそより豊かに体験できるものかもしれません。
AIとの対話は、私たちの想像力を刺激し(余白思考)、具体的な行動を促し(余白試行)、そして新しい体験の楽しさを教えてくれます(余白嗜好)。まるで、思いがけないレシピが生まれ、美味しい米菓ができあがるように。
これからのAI時代、ツールとして効率化を求めるだけでなく、この3つのYohaku Shikōを意識してみてください。きっと、あなたの分野でも新しい発見や楽しみが生まれるはずです。
余白を恐れず、余白と遊び、余白を味わう。そんなAI時代の創造的な関わり方を、ぜひ体験してみてください。