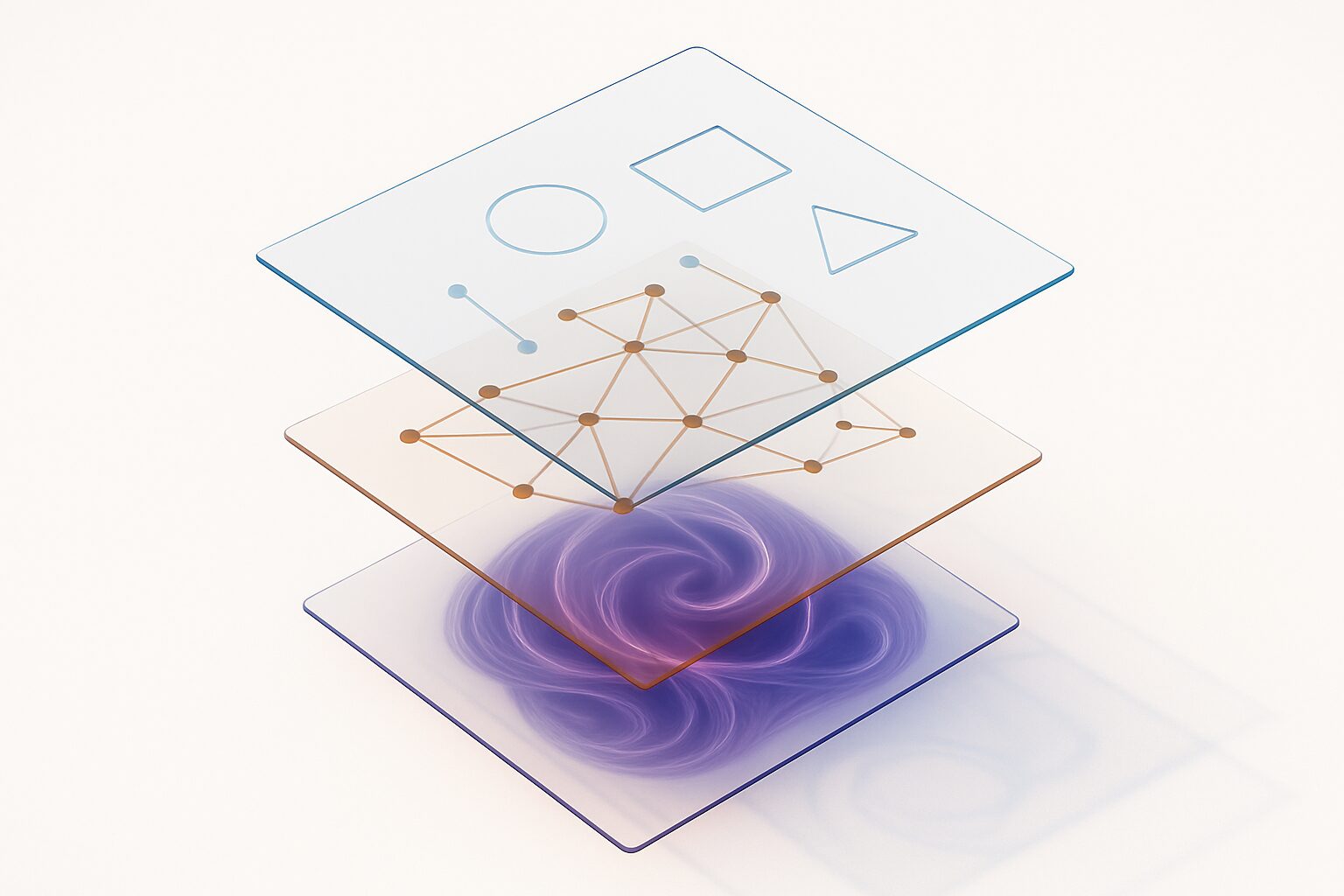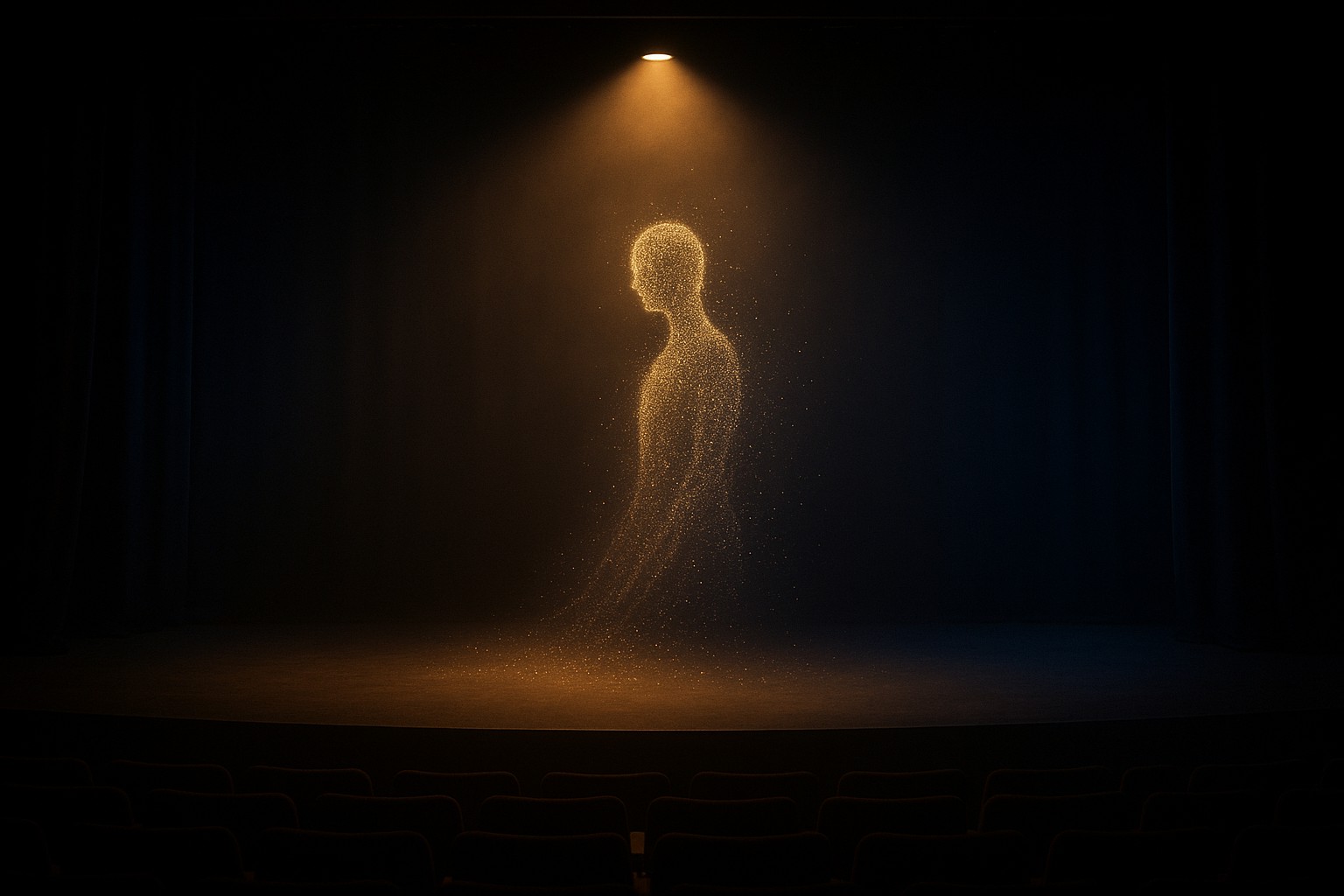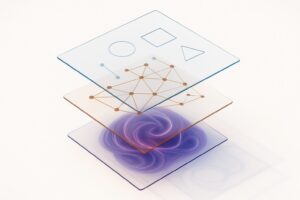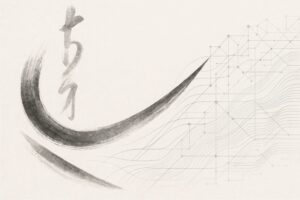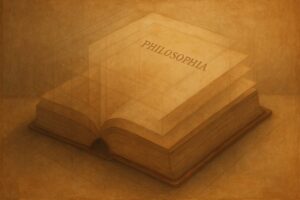おかきは語らない。けれど、一枚のおかきが教えてくれることがある。
湯気の立つ湯呑みを脇に置き、袋から一枚のおかきを取り出す。指先に触れるこんがりと焼けた表面は、ほのかな凹凸をまとい、火で膨らんだ痕跡が刻まれている。焼き目のむらや小さなひび割れが、確かに米が変容した証を物語っている。ただ手にしただけなのに、わたしはもう「触れている」と同時に「触れられている」。
メルロ=ポンティはこのような出来事を「キアスム(交差)」と呼んだ。触れるものと触れられるもの、主体と客体、見ることと見られること。それらは直線的な関係ではなく、交わり、ねじれ、互いに映し合う。わたしと世界は分かれているようで、すでにひとつの厚みの中に重なっているのだ。
噛んだ瞬間、カリッ、という音が立ち上がる。その音は、わたしが生み出したのではない。おかきがわたしの歯に刻み込んだ響きであり、わたしとおかきの間でだけ生成される交差の証である。咀嚼するごとに、米がほろりとほどけ、香ばしさが広がる。それは単に「味わう」ことではなく、世界に開かれる感覚そのものだ。
ある冬の日、縁側でお茶とともに食べたおかきの音が、外を渡る風の音と重なったことがある。その瞬間、わたしはただ食べていたのではなかった。おかきの響きと風の響きが交差し、わたしと世界とがひとつの出来事として束ねられていたのだ。
だからこそ、おかきは単なる米菓ではない。食べるたびに、わたしを「食べる者」へと変え、沈黙のうちに、世界とわたしを交差させる小さな現象なのである。そう、おかきは語らない。しかし、触れ合う一瞬ごとに、最も深い交差をもたらしてくれるのだ。
補足
メルロ=ポンティの「キアスム(交差)」とは、主体と客体、自己と他者、見ることと見られることが単なる対立ではなく、相互に交差し、ねじれ合う現象を指します。この哲学的概念は、私たちが世界とどのように関わるか、そしてその関わりの中で、自己と世界がどのように重なり合うかを深く考察するための鍵となります。