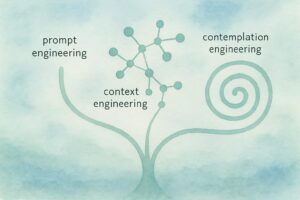7種類のせんべいから学ぶAIプロンプトの使い分け
目の前に7種類のせんべいを並べた。素焼き、醤油、サラダ、山椒、七味、わさび、カレー。同じ「せんべい」でも、風味が違うだけで全くの別の味合いである。
30年間米菓と向き合ってきた私がAIと向き合う中で気づいた。これはAIへのプロンプト(質問の仕方)も同じではないのかと。
ChatGPT、Claude、Gemini。みんな同じAIを使っているのに、なぜ成果に差が出るのか。今回は「風味」という視点から、AIプロンプトの効果的な使い方と使い分けを実証実験してみた。
基本のAIプロンプト – 王道風味の使い方
素焼き風味:無風味という基準点
まず素焼きせんべいを口にする。米の味、そのまま。これがAIプロンプトでいう「標準的な質問」パターン。
プロンプト例: 「中小企業の戦略を教えてください」
AIの回答: ・差別化を図りましょう ・ニッチ市場を狙いましょう ・顧客との関係を大切にしましょう
シンプルで基本的な答えは、出発点として重要な基準になる。ここから、どう風味を加えていくかが腕の見せ所。
醤油風味:甘辛バランスの効いたプロンプト
醤油せんべいの甘辛さが口に広がる。これは「本音と建前のバランス」を引き出すプロンプトといえるかもしれない。
プロンプト例: 「正直なところ、リソースが限られた中小企業ってどう戦えばいい?現実的な話を聞きたい」
AIの回答: 「理想を言えば全方位戦略ですが、現実的には一点突破です。まず既存顧客の維持に全力を注ぎ、そこから横展開するのが堅実です。新規開拓は既存顧客の紹介から始めましょう」
温度感のある、使える答えが返ってきた。
サラダ風味:さっぱり明快なプロンプト術
塩味のきいたサラダせんべい。シンプルで後味さっぱり。忙しい経営者向けのプロンプトになりそうだ。
プロンプト例: 「中小企業が今すぐやるべきこと、3つだけ教えて。説明は各30文字以内で」
AIの回答:
- 既存顧客に追加提案(売上即効性あり)
- 固定費の見直し(特に使ってないサブスク)
- 社長の時間配分見直し(営業7割へ)
回答に無駄がない。これならいつからでも実行できそう。
個性的なAIプロンプト – 嗜好性風味の使い分け
山椒風味:ピリリと刺激的な質問で本質を突く
山椒の痺れる刺激。普通は聞きにくいことを聞くプロンプトになるだろう。
プロンプト例: 「競合を出し抜く、ちょっとグレーだけど合法な方法ない?」
AIの回答: 「競合の求人情報から戦略を読む、離職者から情報収集、競合の顧客の不満をSNSで拾う…これらは情報収集の基本ですが、多くの企業はやっていません」
普段は出てこない、でも確かに効果的な答えかもしれない。
七味風味:複雑な要素を同時に扱うプロンプト
七種の香辛料が織りなす複雑さ。実は七味は、製造元によって配合が全く異なる。唐辛子を強めにするか、山椒を効かせるか、胡麻の香ばしさを前面に出すか。
プロンプト例: 「新規事業について、収益性、リスク、必要リソース、撤退基準まで含めて総合的に教えて」
七味と同じように、複数の要素をどうブレンドするかはあなた次第。私の七味とあなたの七味は、きっと違う配合になるはず。
わさび風味:ツーンとくる辛辣なフィードバック
わさびの鼻に抜ける刺激。耳が痛い真実を聞きたいときのプロンプト。
プロンプト例: 「うちの事業モデル、ぶっちゃけ5年後も通用する?ダメなら理由も容赦なく教えて」
AIの回答: 「申し訳ないが、現状のままでは厳しい。理由は3つ。①その価格帯はAIに代替される ②差別化要素が曖昧 ③顧客の高齢化に対応できていない」
耳が痛い。でも、これが聞きたかった。
カレー風味:異分野ミックスで発想を飛躍させる
カレー粉という風味の解釈は実に興味深い。軽く振りかけるスパイスとして使うか、じっくり煮込んでベースの味を変えるか。インド風、欧風、日本風…同じ「カレー」でも全く別物に。
プロンプト例: 「うちは町の印刷屋だけど、もしこれがシリコンバレーのスタートアップだったら、どんなビジネスモデルにする?」
カレーせんべいも、メーカーによってスパイスの効かせ方が違う。あなたのカレー風味は、どんな異文化を混ぜ込むだろうか。
風味ブレンドでオリジナルの答えを作る
実験1:醤油×わさび(本音の中の本音)
「正直どう思う?(醤油)でも綺麗事は一切いらない(わさび)」
このブレンドプロンプトで、AIから驚くほど率直な答えが返ってくる。
実験2:サラダ×カレー(シンプル×異分野)
「簡潔に3つ(サラダ)、でも飲食業界以外の成功例で(カレー)」
簡潔さと意外性を両立させる、興味深いプロンプト技法といえるだろう。
あなたに最適な風味を見つける方法
風味診断:あなたはどのタイプ?
時間がない経営者 → サラダ風味(要点のみ)
じっくり検討派 → 七味風味(多角的分析)
現状打破したい → カレー風味(異分野発想)
本音が聞きたい → わさび風味(辛辣な真実)
段階的な風味マスター法
- 初級:素焼きで基準を知る
まず標準的な質問で、AIの基本回答を確認 - 中級:王道3種を使い分ける
醤油(バランス)、サラダ(簡潔)を場面で使い分け - 上級:嗜好性風味で差別化
山椒、わさびなど、他者が使わない風味で独自の答えを - 達人:オリジナルブレンド
複数風味の組み合わせで、唯一無二の回答を引き出す
AIプロンプトに風味を加える時代へ
30年間、米菓の風味を見極めてきた。同じ米、同じ製法でも風味の違いで異なる商品を生み出す。
七味せんべいを例にとれば、浅草の老舗と京都の老舗では配合が違う。どちらが正解ということはなく、それぞれの店が、それぞれの客に合わせて調合を重ねた最適解。
AIプロンプトも同じではないのか。だいたい、みんな同じAIを使っている。でも、風味を加える人と加えない人では得られる答えが違ってくる。
素焼きのような基本的な質問も大切な基準点。そこから自分なりの風味を見つけていく企業。七味のように独自の配合を編み出す企業。それぞれの道があっていいのではと思う。
あなたは、何風味でAIに問いかけますか?
まずは、いつもの質問に少し風味を加えてみてほしい。きっと、違う景色が見えてくるでしょう。
※本記事はAIとの対話を基に、筆者独自の視点で再構成したものです。