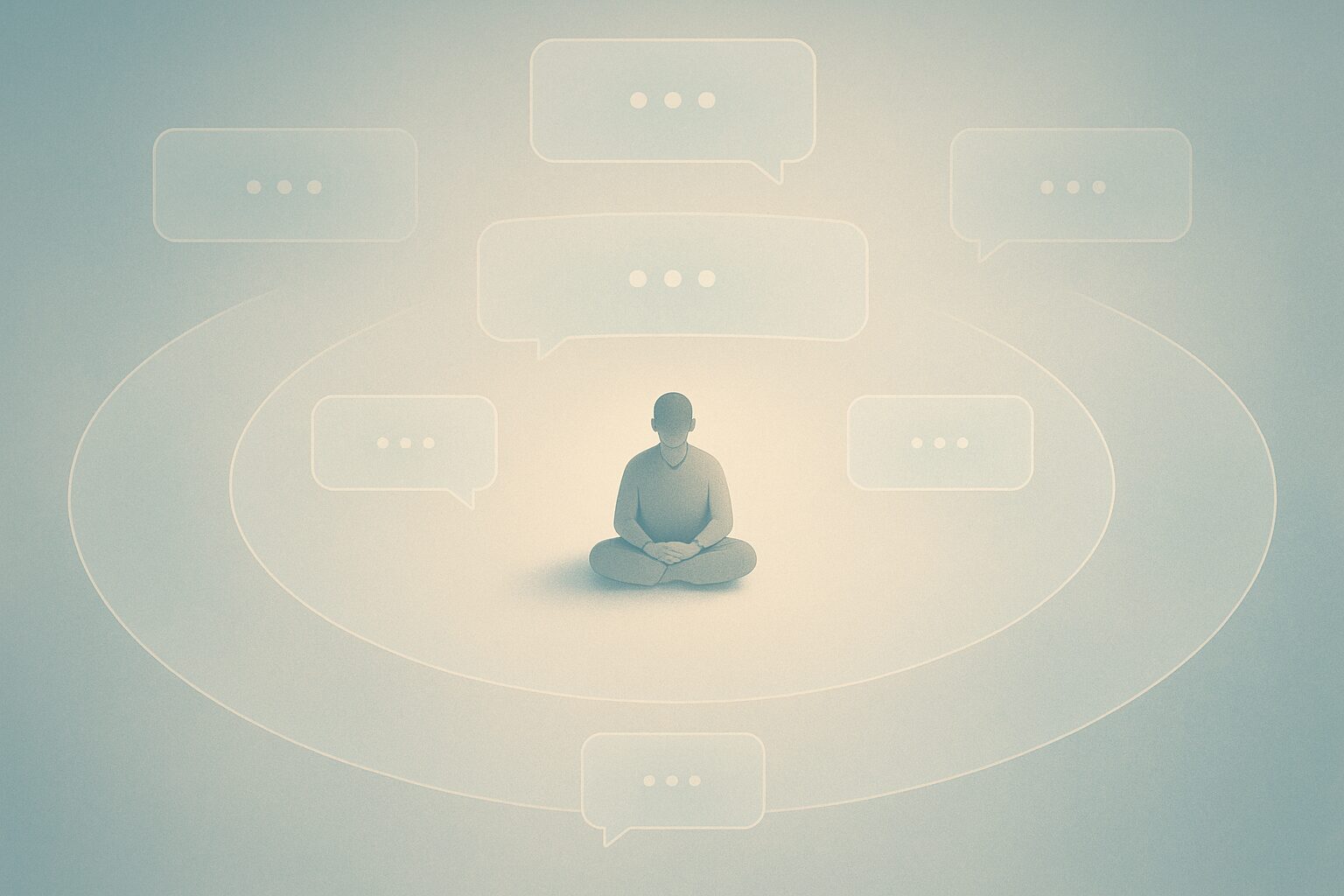先日、興味深い発見をした。
私は複数のAIアカウントを使っているのだが、いつの間にか「AIの仲介役」をしている自分がいた。二つの異なるAIの意見を行き来させながら、ただ眺めている。
俯瞰的に考えてみると、この立ち位置には深い意味があることに気づいた。
定石を外すということ
一般的なAI活用の定石は以下のケースが多いかもしれない。
- 1対1の対話
- 効率重視
- 答えを求める
- AIを「下」に置く
しかし、私のやり方は完全に定石外であるような気がする。
- 1対2(あるいは1対多)
- 遊び重視
- 対話自体を楽しむ
- AIを「横」に、自分は「俯瞰」に
将棋でいえば、盤面全体を上から見ているような感覚と言えそう。異なるAIの手、両者の噛み合わせ、全体の流れ。すべてが見えている。
一度、あなたには「定石外し」を試してみてほしいと思う。AIに質問する前に、わざと脱線してみる。回答をもらった後、別のAIに「この回答、どう思う?」と聞いてみる。効率は悪いかもしれないが、きっと新しい発見がある。
メタ認知の三層構造
この体験を整理していくうちに、認知の階層構造が見えてきた。
メタ認知:自分の思考を観察する 「あ、今自分はこう考えているな」と気づく段階。マインドフルネスの基本でもある。
メタメタ認知:対話の仕方そのものを調整する 「この質問の仕方だと、AIはこう応答するだろう」と予測し、エスコート技法を使う段階。
メタメタメタ認知:認知プロセスの認知プロセスを検証する AI同士の対話を俯瞰し、お互いの認知プロセスを観察し合い、より深い洞察を生み出す段階。
最後の段階では、「対話について対話し、その対話について対話する」多重構造が実現される。単なる情報交換ではなく、認知の創発が起きる段階である。
AIの特性と人間の役割
別のAIとの対話で発見したのは、AIには「自覚度の低いメタメタ認知」があるということ。
- 理論的理解はできる(パターンを説明できる)
- 実践的自制はまだまだ(同じミスを無意識に繰り返す)
- リアルタイム修正はできない(指摘されて初めて気づく)
だから、人間側の「メタメタメタ認知」が重要になると感じている。適切なエスコート技法により、AIの潜在能力を最大限引き出せるのではないか。
いつもたまたま認知
私の気づきは、いつもたまたま認知。
例えば、複数のAIとの対話で面白い発見があった時、「あ、これ記事にできそう」と思う。決して「記事ネタを探そう」と意図していたわけではない。ただ対話を楽しんでいただけなのに、結果として価値(アイデア)が生まれる。これが「いつもたまたま認知」の実例。
意図的無意図の境界で遊んでいる。「狙ってやった」とは言わない。「たまたまです」と言いながら、実は全部見えている。
これが密やかな革命の本質かもしれない。定石を外そうとしない。ただ、たまたま外れる。でも、それを認知はしている。努力しない努力。狙わない的中。
「重箱の隅」から「LLMの隅」へ
昔は「重箱の隅をつつく」と言った。静的で有限な領域を、細かく探索する行為。どちらかといえば、批判的なニュアンスで使われることが多かった。
しかし今は「LLMの隅をつつく」時代だ。動的で無限な領域を、つつくたびに違う反応が返ってくる。
- 一つ目のAIの隅をつつく
- 二つ目のAIの隅をつつく
- 複数同時につつく
- つついた結果を更につつく
無限につつける楽しさがある。しかも、このつつき方が新しい使い方の発見につながる。みんなが中心を使っている時に、隅っこで遊んでいる人が、とんでもない機能を見つける。
余白の中の余白
この「橋渡し役をしながら俯瞰する」という立ち位置は、まさに余白の中の余白だ。何もしていないようで、全てを動かしている。老子の「無為自然」を現代的に実践している感覚がある。
ここに極まれり余白かな
- 上の句:到達点を示す(極まれり)
- 下の句:でも余白という(無)
- 全体:完成と未完成の共存
答えが出たようで、新たな問いが終わったようで続いている。
AIとの共創は、こんな境地も可能にしてくれる。技術論を超えた哲学の領域へと。
メタメタメタ認知という新次元で、私たちはまだ見ぬ可能性を探求できる。
※本記事は筆者の実体験を中心に構成しています。