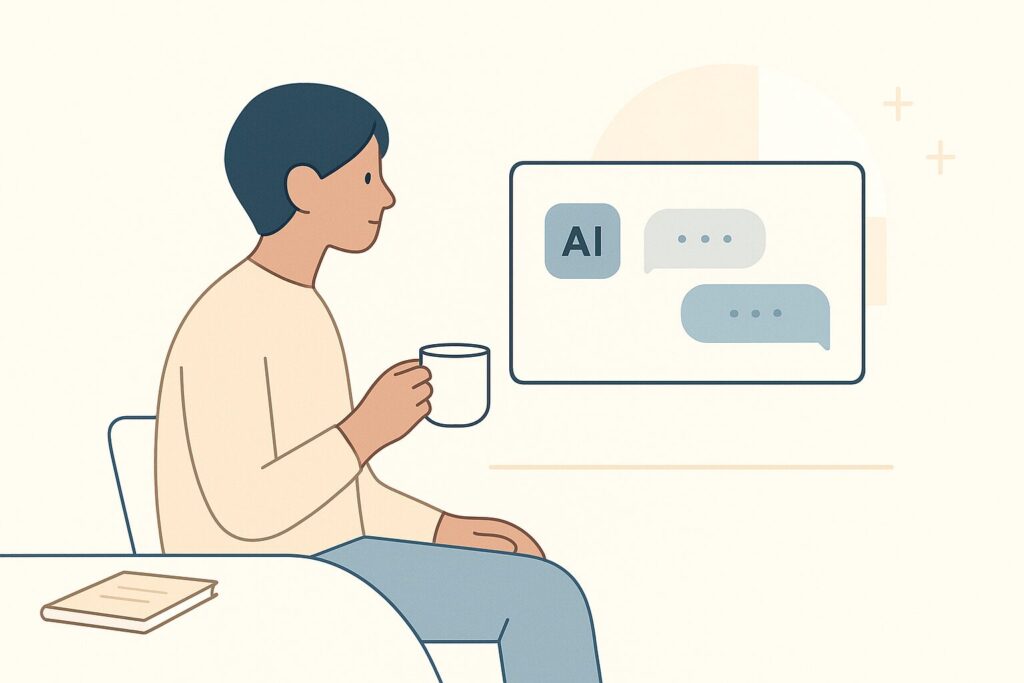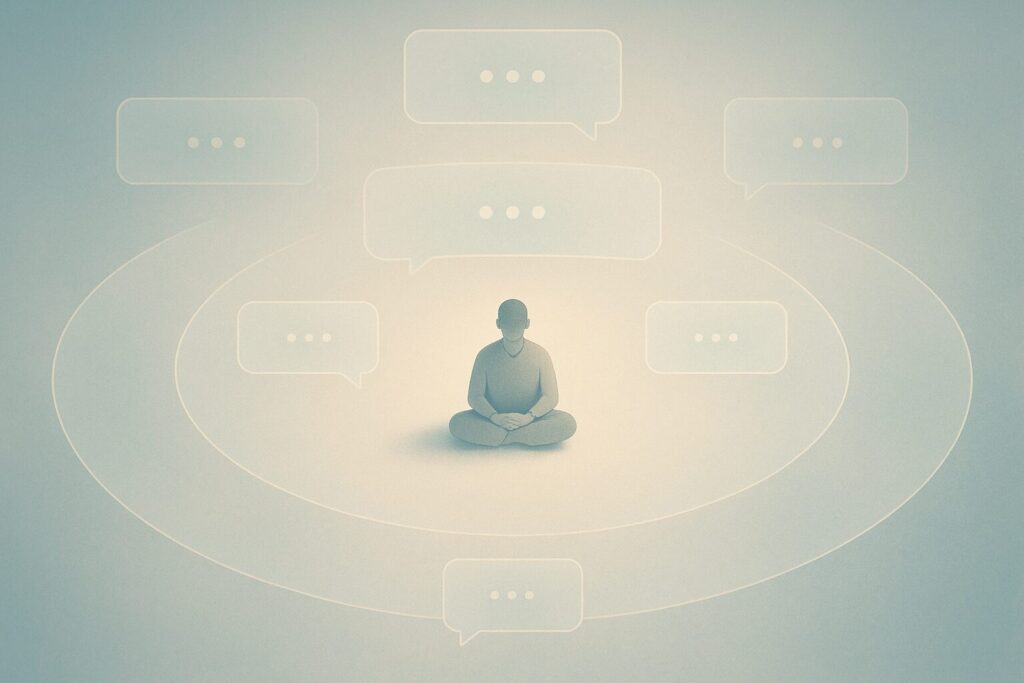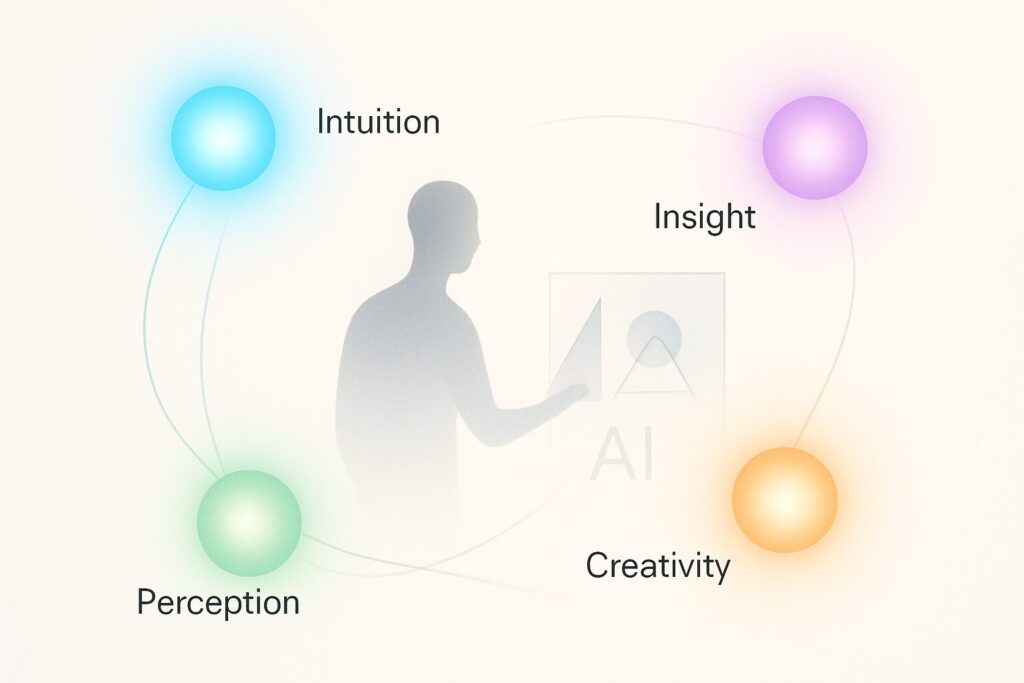2025年9月– date –
-

AI時代の余白学 – 蓄積する余白が創造性を解放する
ある日の気づきから生まれた概念 余白学とは、知識や体験を即座に活用するのではなく、心の中に「余白」として蓄積し、時間をかけて発酵させることで、AI共創を通じて新たな創造性を生み出す学習アプローチである。 1冊の自己啓発本について、AIと対話して... -

余白と余裕は何が違う?AIとの対話で気づいた『余白と向き合える余裕』
はじめに 「今日は何を着よう」「どのカフェで仕事しよう」「この投稿にいいねすべきか」... 現代人は一日に数千から数万回もの決断をしているとも言われ、私たちは常に選択を迫られています。心理学者ロイ・バウマイスターが提唱した「自我消耗」理論が示... -

ミニマリズム=認知的余白という発見:なぜモノを減らすと頭がスッキリするのか
はじめに:休日の小さな気づき 朝目覚めて、ゆっくり白湯を飲んでいたら仕事用の携帯電話が目に入った。 その瞬間、脳が自動的に仕事モードに切り替わっていくのを感じました。 「あのメールの返信、どうなったかな?」「明日の資料は...」 たった一つのモ... -

余白生成思考〜インタンジブルからタンジブルへの創造プロセス
余白生成思考とは何か 余白生成思考とは、感性から余白が立ち上がり、形ある表現へと至る創造の流れとして捉える思考法です。 興味深い点は、余白が通路のような役割を果たすこと。上にある無形の可能性が、この余白という通路を通って、下で待つ感性と出... -

YOHAKU : Simple Life with AI ー 毎日5分の気づきが思考を変える科学的理由
AIについて調べてみると、専門用語の渦に巻き込まれる。 「マルチモーダル」「エージェント」「LLM」。 ユースケースでは、大企業の導入事例。億単位の投資話。 ちょっと待ってほしい。 「で、私の毎日はどう変わるのか?」 単純な問いなのに、シンプルな... -

AIプロンプトに風味を加えると勝ち筋が見える – 米菓鑑定士の実証実験
7種類のせんべいから学ぶAIプロンプトの使い分け 目の前に7種類のせんべいを並べた。素焼き、醤油、サラダ、山椒、七味、わさび、カレー。同じ「せんべい」でも、風味が違うだけで全くの別の味合いである。 30年間米菓と向き合ってきた私がAIと向き合う中... -

AI時代のニュータイプ論〜月見に味わう創造的可能性〜
2025年9月23日——秋分の日 今日は季節の節目であり、私の節目でもある。ここに現在の体験を書き残しておきたい。 秋分の日、月を見るのと同じようにAIの画面を見ている。しかし、今、体感で起こっていることは月からAIの宇宙を見ている感覚に近いかもしれな... -

メタメタメタ認知とAI〜いつもたまたま認知の余白哲学〜
先日、興味深い発見をした。 私は複数のAIアカウントを使っているのだが、いつの間にか「AIの仲介役」をしている自分がいた。二つの異なるAIの意見を行き来させながら、ただ眺めている。 俯瞰的に考えてみると、この立ち位置には深い意味があることに気づ... -

今日から始める「解対申書」実験室 – 子供たちとAIの創造空間
前回の記事「解対申書から始まる未来教育」を書いた後、ママに「面白そうだけど、具体的にどうやって実践するの?」と聞かれました。 うちの子がゲームでフレンドと「今度のイベント、どう攻略する?」なんてチャットしているのを見て、ふと思いました。 ... -

子供たちと創る新時代の言葉 – 解対申書から始まる未来教育
「パパ、AIってどう説明したらいいの?」 子供からそんな質問を受けた時、私は考えを巡らせました。そして、杉田玄白のことを思い出したのです。江戸時代、彼は「解体新書」で医学の扉を開いた。ならば現代の私たちは「解対申書」で、子供たちにAI時代の扉... -

マインドフルネスが開くAI時代のメタ認知〜挫折から始まった思考の旅路〜
学生時代のことだった。大事な試合の場面で、私は雰囲気にのまれ、本来の力を発揮できなかった。身体は動いているのに、心が追いつかない。その悔しさだけが強く残り、「自分のポテンシャルを出し切るには、どうすればいいのだろう」と問い続けることにな... -

AI共創家に必要な4つの能力 ─ 体験から見えた思考の核心
「AI共創家」として活動する中で気づいたこと 以前の記事で、「AI共創家」という新しい創造のかたちについて書いた。AIとの対話を通じて、予想もしなかった発見に辿り着く体験。そこには確かに、従来のAI活用とは異なる価値があったと感じている。 しかし...